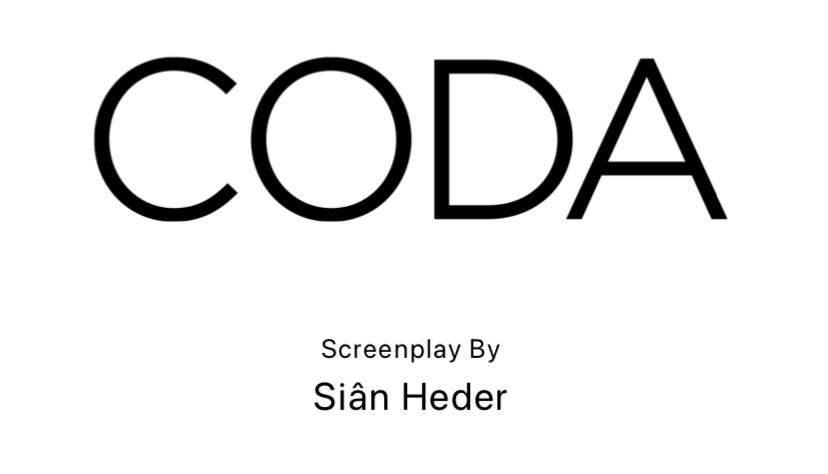久しぶりのたのしいブックレビュー、読み語りにおすすめの本を紹介します。
「あっ、ひっかかった」 オリバー・ジェファーズ作・絵 青山南 訳
(徳間書店) 1650円 ユーモアたっぷりの絵本です。
1.jpg)
フロイドくんが凧揚げをていると・・・
凧が木にひっかかった。
これはよくあることですね、私もこどもの頃、経験があります。
ところがこの絵本、予想をはるかに超えてすすんでいきます。
凧をおとそうとして、お気に入りの靴を投げたけど・・・
それもひっかかってしまいます。
くつをおとすために猫を連れてきて
どうするのかと思ったら、フロイドくん、猫をなげてしまいました。
すると猫も・・・
いったいどうなっていくのでしょう?
2.jpg)
この作品をたくさんのこどもたちに読み語ってきたのですけど、はじめのうち「えーーー」「ありえない〜」と言いながら見ていて、そのうちに、大笑いしてくれました。
以前、たのcafeでいっきゅう先生が「こどもは作品そのものも楽しんでくれるけど、こういう絵本を自分たちと一緒にたのしんでくれる大人がいることも、こどもたちにとってはとても嬉しいことなんだ」と話していました。
みなさんもぜひ、こども達に読み語ってみませんか。
ところで絵本をたのしんだこども達は「あ~たのしかった」で終わることはありません。次回はその絵本から広がる世界について紹介しましょう。
たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!


 全体の構成がほぼ同じな上に、脚本がネット上で上がっていたので、それを読んで感動していたのですけど、映画そのものは更にすばらしい作品でした。
全体の構成がほぼ同じな上に、脚本がネット上で上がっていたので、それを読んで感動していたのですけど、映画そのものは更にすばらしい作品でした。