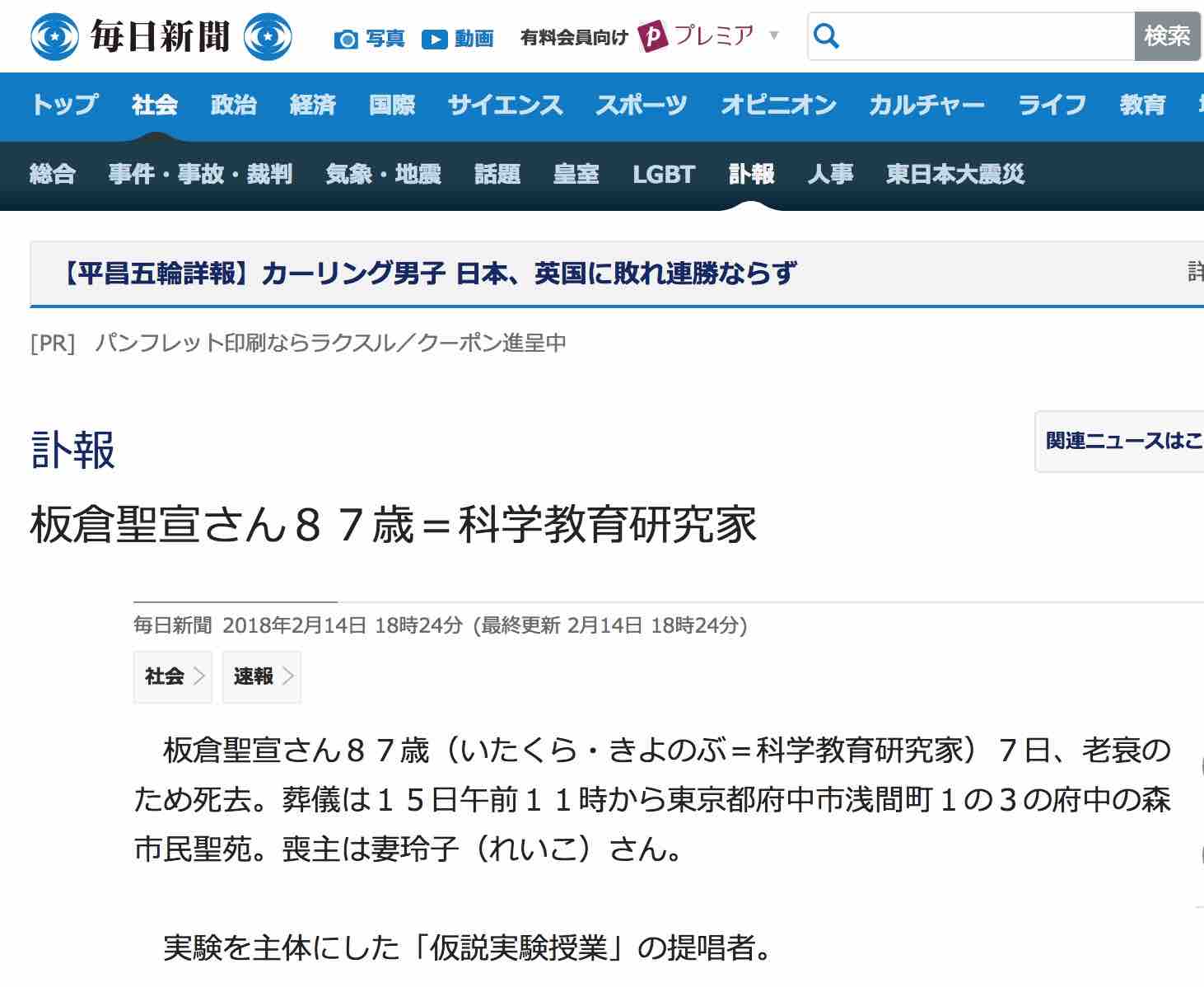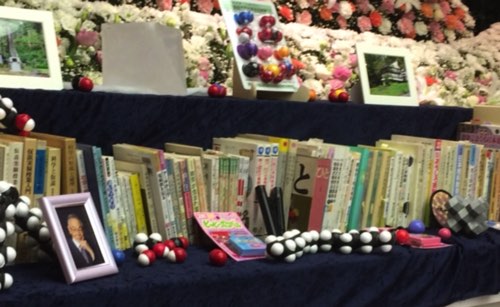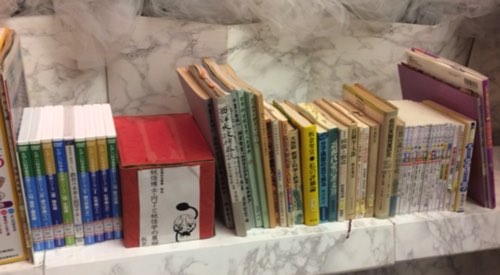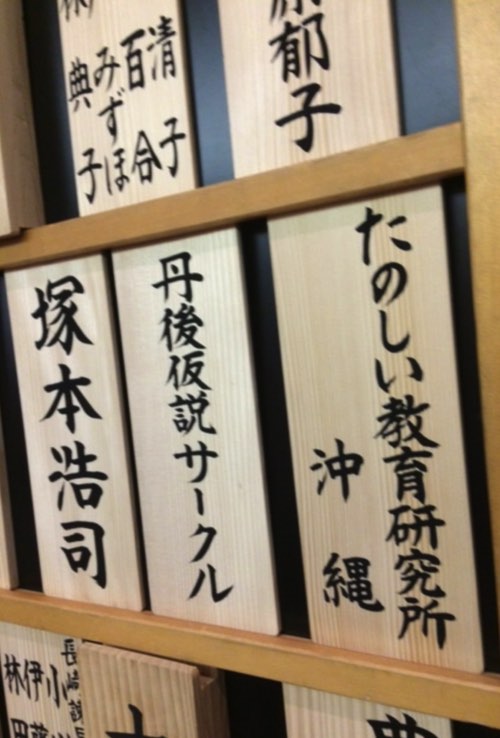今回はたのしい教育メールマガジンで評判の実験の一部を紹介します。とても簡単ですよ。
ここに、ペットボトルに入った液体があります。※見やすくするために、ここではペットボトル入りの紅茶を利用していますけど、飲んで後に水を入れて試してみてください。

その中程を真横にカッターで5cmほどカットします。

切っている途中いくらか液体がもれてしまいます。

しかし、その後は水がほとんど出て行きません。

切り口がピタリとくっついているからだと思うでしょう?
けれど、指で切り口をこじあけてみてもこぼれませんよ!

プリンやゼリーを食べる時のスプーンの柄をカットして、この切り口に挟んでみましょう。

こんな具合にしても、水は流れ出ていきません!

ストローを突っ込んで飲むこともできますね。

中が水なら、こうやって植物を育てたり、グッピーなどの小さな魚を飼って、この開き口からエサをあげたりできます。

謎解きは、それぞれで挑戦してみるとよいですね。
いかがでしょうか。
ペットボトルがあればできる簡単でたのしい実験でした。 〈いいね!〉 このいいねクリックで〈たのしい教育研究所〉が強くなる!




 こういう笑顔をたくさん増やし、賢く元気な子ども達を育てようと思います。興味ある方は一緒に活動しませんか? ボランティア募集中です。
こういう笑顔をたくさん増やし、賢く元気な子ども達を育てようと思います。興味ある方は一緒に活動しませんか? ボランティア募集中です。