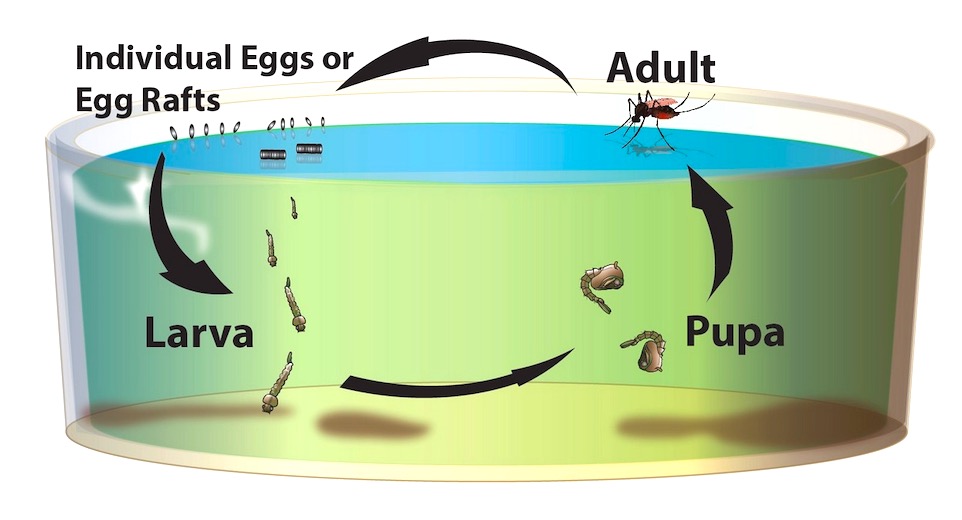最新メルマガの授業の章に書いた〈たのしい算数の問題集〉の一つの問題にさっそくいくつも反響が届いています。
100円玉(下)の円周上から離れない様にもう一つの100円玉(上)をぐるりと一周させます。上の100円玉は何回転するでしょうか?
という問題です。
知っている人もいるかもしれません、そういう人ももう一度考えてみてくれませんか。
⬇︎
予想してからね
⬇︎
同じ100円玉同士ですから円周の長さはピタリと一致します。
当然1回転することになりますよね…
ほんとうでしょうか?
やってみましょう。
実験
ここからスタート

時計回りに回転しはじめたところです

あれ、真横に来た段階で回る側の100円田は半周(180度)回っています

そろそろ真下まできました・・・

真下に来た段階で回る側の100円玉は一回転しました

右半分は回り終わって左側の回転に入ります

さっきと同じ様に左半分で180度回転し

そろそろ真ん中の100円の円周上を一周します
 これで一回りしました、回っている100円玉は二回転したことになります
これで一回りしました、回っている100円玉は二回転したことになります

答えは〈2回転〉です
これは簡単に実験できるので自分でもやってみるとよいでしょう。
ところで、同じ100円玉なのに、回る方はどうして2回転することになるんでしょう、おかしくないですか?
しばらくたのしめると思いますよ。
② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります