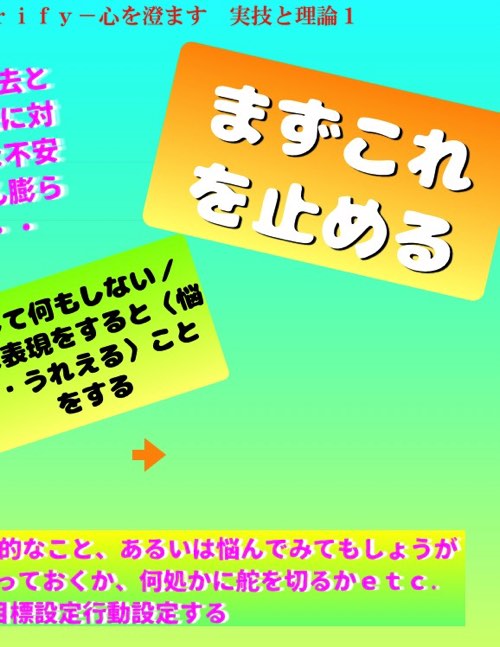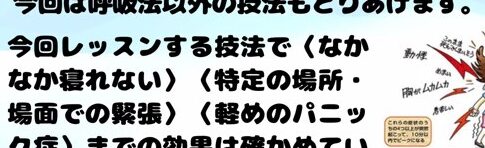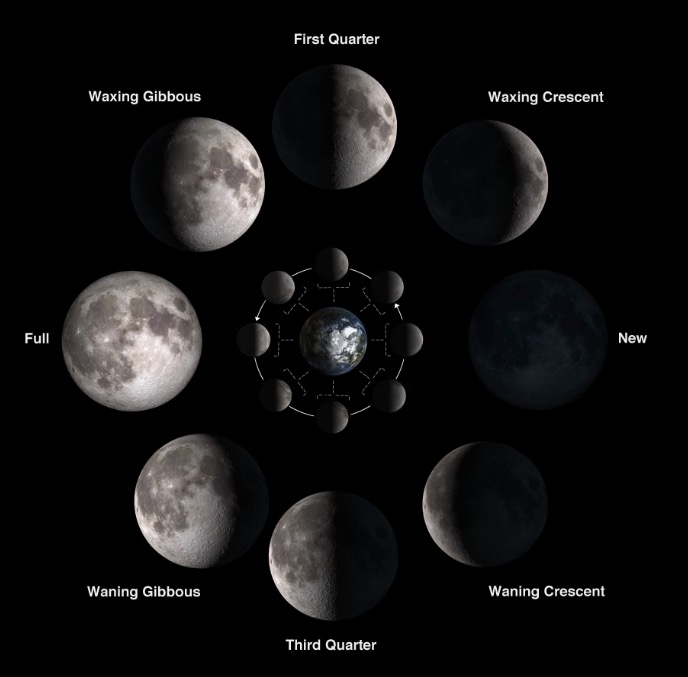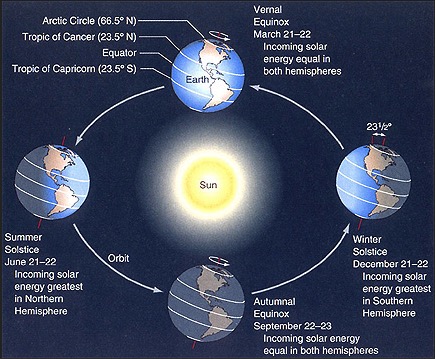みなさん、こんにちは。
今年もスタッフ一同、「子どもたちの笑顔」をイメージしながら教材づくりなどたのしく進めていきます。今年もよろしくお願いします。
さて、学級の子どもたちと過ごす時間もあと3ヶ月。思い出に残る日々にしていきたいですね。毎年大好評の「春の講座」のお知らせです。
ー受講した次の日に同じようにたのしく授業できますー
ーーーーーーーーーーーーー
2023年 春の講座
出あい も別れも たのしい教育
ーーーーーーーーーーーーーーー
参加人数には限りがあります、お早めにお申し込みください。

①みんなで仲良くゲームプラン
② パーティーでもりあがる〈クイックちんすこう〉づくり
③出会いと別れを彩る〈ものづくり〉
④思い出にのこる読み語り
⑤いっきゅう先生の〈思い出に残るたのしい教育授業書〉
⑥たのしい教育教材の紹介 他
★ お問合せ 090-1081-7842 (平日 18:00まで)申し込み★★ 下記QRコード、URLからhttps://forms.gle/FaVjS5AwTPfKVebo8
メールからも可能 ⇨office@tanoken.com
件名に「春の講座申し込み」と書き ①名前 ②所属(会社・団体・学校学年など)③ 電話番号(緊急連絡に利用) RIDE会員の方は「RIDE会員」と明記して申し込みください(週1回のメルマガが届いている方は会員です)※受講の可否メールが研究所から3日以内に届きます、届かない場合はお電話ください
講師代表:いっきゅう先生(喜友名 一)たのしい敎育所所長。アメリカNASAと連携し宇宙に滞在中の〈若田光一宇宙飛行士〉と地上を結んだ教育イベントを成功させ、自らも1000人近くの参加者に一斉授業するほか〈たのしい教育〉の第一人者として活躍。マスコミにも多数取り上げられている。学校教師を早期退職し「たのしい教育研究所」を設立。県内だけでなく全国そして海外を飛び回る。国や県との連携、医師会の要請で副読本を作成するなど幅広く活動中。
ride.i.tanoken@gmail.com
② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります