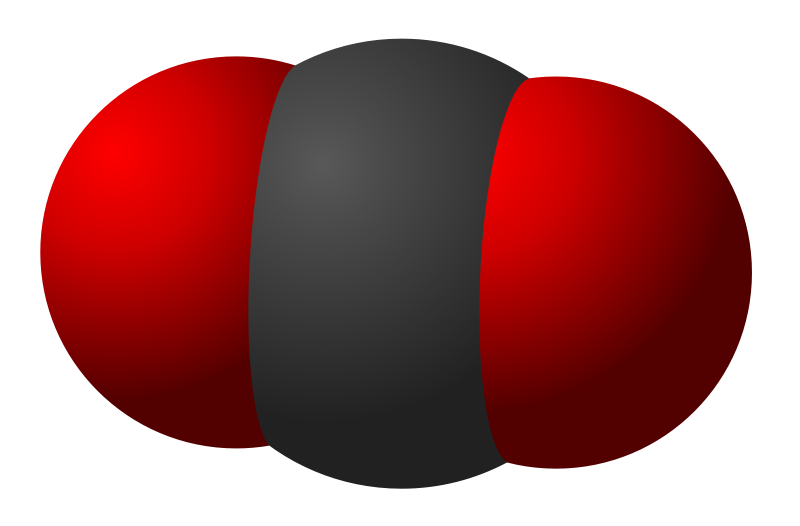私の愛読する雑誌Be−PALでカヌー旅を連載していた頃から大好きだった野田知佑さんが他界した、2022年3月27日に生を閉じ、広く告知されたのは私が年度まとめの〆切に追われて夜中まで数字とにらめっこしていた30日のこと・・・
これは在りし日の野田知佑とカヌー犬ガクの姿。

84歳だったんだな。
野田知佑さんのことはこのサイトにも以前、とりあげたことがあります。
先月の〈たのしい教育メールマガジン〉の「発送法の章」にはさらに詳しく書きました、書き抜いてみましょう。
=================
たのしい教育の発想法
反論の技法
いっきゅう2022.02.08
================
いっきゅう
公式サイトに野田知佑が語った「力のない奴に限って横文字を使いたがる」という話の評判がよく、いくつか便りをいただきました。その一つから、私の記憶していたその話の出展は「文芸春秋社刊 本日順風(廃刊)」だとわかりました、ありがとうございます。
読者からの質問に野田知佑が答えるという形式でまとめられた本です。さっそく読み直して、久しぶりに野田節の爽快な感覚を味わっています。
その中から一つ反論の例として取り上げさせてください。
野田知佑はカヌーで自然を味わうことを生きがいとしていて、環境保護についてもハッキリ物言いする人物です、ダム建設反対運動には積極的に関わっています。
それに対してある読者からこういう批判が届きました。—--—
果たし状
野田知佑に物申す。
どうしてなんでもかんでもダムに反対するのだ。
俺はダム作って飯を食っている、妻子を養っている。
文句あるなら一対一で勝負するから俺をねじ伏せてみろ。
宮城県岡本直義28歳建設業
—--—
いっきゅう
さてみなさんならどう答えるでしょう。
ダム建設に賛成か反対かによって違うとは思うのですけど、建設反対の野田知佑はどう答えたか?
反論の仕方の流れという視点でごらんいただこうと思います。
ところで〈たの研〉は「批判ではなく提案をする組織」だからなのか、これまで批判らしい批判を受けたことがありません。
とはいえいわれのない批判が来た時、ケンカは避けるとしても、しっかり物申さなくてはいけない場合もあるでしょう。そういう時に冷静に整えて相手に伝えていくことになるでしょう。
対して野田さんは血の気が多く、相手がケンカモードで来ていると察して、後半には荒い言葉づかいになっています。それはまぁ野田さん一流の物書き技法だと思って、真似はしないようにするとよいでしょう。
—-
野田知佑
現在、日本国中で建設中のダム、または建設を計画しているダムは500ある。そのうち本当に必要なダムがいくつあるのか?
建設庁や県の土木課はいつもの例でもっともらしい理由を挙げるだろう。
曰く
1.洪水防止
2.農地への灌漑用水を得るため
3.発電のため
4.飲料水を得るため
——
と、まずダム建設としてあげられている理由を列記しています。その後一つ一つについて反論していきます。—-
野田知佑
まず1について。
現在、日本の洪水の恐れのある川でダムを持たない川はない。ダムを作るべき川にはすでにみなダムを作ってしまっている。少なくとも現在建設中および将来作られるダムに関して言えば、その建設目的は治水とは別のものだ。例えば建設庁か県庁か市町村役場と土建業界と建設族の政治家との癒着、土建業者のための仕事を作るためのダムだ。治水のためなら50年で埋まってしまうダムより、山に木を植える方がより効果がある。
2の農業用水についていえば、たいていそこの農業は後継者がいない、減反している。つまり農業用水を使う見込みのないところである。
3,4、電力会社のパンフレットにはそう書いていないが、現在わが国では電力は余っているのだ。ごくわずかの地区を除いて水も余っている。
ちょっと図書館に行って行政側ではなく民間の学識者の書いた本を読んでいただきたい。水不足、電力不足の話は作り物だ、ウソなのである。なぜそうするのかといえば、ダムや原子炉などの巨大なものを作りたいからだ。
日本には現在、適正数の約三倍の土建業者があるといわれる。普通なら食っていけないはずの土建業者が食っていけるのは、工事をつくることによって利益を得る政治家、官僚が多いからだ。
そのことは金丸信の事件によって明らかになった。
いっきゅう
ここで終わるわけではありません、さらに伝えたいことに進みます。
—
野田知佑
さて投稿の件に移る。
ボクは全てのダムに反対しているのではない。作られてしかるべきダムもあったのだろう、過去には。
しかしここ二十年間に作られたダムで本当に必要なものがあるなら、ボクはぜひ知りたい、教えてもらいたいくらいだ。
住民や市民の声がどれだけダム計画、ダム建設の時に吸い上げられ反映されているか。全てお上の一方的な決定によるものではないか。
先進国の例をみると住民数百人、数千人の反対でダム計画は潰されている。
日本のダム建設のゆき先を見て日本は民主国家ではない、ひどい土建屋独裁国家だと思っている人は多い。
ダム建設で食っているのなら、マンガばかり読んでいないで少しは日本のダム問題について勉強しなさい、それから文句を言え。
——
私としてはここからが爽快でした。
—
野田知佑
もう一つ、この種の問題とキミが妻子を養っている話はぜんぜん関係がない。
自分の仕事の話に妻子を持ち込むのは卑怯である、公私混同してはいけない。
山賊が「オレは人を殺してメシを食っている、それで妻子を養っている」言って自分の仕事を正当化しようとしたら、キミなら何というかね。
いっきゅう
批判を正面から受け立つことは疲れるので軽く受け流すことが楽に生きるコツでしょう。私は武道家なので正面から受けて立つことも苦手ではないのですけど、そういうことは避ける様にしています。
勝敗に関わらず負の荷物が増えていくからです。
批判に受けて立つ立たないは別にして、受けて立つと〈負けるに決まっている〉というのは残念なことです。特に自分が大切にしているものへの批判を跳ね返す力は持っておく必要があるでしょう。
その意味でも、批判に対して受けて立つ人の論理組み立てを見ていくことは悪くないと思うのですけど、どうでしょうか。
たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!