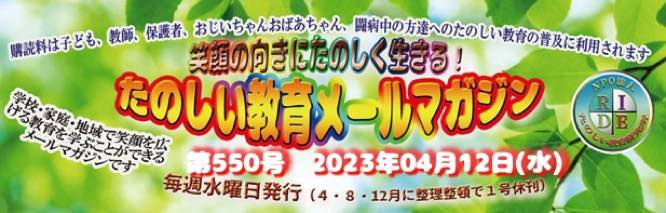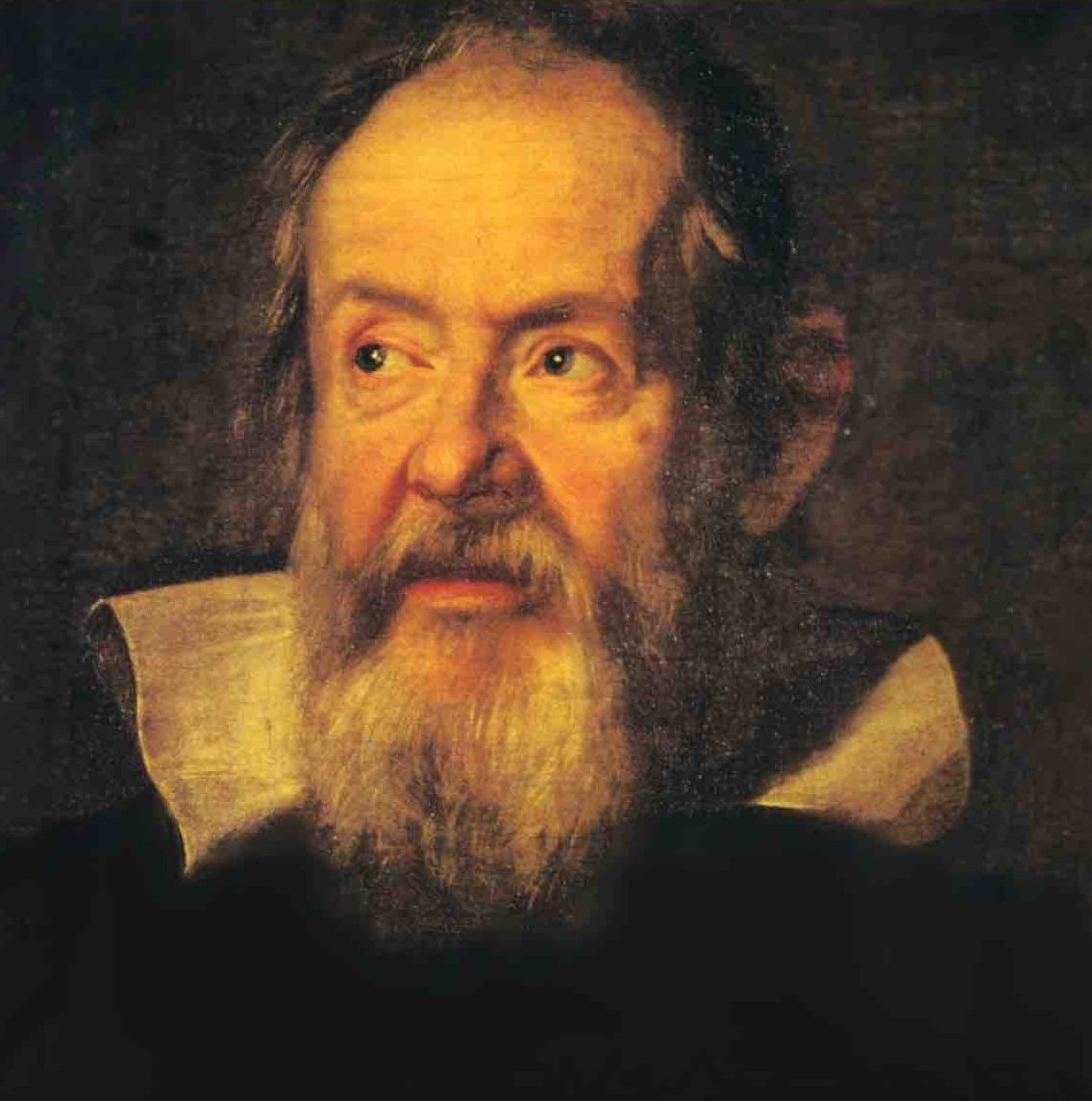※前後してUPされていた時間があります、この記事から先に読んだ方は一つ戻ってお読みください。空手には先手がない、では突き・蹴り・受け・気合いそれらを何のために学ぶのか、子ども達にどう語るのか?
大会などに出て華々しい成果をあげたいという目標で空手を修行する人もいますから、それはそれで成り立つでしょう。また私の様に道場を開きたいという人にも学ぶ意義はあるでしょう。しかし実生活で何の意味があるのでしょう。
健康増進、たしかに。
でもそれを子ども達に伝えて学ぶ意欲が増すでしょうか?

前回投げかけたのは「蹴りはこう、突きはこう」というような実際の動き・ノウハウとは違います、発想法、哲学の部分です。
みなさんはどう考えたでしょう。
※
空手の有段者として、武道の心得があるものとしての今の私に具体的に役立っているものは何か?

「空手に先手なし」です。
私は師の仲里周五郎(無形文化財保持者)から「喧嘩を買っても、買ったものを捨てよ」と言われていました、徹底的に「戦うな」です。
ではこれだけ学んできたもの、その身体の動きはいつ使えばよいのでしょう?
それは危機的な状況です。
目の前で誰かが襲われそうになっているのを見て見ぬふりするのか?
あり得ません。
他にも危機的な状況はあるでしょう、その時にはじめて学んだ技を活かす。
ではそういう機器的な状況がこれまで何度現れたのか?
ゼロです。
私は実生活で危機を突破するために空手の技を使ったことがありません。
これだけ何十年にも渡って修行した技を実生活で使う機会がない・・・
バレーボールをやっていたら年に一回くらいはヒーローになる機会があるのにね。
実生活では使わないものを学び続ける意義は何か?
このサイトにも時々アップしているのですけど、私は一人で山に入ることがあります。野営・キャンプする時なども、あれこれ心配せずゆっくり過ごすことができる、ということです。組手は素手の一対一の流れです。ただし練習では、相手が凶器を持っている想定、また複数の相手と対峙する時の練習も重ねてきました。練習とはいえとてもスリリングです。武道を修行している人たちを三人倒すというのは大変ですけど、普通の人たちを三人倒すというのは本気で空手を学ぶものにはそれほど難しくないと思います。
万が一のことに対する構えがしっかりできていると、自由度が増えます。
その自由度はつまり、いろいろなことを心配することが少なくなるということでもあります。
そしてそのエキサイティングな練習は実にたのしい。
DNAの中に刻まれているハンティング的な心の動きなのかもしれません。
普通の暮らしの中でこういうワクワクドキドキ感は得られないでしょう。
武道によって、たのしい、そして行動の自由度が増える、それは何らかの決断をすねるときにも大きく影響するでしょう。
今の時代、日常で使うことのない武道を学ぶ大きな意義はそこにあるでしょう。
それが武道の哲学です。
では武道の理論・空手の理論とは何か?
相手が顔を殴ってきたらどう動けばよいのか、という話にもどりましょう。こちらの周りの状況、相手の身体の向き、飛んでくるパンチのスピードなどいろいろなファクターが関わるのですけど、基本は〈飛んでくる力を自分の身体以外の空間に流す〉ことです。空手の受けもサバキも基本はそこです。
攻撃は千差万別でも基本は千差万別ではありません。
生き方に哲学や理論がある様に、空手にも哲学や理論があります。
その基本(理論)を学ぶことによって、実際の動き・ノウハウの部分もしっかりしていくでしょう。
少々長くなってしまいました、とりあえずここまでにしておきます。
① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!