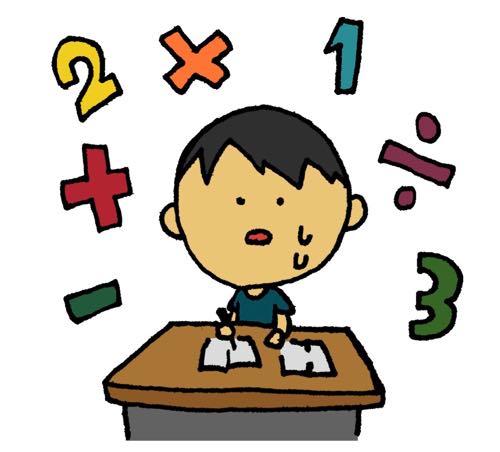たのしい教育研究所のベランダでもいろいろな実験が行われています、これは最近花開いた〈菜の花〉、清楚できれいです、何の花だと思いますか?

「え、菜の花は菜の花でしょ、〈◯◯の菜の花〉なんてあるの?」と思う方もいるかもしれません。
菜の花にはいろんな種類があるんです。
とはいってもみんな「アブラナ科」の植物の花です。
アブラナ科の植物というと、ハクサイ、カラシナ、コマツナ、カブ、ダイコン、ミズナ、チンゲンサイ、キャベツ、ブロッコリー まだまだあります・・・
花の形などもとてもよく似ています。
この菜の花は〈ダイコンの花〉です、ダイコンはダイコンでもカイワレダイコンです。
初夏の講座のプログラムの一つ〈カイワレダイコンを育てていくとダイコンになるというプログラム=カイワレダイコンを育てよう〉で使った教材をベランダに置いて水やりしていたら、きれいな花を咲かせました。

ベランダのある側には三、四階の建物があって日当たりがよくなく、晴れの日でも2~3時間くらいかな、土の中でひょろっとしたダイコンになっているのですけど、花をみると「カイワレダイコンもダイコンなのだ」とわかります。
ダイコンにもいろいろな品種があるので、ムラサキ色ではない菜の花もあるのですけど、みなさんも菜の花、ダイコンの花について調べてみませんか。
きっと野山や公園を歩く時にも「あ、あれも菜の花だ」とたのしく歩くことができるようになると思います。
① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!