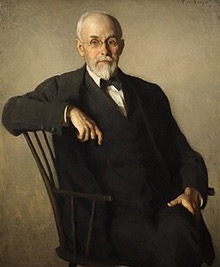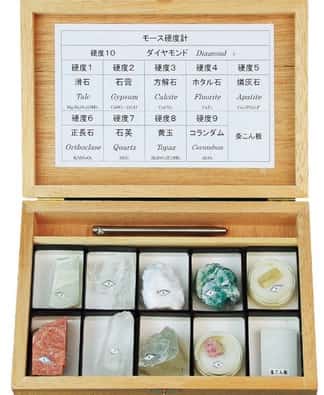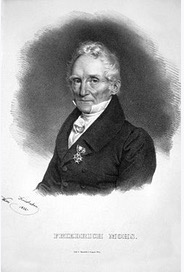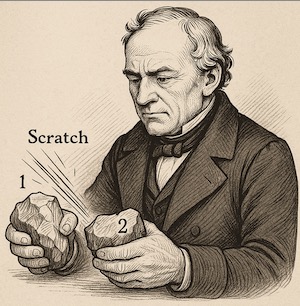私自身は毎日届く新聞も読みませんし、テレビは録画した旅番組や「チコちゃんに叱られる」くらいしか観ないのだけど、読者の方からニュースやネット情報がたくさん届きます、おかげで普通にニュースなどを収集する方たちの2割くらいは情報を得ることができます。
最近届いた一つが
「日本人は親から〈周りの人たちに迷惑をかけないようにしなさい〉と教えられ、インド人は親から〈自分は周りの人たちに迷惑をかけているのだから周りの人たちの迷惑を許してあげなさい〉と教えられる」という話。
面白い話です。
インド人の教えっていいですよね、という話も加わっていました。
日本の多くの親の教えがよいのか、インドの多くの親の教えがよいのか、片方ではなく両方必要なのだと思います。
私にとってアウトドアの座右の名著が『河口慧海 チベット旅行記』です、その話を聞いた時にその『チベット旅行記』の話を思い出していました。
チベットはインドの北の方に位置していて、近い考えをするのかもしれません。
チベット旅行記には、さらに面白い発想が紹介されています。
恐ろしい強盗の話で、アクが強いので部分的に編集して紹介します。少し長いのですけど、読んで損はない話です。
さてその翌日もその寺で泊り込んでいろいろその地の事について研究しましたが、夜はやはり禅定に入ってその楽しみを続けた。
その時の楽しみは一生忘れられません。その翌日は非常に厳い坂で三途の脱れ坂というのを踰えねばならん。ところが幹事は誠に親切な人でヤクを貸して上げましょうという。
私とは余程深い縁があると見えて出来得るだけの親切を尽してくれいろいろな喰物もくれました。そのヤクに乗って一人の人に案内されて恐ろしい坂を登って参りました。
するとチベット人の妄信といってよいか信仰力といってよいか、仏陀に対して自分の罪業を懺悔し自分の善業を積むという熱心は実に驚くべきほどで、その山を一足一礼で巡るという酷い行をやって居る者もあるです。
それらは大抵若い男女がやって居るので老人には出来ない。ただ登って行くだけでも随分困難を感ずるですからとても若い者のような具合には行かない。
私はヤクに乗って登ってさえも随分苦しい。何故かならばいかにも空気が稀薄ですから、三途の脱れ坂を二里ばかり登りますと非常に疲れて呼吸が大分苦しくなったから少しは薬なども飲むつもりで休みました。するとそこで面白い話を聞いたです。
それは向うの釈迦牟尼如来といわれる雪峰チーセに対して礼拝をして居る人がある。その人はいわゆる強盗の本場であるカムの人です。様子を見るに実に獰悪なまた豪壮な姿であって眼眦なども恐ろしい奴ですから、強盗本場の中でも一段勝れた悪徒であろうと思われたです。その悪徒が大きな声で懺悔をして居る
未来の悪事の懺悔
その懺悔のおかしさと言ったらないです。
なぜならばおよそ懺悔というものは自分のこれまでした罪業の悪い事を知って其罪を悔いどうかこれを免してくれろ、これから後は悪い事しないというのが一体の主義である。
しかるにその人らのして居る懺悔は実に奇態で私も聞いて驚いたです。その後ある人に聞きますればカムの人がそういう懺悔をするのは当り前である。誰でもその通りやって居るという。だから私は実に驚いた。それはどういう訳かというとこういって居るのです。
ああ、カン・リンボチェよ。釈迦牟尼仏よ、三世十方の諸仏菩薩よ。私がこれまで幾人かの人をあやめ、あまたの物品を奪い、人と喧嘩口論をして人をぶん撲った種々の大罪悪を此坂で確かに懺悔しました。だからこれで罪はすっかりなくなったと私は信じます。これから後私が人をあやめ、人の物を奪い、人をぶん撲る罪も此坂で確かに懺悔致して置きます。とこういう事なんです。
実に驚かざるを得んではありませんか。
慧海さんが紹介しているのは、「私はこれからたくさんの罪をおかす、と懺悔します。、だから神さま、それを許してください。はい、これで私のこれからの罪もなくなりましたね!」というわけです。
迷惑や罪は許されるべきものだという発想を突き詰めていくと、こういうところまですすむのでしょう、すごいですよね。
周りの人たちが苦しむ姿は減らしたいし、それでも迷惑をかけるのは仕方ないことで、自分も許してあげよう、ということになるのでしょう。
① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!