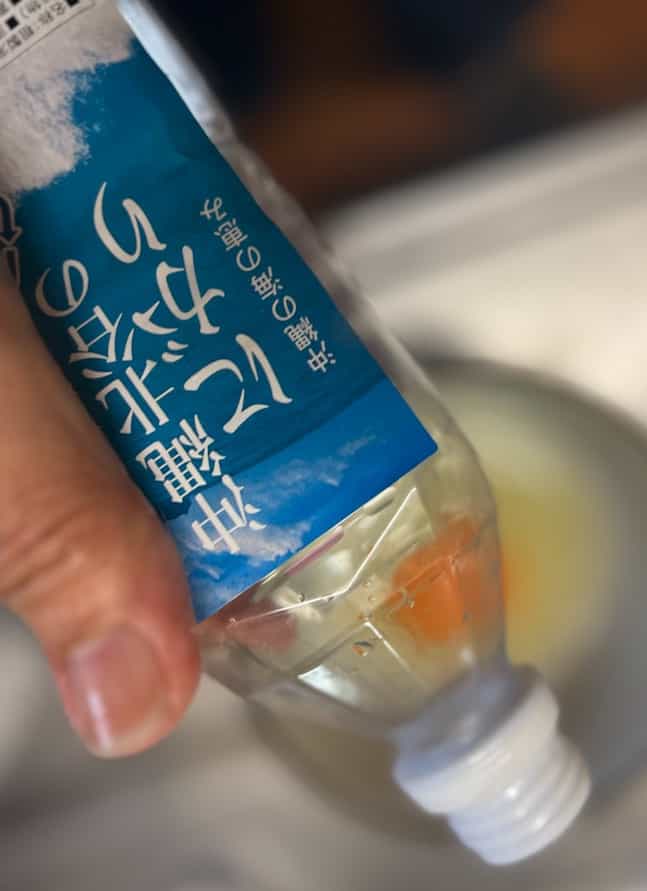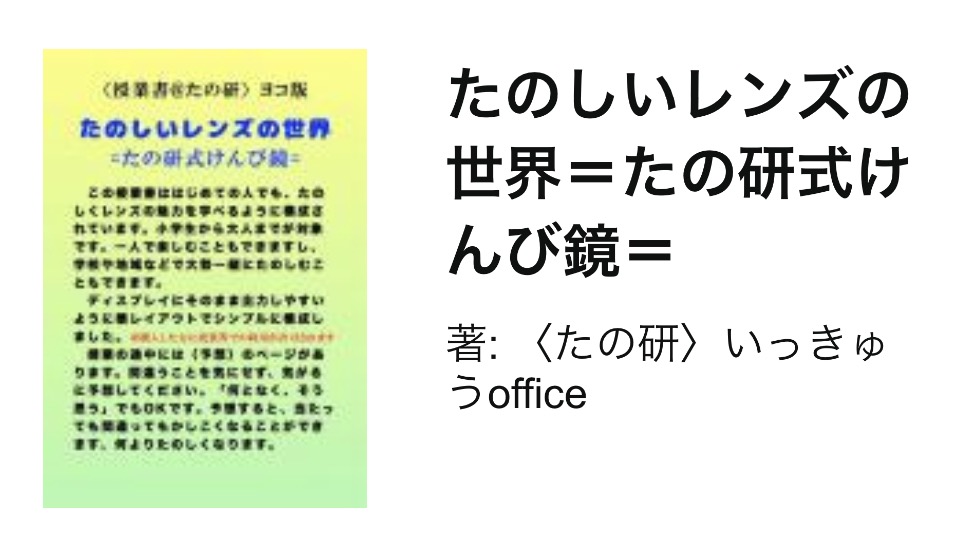欲しいという方には有料で受け付けています。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

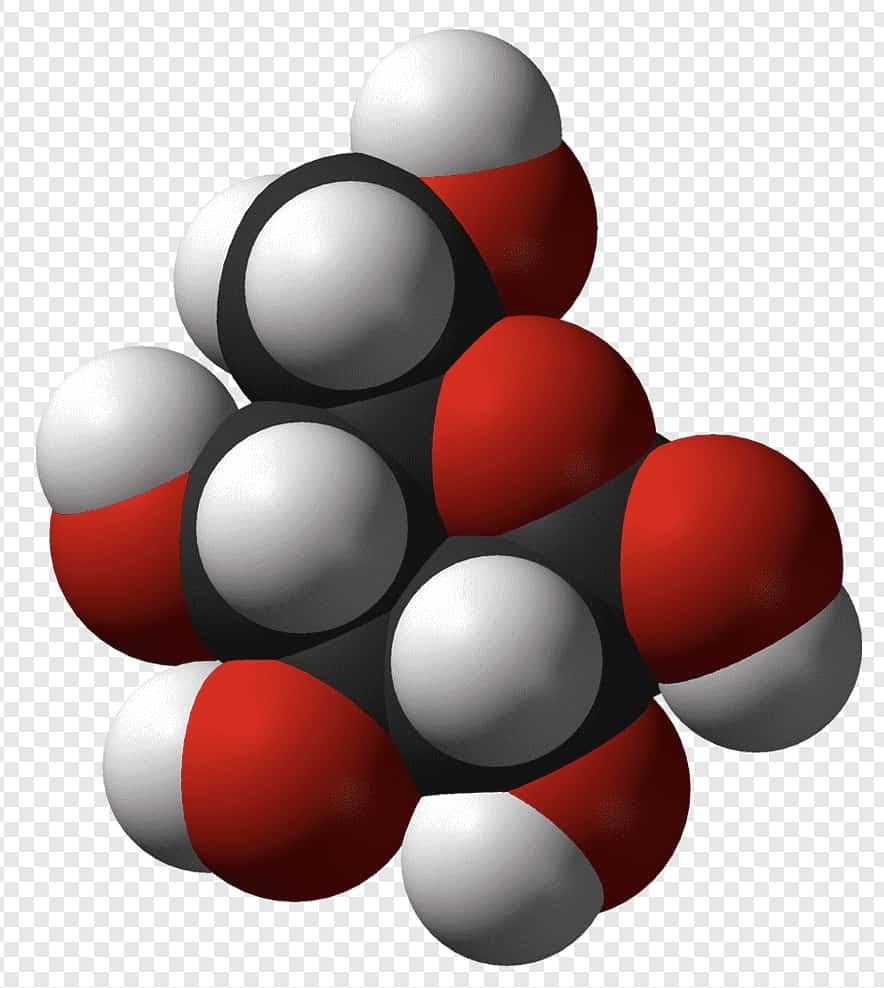
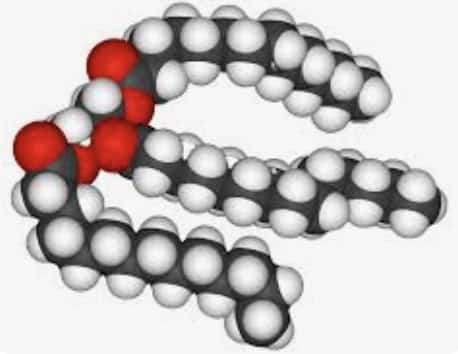
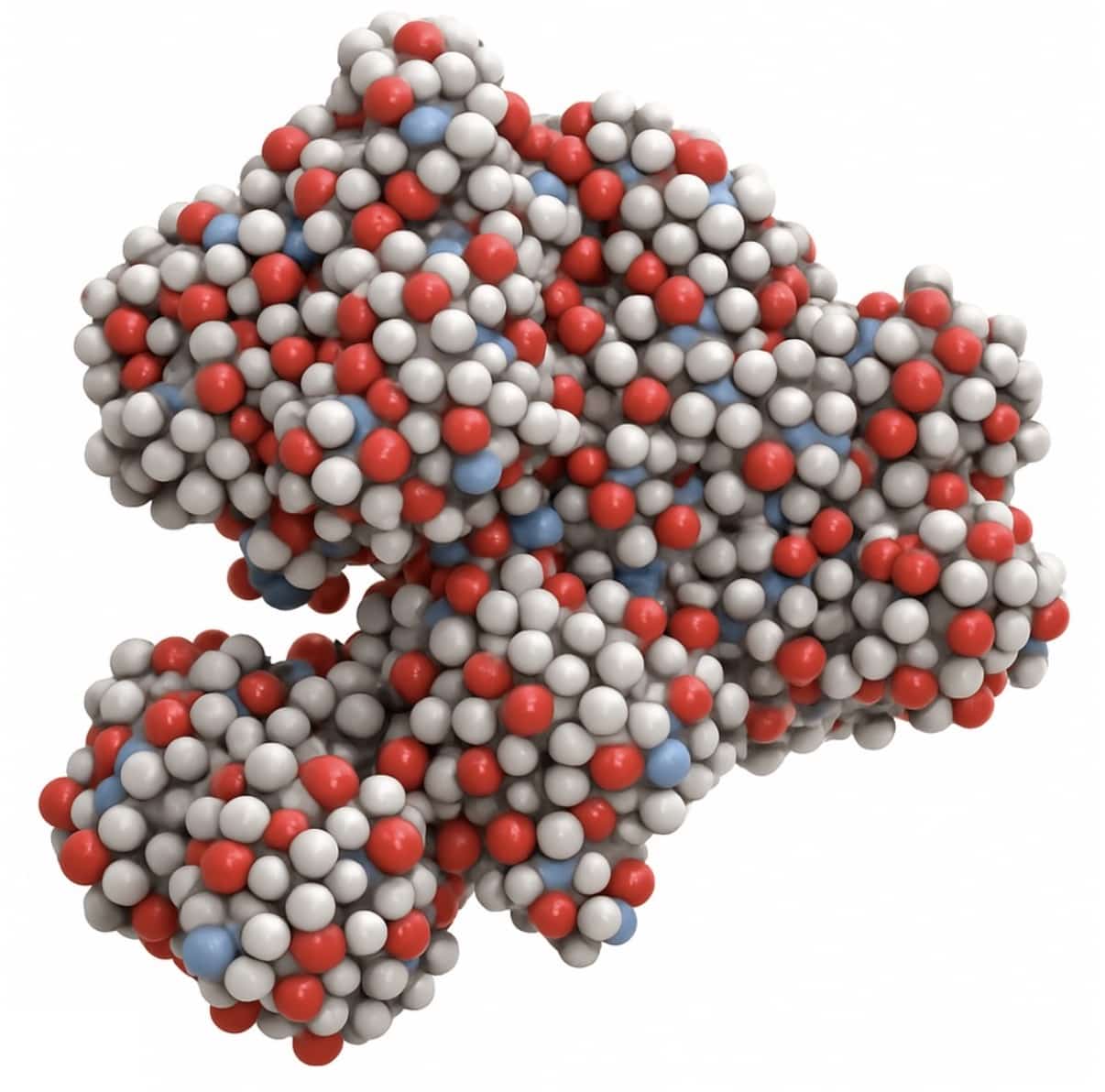
 ニガリはスーパーにある多くのものは弱い・薄いので、濃いものを利用しています。
ニガリはスーパーにある多くのものは弱い・薄いので、濃いものを利用しています。