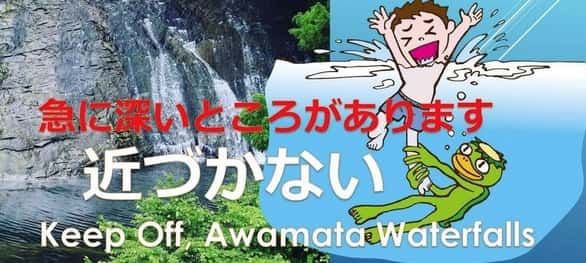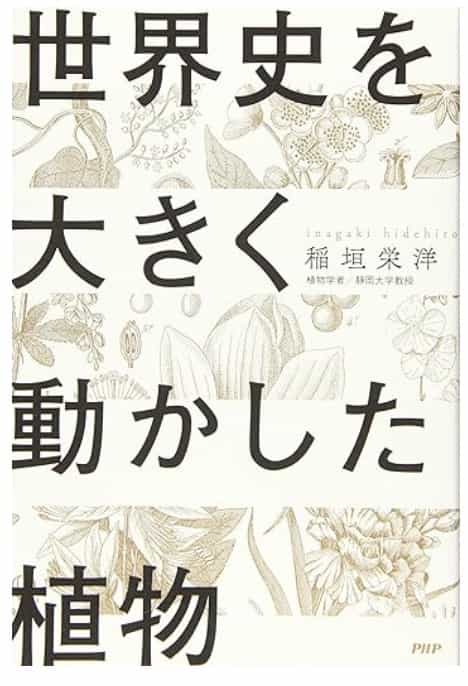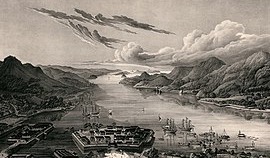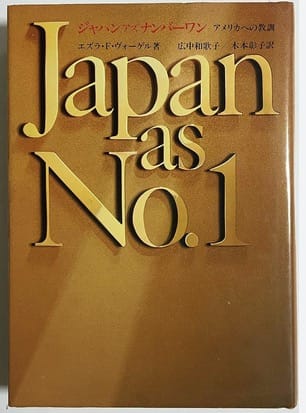大好きな作家に米原万里さんがいます、残念なことに56歳という若さで他界してしまいました。切れ味鋭い文章を綴る達人でした、100歳以上まで生きて、もっともっといろいろな本を残して欲しかったと残念でなりません。

米原さんのおすすめの本はたくさんあって、去年メルマガで『嘘つきアーニャの真っ赤な真実』を紹介したところ、さっそく購入しましたという声がいくつも届きました。
多読の米原さんの書評を集めた如唯一の本『打ちのめされるようなすごい本/文春文庫』も多くの方におすすめです、実に面白い。
その本の表紙裏の著者紹介がよくまとまっているので文芸春秋社に感謝して引用させていただきます。
著者紹介
米原万里 (よねはら・まり)
1950年生まれ。 元ロシア語会議通訳、 作家。
59~64年、 在プラハ・ソビエト学校に学ぶ。
東京外国語大学ロシア語科卒業、東京大学大学院露語露文学修士課程修了。
80年設立のロシア語通訳協会の初代事務局長を務め、95~97年、03~06年会長。
92年、 報道の速報性に貢献したとして、日本女性放送者懇談会賞を受賞した。
著書 『不実な美女か貞淑な醜女か』(徳間書店、新潮文庫)で読売文学賞、『魔女の1ダース』 (読売新聞社、 新潮文庫)で講談社エッセイ賞、『嘘つきアーニャの真っ赤な真実』 (角川書店、角川文庫) 大宅壮一ノンフィクション賞、『オリガ・モリソヴナの反語法』(集英社、集英社文庫)Bunkamuraドゥマゴ文学賞を受賞。
他に『ロシアは今日も荒れ模様』(日本経済新聞社、講談社文庫)『真夜中の太陽』 『真昼の星空」(中央公論新社、 中公文庫) などがある。
2006年5月、 逝去。
※
米原さんは多読家で、多岐にわたる興味関心にまかせてたくさんの本を手にし、〈歯に衣着せぬ〉言葉で、いいのはいい、おかしいのはおかしい、と腑に落ちるように語ってくれています。また教育や政治、〈ものの見方・考え方〉についても折に触れて伝えてくれます。
今回はその中の一つを紹介しましょう。
54ページ《退屈な教科書と大江づく日々》の項に「期待はずれだった」という本(あえてタイトルは伏せましょう)に触れて、こう綴っています。
中学2年の時に帰国し近くの公立中学校に編入した私は、歴史のみならず、あらゆる教科書の絶望的たいくつさ加減にショックを受けた経験がある。
義務教育であるとかテストがあるとかの強制力がないかぎり、一行とて読み進める気が起こらない羅列(られつ)的記述。そこには〈ものを知る〉=〈知らせる〉喜びも、ものごとの本質を極めていく時のあの胸のたかなりも影を潜めているのだった。
それまで小学校の3年から5年間滞在したプラハで通ったソビエト学校の教科書は、どれも読み出したら最後、止まらなくなるおもしろさだった。これは嘘でも誇張でもない。新学期が始まってひと月もすると、大方の生徒が全ての教科書を読破し終えていた。
この「面白くなくては」つまり「子どもが読んでくれなくては教科書ではない」という常識が日本では逆転していて、教科書はたいくつの代名詞となっていた。
客観的記述=羅列という思い込みが日本の教科書を支配していると思った。
日本の教科書の無味乾燥さは、たくさんの人たちが指摘するところで、特に驚かないのですけど「嘘でも誇張でもなく〈ソビエト学校の教科書は、どれも読み出したら最後、止まらなくなるおもしろさだった〉。新学期が始まってひと月もすると、おおかたの生徒が全ての教科書を読破し終えていた」という話には驚いた。
そうか、ドストエフスキー、トルストイ、チェーホフ、プーシキンとかいう世界に名だたる大作家たちを生んだソビエト・ロシアは教科書も読み応えあるものなのだな、とてもうらやましい。
ただ、あえて米原さんに伝えたい。
「国語の教科書の文学作品はいいと思うよ」
ちなみにこのサイトでも以前かいたかもしれません、私が無人島に本を一冊持っていくとしたら、国語の教科書(高校)を手にすると思います。
① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!
④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎