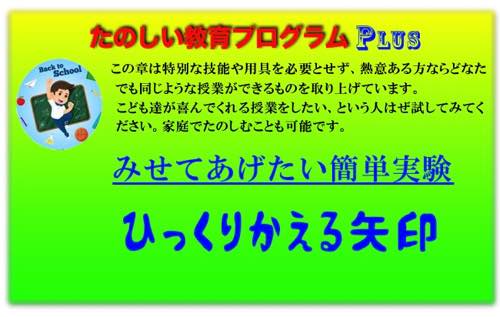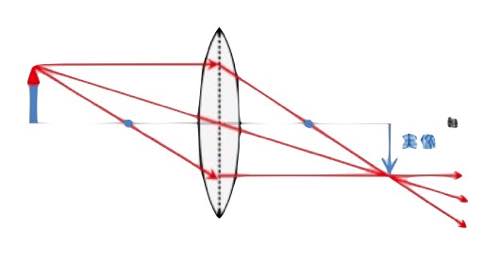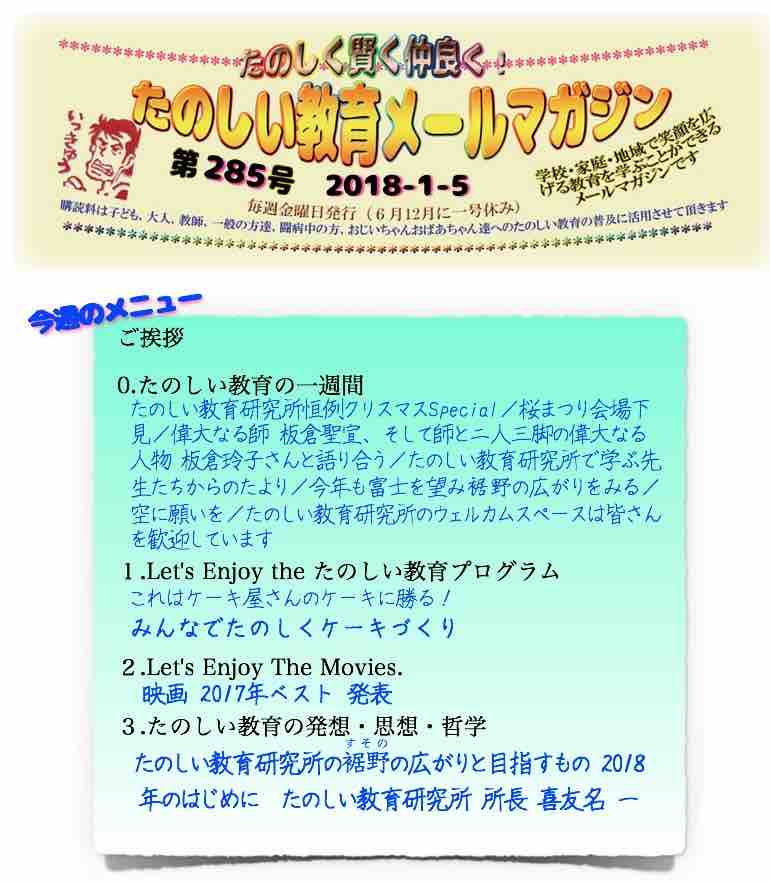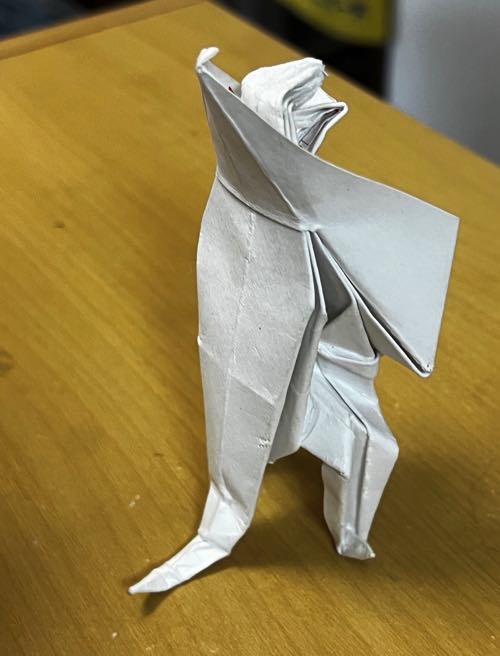季節の風を感じながら散歩をするのが好きで時間をみつけて野山を歩いている様子を時々このサイトやメルマガでも紹介しています。嬉しいことに、いろいろな反響も届きます。
先日の様子を紹介しましょう。
沖縄でイジュという名で呼ばれている〈ヒメツバキ〉の木があります。
沖縄本島の北半分くらいで見られる植物です、紅葉がほとんど見られない沖縄で、部分的とはいえあざやかな彩りをみせてくれます。

〈ギンネム〉の木はいつの季節でも若葉の様な彩りをみせてくれます。

サヤに入ったタネもいっぱい見えます。

特別な場所を歩いているのではなく、おきなわの今日この頃、道端に車を止めて少しあるけばこういう景色をみることができるんです。
さて、前にも少し書いたのですけど、読者の中のたくさんの方たちから「動画配信してほしい」という要望が届き続けています。
スタッフで相談して、この秋から配信実験してみようということでYoutube 動画の作成をすすめています。
このサイトの様にテキストと画像で構成された良さもあります。映像だけでは伝えられないことや、その時の想いなども伝えられるからです。それを自分の好きなスピードでゆっくり味わい、時には戻って確認する。大きくしたりコピーして利用したりも簡単です。
動画で味わう良さもあります、その画面に没入してまるでその場にいる様な感覚を味わったり、風の香りを感じたりできるからです。
文章を綴るのは慣れている方ですけど、YouTubeのような動画は初心者です、準備運動的に軽く2分くらいの動画で作成してみました、両方味わってみてください。
教育系によくある〈わかりやすさ〉より〈音楽を聴きながら軽やかにみてもらえるもの〉を目標にしています。
この下の窓の〈再生▶︎ボタン〉を押して下のバーに出てくるYouTubeをクリックして〈大画面〉でご覧ください。
作り始めですからまだまだというところもあると思います、長い目でお付き合いください。
YouTubeの中でのコメントの対応は私自身が不可能ですから、そのスペース無しでUPしています。メール等でコメントいただけると幸いです。
よろしければ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。
① たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!
② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります