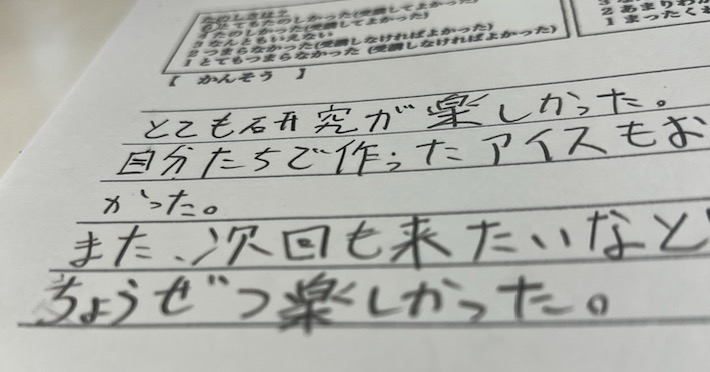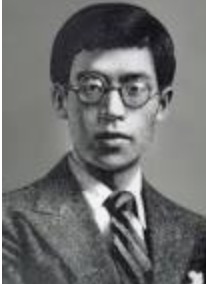今、島言葉を学ぶ意義はなんでしょう?
人々の想いがもっとも刻まれたものは〈ことば〉です。かつての人々が使っていたことばを学ぶことは、かつての琉球で生きた人たちの想いを知ることもできます。それは私たちの人生を今より豊かにすることにつながります。
たのしい教育研究所のこれまでの活動の中で、島言葉は明らかに〈楽しく学ぶことができる〉ことがわかりました。
いろいろなたのしい島言葉教材の開発がすすんでいます、今回は、たのしい夏の講座でもとりあげた「楽しい島言葉・しまくとぅば教材」の動画教材を紹介させていただきます。
テーマは「いろいろな人たちと仲よくなるかっかけになる島言葉」です。どんどん使って、友だちをつくったり、今の友達と、もっと仲よくなってください。
教材プリントはここからダウンロードできるようになっています⇨ https://tanokyo.com/archives/155890
動画はこちらです⬇︎
このQRコードから入ることもできます。

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!
① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎

 〈大人も子どもも仲よくたのしく〉というサブタイトル通り、大人も子どもも一緒にたのしくもりあがっている様子が写真からも伝わると思います。
〈大人も子どもも仲よくたのしく〉というサブタイトル通り、大人も子どもも一緒にたのしくもりあがっている様子が写真からも伝わると思います。