「この冬いちばんの寒波」という怖いキャッチフレーズをここ一二ヶ月で何度耳にしたことか…、幅広のネックウォーマーを耳まであげて、分厚いジャンパーに靴下重ね着で、身近な自然の中を歩きました。
雨模様なので、公園を選びました。
でもそもそも花って見つかるのでしょうか?
⇩
⇩
⇩
やはり目についたのは桜の花です、キレイです。

葉が目立ってきました。
そろそろ「また一年くらいしたら会いましょう」という頃です。
※
こういう低木の植物もありました。
「ゴモジュ」というこもった響きの植物です。
首里城の御門に植えられていたから、そう名付けられたという説があります。そう名付けられたということは、真偽は別にして〈リュウキュウ・沖縄の固有種〉だということでしょう。※確かめてみると琉球固有種でした

スイカズラ(忍冬)ファミリー・科の植物です。
こんなに寒くても、花が咲いています…

ソテツに実がたくさんついています、しみじみ見たのは何十年ぶりのような気がします。
ソテツは雄株・雌株に分かれていて、もちろん雌株にしか実がつきません。

みずみずしい実の時期は過ぎているようです。

これはみずみずしい状態のソテツです。

沖縄県地域環境センターのサイトに感謝して掲載
沖縄を含む南西諸島では、飢饉の時に、ソテツのアク抜きをする工程をとばして食べてしまい、命を落とした人たちも出たといいます。
ただし、ソテツの実はそういう工程を飛ばさなければ、とても美味しいのだといいます。私もぜひ食べてみたいと思っています。ソテツの実の料理を出しているところをご存知の方はお知らせください。
寒くても暖かくても、たのしい花さんぽ、みなさんも出かけてみませんか。
① 毎日1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!





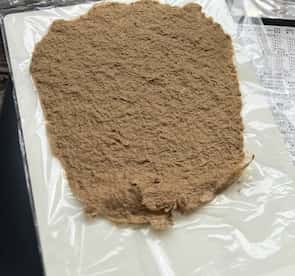
 味のある和紙風の紙がとても簡単に出来上がりました。
味のある和紙風の紙がとても簡単に出来上がりました。







