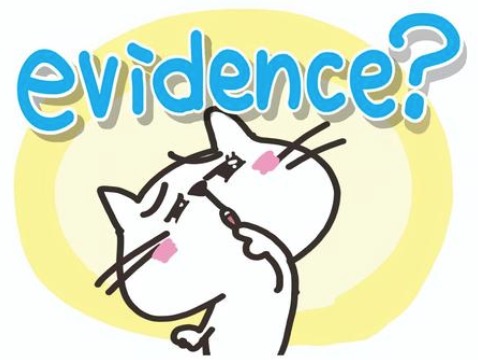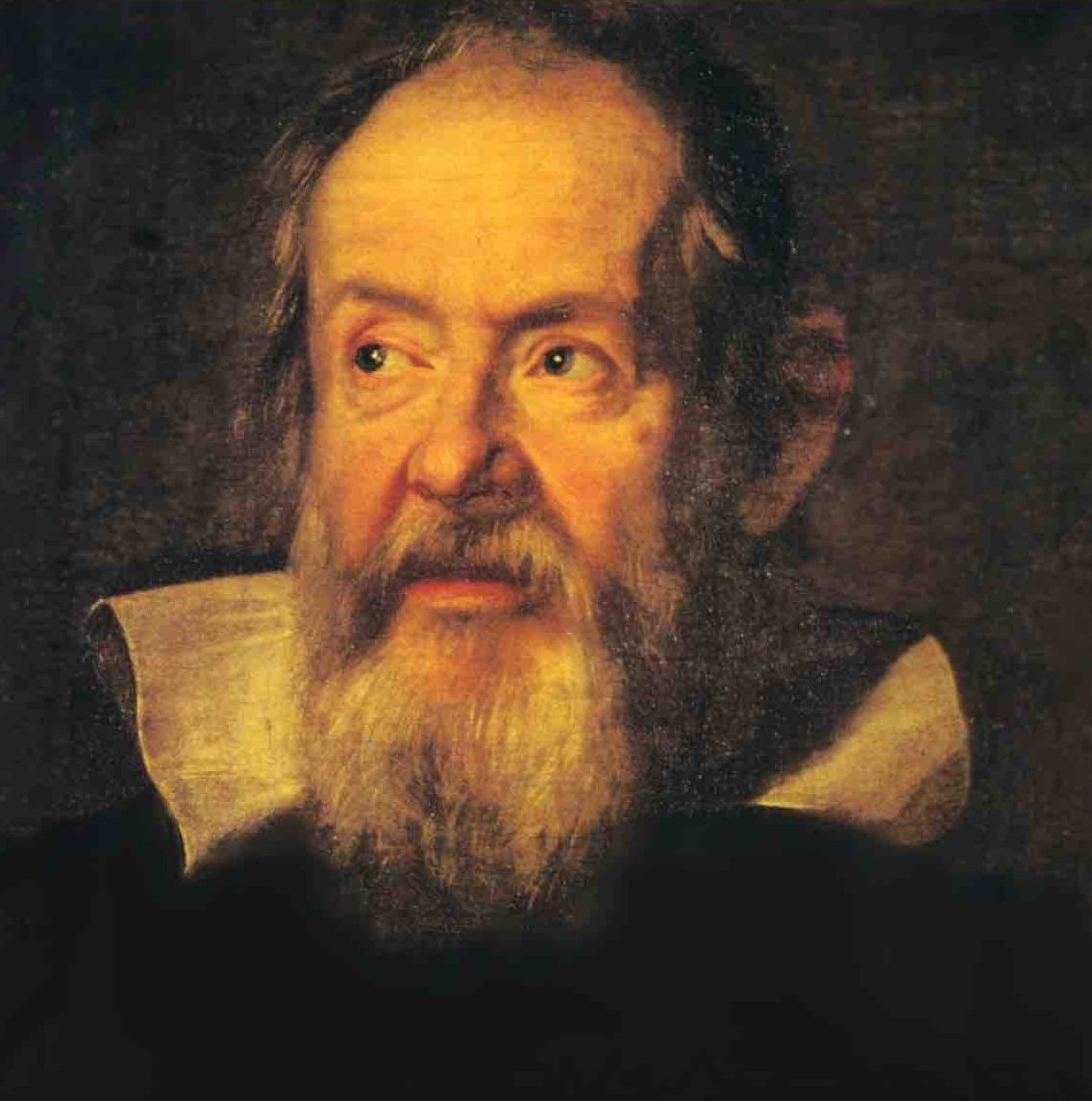前回からの続きです、どうしてダーウィンさんは自分の進化論にとって決定的に重要な実験をしていたメンデルさんの研究に触れていないのか、知らなかったのか、という話です。
最近読んだ本
シッダールタ・ムカジー著『遺伝子(上)』早川書房
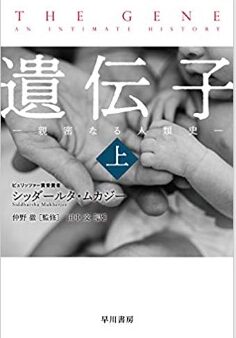
にこうあります。
もしダーウィンが彼の膨大な蔵書を注意深く探したなら、ブルノに住むほとんど無名の植物学者の書いたパッとしない論文への言及に目を止めたかもしれない。
1866年に無名の雑誌に掲載された「植物の交雑実験」という控えめなタイトルのその論文には、ドイツ語がびっしりと並んでいた上にダーウィンがとりわけ嫌っていた〈数表〉がいくつもあった。それでもダーウィンはあと1歩でその論文を読むところだった。
1870年代初めに植物の交雑に関するある本を読みながら、彼は50ページと51ページと53ページと54ページに膨大な書き込みをしていたのだ。しかしなぜか、エンドウの交雑実験に関するブルノで発表された論文について詳細に論じられている〈52ページ〉には何の書き込みもなかった。
もしダーウィンがエンドウの論文を実際に読んだなら、とりわけ家畜、栽培植物の変異を書きながら、パンゲン説を作り上げようとしていた最中に、その論文は、彼に自らの進化論を理解するための決定的な洞察を与えたはずだった。
彼はおそらくそこに含まれた意味に魅了され、その研究者が行った優しさあふれる作業に感銘を受け、その論文の持つ奇妙な説得力に胸を打たれたに違いなかった。
直感的な知性によって進化論を理解するための理論が含まれていることをすぐに見抜いたはずだ。さらにその論文の著者が自分と同じ聖職者であり、自分と同じように神学から生物学へと壮大な旅をして、そしてまた自分と同じように、地図の端から起こした人物だということを知って喜んではずだ。その人物とは聖アウグスト修道会の修道士、グレゴール・ヨハン・メンデルだった。
〈とても広い空白〉の章ラスト部分
生物学の研究者の間では「ダーウィンがメンデルの論文を読んだ証拠は見つかっていない」と言われているのですけど、ムカジーさんはダーウィンの書き込みにまで言及しているので、ほぼ確かなことなのでしょう。とはいえ確かではない可能性もあるので「かなり確かだろう」という段階でとめておいて、今後その書き込みの写真が出てきた時に決定打とした方がよいと思います。
ちなみにこのムカジーさんは一流の研究者であり、ピュリッツァー賞も手にした人物で、ネットなどでみる様な怪しい人物ではありません。
さて、ムカジーの著書によるとダーウィンは数表をとりわけ嫌っていた、とのこと・・・
ダーウィンさんが数表を嫌っていなかったら、その当時の人たちに対して進化論をさらに説得力ある文章で説いていったに違いありません。
あの頃、たのしい教育研究所があったら、ダーウィンさんにたのしく算数・数学の力を高めてあげられたのに・・・
そんなことを考えていました。
① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!