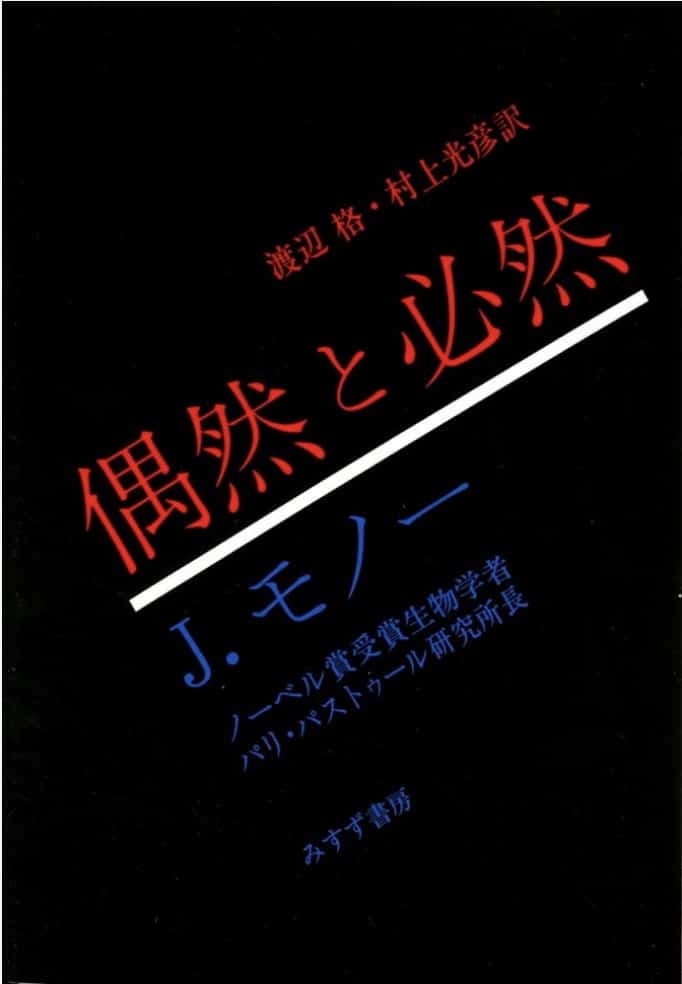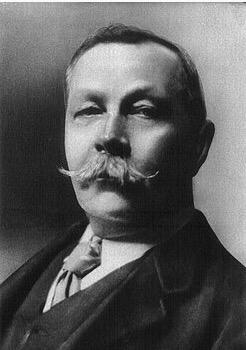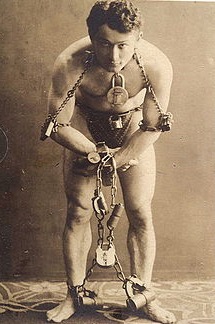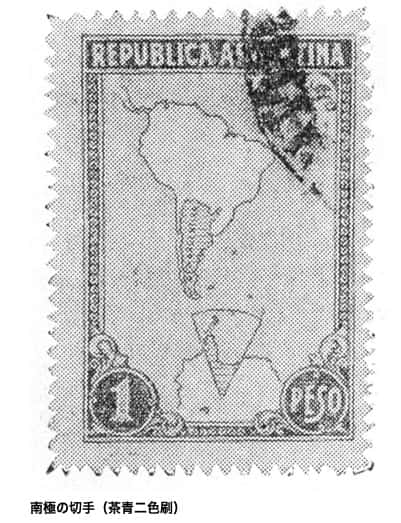日本で本格的なA.I.〈ChatGPT〉が利用できると同時に利用を開始して有料版をかなり使い込んできました、計算すると私のA.I.利用経験は2年以上になります。
最新の〈たのしい教育メールマガジン〉に私の利用方法の一端を紹介したところ、すぐにいろいろな反響が入っています。
いずれ少数での実践講座を開催しようと思っているところです。

〈たのしい教育メールマガジン〉で紹介したものの一部をご覧ください。ChatGPTの基礎編のあと「たとえば教育の分野ではこういう利用ができます」と紹介したはじめの部分です。
⇩⇩〈たのしい教育メールマガジン〉から⇩⇩
・・・
イメージできたでしょうか。
答えを探したいならこれまで通りweb検索を重ねるとよいのです。「世界にはいくつの国がありますか?」というように尋ねていくつかのサイトを読んで確認していくわけです。
自分の問題意識に沿った提案をしてもらうならChatGPTなどの対話型A.I.が適しています。
とはいえChatGPTの答えが正しいと考えてはいけません、提案の一つとして活用するというのが鉄則です。
ということで私が活用している事例をいくつか紹介しましょう。教師としての仕事だけでなく、いろいろな分野に応用できるでしょう。
質問(わたし)
小学校3年生23名のクラスを受け持っています。最近、クラスの人間関係がぎくしゃくしてきました。みんなが仲良くなるような楽しいイベントを企画したいと思います、10くらいあげてくれませんか。⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎☆ここからChatGPT☆⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎
小学校3年生(8~9歳くらい)の子どもたちが「一緒に楽しむ」ことで自然と仲良くなれるようなアイデアを、以下に10個挙げてみます。クラスの雰囲気や予算、場所などに合わせてアレンジしてみてください。
1. 共同アート「みんなで作る壁画」
ポイント
大きな紙(模造紙など)や段ボール、あるいは校舎の壁に貼れる横長の紙を用意して、テーマを決めてみんなで絵を描きます。
テーマ例:クラス全員でつくる「大きな動物園」「未来の街」など。
協力して一つの作品を完成させる達成感が得られます。2. なんでも宝探しゲーム
ポイント
教室や学校の敷地内で簡単な「宝探し」を企画。クラスを複数のグループに分け、謎やヒントを出し合いながら目的のものを探します。
グループごとにヒントを共有しないと見つけられないように仕掛けるなど、自然と話し合いが増える工夫を。
最後に全グループがゴールできるような“協力要素”を入れると、仲間意識が育ちます。3. かんたん「ミニ運動会」
ポイント
大がかりな運動会ではなく、教室や校庭の一部でできるミニゲームを複数用意します。
例:「玉入れ」「イス取りゲーム」「輪投げ」「じゃんけん列車」「綱引き」など、短時間で盛り上がる種目をいくつか組み合わせる。
チーム対抗にするより、最後は「全員でやりきろう!」という雰囲気にすると協力ムードが高まります。4. 「他己紹介」ゲーム
ポイント
ペアになってお互いのいいところや好きなことなどを聞き合い、「相手がどんな人か」をクラスの前で紹介する。
短い時間でも、相手の情報を聞いてまとめることで相互理解が深まります。
発表時には「◯◯さんのこんないいところを発見しました!」と伝え合う形式にするとクラスの雰囲気が温かくなります。5. 交換お手紙リレー
ポイント
自分の良いところや好きなものを書いた自己紹介カードと、相手に伝えたいメッセージ(「ありがとう」「ここがすごい」など)を書いたカードの2種類を作ります。
お手紙をクラス内でリレー式に回す(1日1人ずつ違う人に渡していくなど)と、しばらくの間クラスに手紙交換のワクワクが続きます。
互いの長所に気づきやすくなり、クラスメイトを見直すきっかけに。6. みんなで料理体験(簡易版)
ポイント
火や包丁を扱うのが難しければ、サンドイッチ作りやトッピングピザなど簡単なものをグループで協力して作る。
共同作業で「何をどう分担するか」を話し合う経験ができます。
最後にみんなで食べると自然と笑顔が増えます。7. 「お題連想リレー」ゲーム
ポイント
円になって座り、教師が最初に「〇〇といえば?」などのお題を出す。
1人目の子がイメージするものを答え、次の子はその答えから連想したものを答えていくリレー式のゲーム。
例えば、お題「夏」を出して、「スイカ」→「赤色」→「りんご」→「果物」→…と続いていく。
連想を通じて「こんな発想もあるんだ」と驚いたり、「自分と似てる!」と共通点を見つけたりできます。8. みんなで「お笑いスピーチ大会」
ポイント
テーマを「ちょっと笑える自分の失敗談」「小さなハッピーエピソード」などに決めて、短いスピーチをしてもらう。
「司会者(MC)役」を交代制で務めさせるのも楽しい。
発表する子をみんなで応援し合うことで、クラスの一体感が高まります。
あまり恥ずかしくならないように、柔らかい雰囲気を教師がリードすると◎。9. クラス全員「コラボダンス」または「リズムアンサンブル」
ポイント
簡単な振り付けやリズムパターンを考えて、グループごとに自分たちなりにアレンジして発表。
全チームがバラバラの振り付けなのに、一緒に音楽を流すと自然につながって1曲になったりする。
仕上げに全員で同じ部分を踊る振りを作っておくと、みんながまとまる瞬間が生まれる。10. 教室キャンプごっこ
ポイント
教室や体育館の一角に「模擬テント」や「みんなで作る段ボールハウス」など簡単な基地を作り、レクリエーションを実施。
たとえば「キャンプに行くなら何を準備する?」とグループでアイテムを書き出したり、「キャンプファイヤーの代わりに小さく囲んでお話をする」など。
非日常感があり、普段とは違う環境で話したり遊んだりすることで、自然に交流が深まります。
まとめ
工夫のポイント
「ただの対決ゲーム」よりも、協力しないとゴールできない仕掛けや、お互いの良いところを再発見できる要素を入れると、人間関係の改善につながりやすいです。
イベントをきっかけに、その後の日常活動にも「一緒にやるのが楽しい」「相手を認め合う」という空気をつなげる工夫をすると、クラス全体の雰囲気がより良く保たれます。
これらのアイデアをベースに、子どもたちの好みに合った形でアレンジしてみてください。楽しいイベントが成功して、クラスのみんながもっと仲良くなりますように!
⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎☆ChatGPTここまで☆⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎
さてChatGPTの利用はここからが本番です。
比較的大きなフレームで投げかけてから、より具体的なことを聞いていくことがおすすめです。
質問(わたし)
提案してくれた「10. 教室キャンプごっこ」をやってみようと思います、やんちゃなこもたくさんいるので、安全面にも気をつけなくてはいけません。子どもたちに命令的にならずに安全な活動を呼びかける具体的な声掛けの仕方を考えてください。
⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎☆ここからChatGPT☆⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎
「教室キャンプごっこ」を安全かつ楽しく進めるためには、子どもたち自身が「自分たちで安全を作る」という気持ちをもてるような声かけが大切です。上から指示をするのではなく、子どもたちと同じ目線で「どうやったらみんなが安心して楽しめるか」を共に考える姿勢で声をかけると良いでしょう。以下に具体的な例を挙げます。
1. 活動前の「ワクワク+安心づくり」声かけ
「みんなで安全係になろう!」
「今日は教室キャンプごっこでいろんなことをやるけど、みんな一人ひとりが『安全係』になってくれると嬉しいな。自分もお友だちもケガしないように、どうしたらいいか一緒に考えてみよう!」
自分が“係”になる感覚をもつことで、主体的に安全を意識しやすくなります。
「どんなことに気をつければ、明日も元気にあそべるかな?」
「楽しく遊ぶためには『ケガをしない』ことが大事だよね。明日も元気に学校に来られるように、どんなところに気をつければいいと思う?」
子どもたちからアイデアを引き出し、「そうだね!そうすると安全だね!」と肯定的に拾うようにします。2. 道具の扱いについての声かけ
「段ボール(または工作道具)と仲良くなるには?」
「今日使う段ボール(工作道具)とうまく仲良くするためには、どんな持ち方・扱い方がいいかな?」
子どもの意見に「そうだね、○○くん(さん)の言う通りだね!」と返しながら、教師の意図する安全な持ち方・使い方につなげます。
「みんなが安心できるルールを一緒に決めよう」
「ハサミやカッターを使うとき、どう持ったら安心かな?どこで使うといい?」
具体的に「このテーブルの上で座って使おう」とか「走らないで座って切ろう」などを子どもたちの声からルール化するイメージで進めましょう。3. 活動中のトラブル回避に向けた声かけ
「お互いに合図を出し合おう」
「もしどこかでぶつかりそうになったら、『○○するねー!』って大きめの声で言って教えてあげよう。そうするとみんなも気づけるよね。」
指示というよりは「合図を出し合うと、お友だち同士で守り合えるよ」という協力姿勢を強調。
「こんなとき、どう声をかけたらいいかな?」
「もし荷物を運んでる途中に、前のお友だちが急に止まったら?危なそうだったら、どんな言い方をすると優しく伝えられるかな?」
具体的なシーンを想定したロールプレイ的な問いかけで、子ども自身に考えさせる。4. 教師が取りまとめるときの声かけ
「教えてくれてありがとう!」と感謝を伝える
「今、『そこは危ないよ』って教えてくれたね。ありがとう!みんなで安全に楽しむために、すごく助かるよ。」
他の子が安全に関する注意をしてくれたら、それを肯定・評価してあげます。
「みんなのアイデアで安全になってるね!」
「すごいね、みんなが気づいたことを実践してくれるから、安全に遊べてるよ。おかげで先生も安心だし、楽しいよ!」
常に子どもたちの取り組みをポジティブな言葉でフィードバック。5. 教室キャンプの終わりの振り返りでの声かけ
「安全に過ごせるように工夫してくれたのは誰かな?」
子どもたちに「誰が、どんな工夫をしてくれたか」を挙げてもらい、みんなの前で称える。
「○○ちゃんが『ここ危ないよ』って教えてくれた」「○○くんが『大きな声で合図しよう』って言ってくれた」など、具体例で褒める。
「また一緒に安全な遊びを考えてくれると嬉しい」
「今回みんなのおかげで安全に、楽しくできたね。次の行事でも、みんなの工夫を借りたいな。」
次回以降の活動へ繋げることで、安全意識が長続きしやすくなります。
まとめ
命令口調ではなく、「どうすればいいと思う?」と子どもの意見を引き出す形にすると、主体的に安全を守ろうとする意識が育ちます。
実際に子どもが正解に近い答えを出してくれたら、**「いいね、それにしよう!」「その考えは安全だし、すごく助かるよ」**と肯定し、クラスでのルールとして採用するのがおすすめです。
多少ふざけたりやんちゃをする子も、「自分の意見が採用された」という体験があると、ポジティブに参加しやすくなります。
こまめに**「ありがとう」「助かったよ」**など感謝や承認の言葉を伝えることで、子どもたち同士も自然と「大丈夫?」「気をつけようね」と声を掛け合いやすくなります。
ぜひ、キャンプごっこを通じて、子どもたち自身が互いの安全を気遣う体験をたくさん積んでみてください。楽しい時間になりますように!⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎☆ChatGPTここまで☆⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎
つづけますよ、自分のイメージが具体的に固まるまでChatGPTはいくらでもつきあってくれます。
質問(わたし)
「10. 教室キャンプごっこ」をやってみようと思っているのですけど、教頭先生に「教科書にないことはやってはいけません」と言われていまいそうです。
教科書に位置付けるアイディアをいくつか出してください。
⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎☆ここからChatGPT☆⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎
「教室キャンプごっこ」を単なる“遊び”として捉えるのではなく、教科書や学習指導要領にある内容と結びつけることで、正規の学習活動として位置づけるアイデアをいくつかご紹介します。 実際には、各学校で使用している教科書や教育課程の編成などに合わせて微調整が必要ですが、あくまで例としてご活用ください。
1. 「国語」:読んで・書いて・話し合う力の育成
1-1. キャンプの準備に関する「説明文」づくり
教科書との関連:3年生国語の学習では、「自分の考えや手順を整理して相手に伝える」学習内容があります。
具体案:
キャンプごっこで準備するもの(テントがわりの段ボール、レクリエーション道具など)や手順を、グループごとに「材料・道具リスト」「手順書」としてまとめさせる。
教科書の説明文(手順の書き方)を参考に、「誰が読んでもわかるように書くコツ」を考えさせる。
それをポスターや小冊子にまとめ、他クラスに「キャンプごっこ」の魅力と準備方法を発信。
1-2. キャンプごっこ後の「振り返り作文」
教科書との関連:学年が上がるにつれ「体験を文章にまとめる」学習も行います。
具体案:
キャンプごっこで感じたことや学んだことを短い作文や新聞形式の記事にまとめる。
国語で学習した「出来事→詳しい説明→感想・まとめ」の構成を意識させる。
2. 「社会」または「生活科(総合的な学習)」:身近な生活と地域・安全
2-1. 防災(避難所体験)的な視点
教科書との関連:3年生の社会科や生活科で、防災や自分たちの暮らし、地域との関わりを学ぶ単元があることが多いです。
具体案:
「キャンプ」という視点を「災害時の避難場所や簡易の生活空間づくり」に変換する。
段ボールやテントを使って「避難所ではどんな工夫が必要?」と考えさせる。
教科書にある「避難訓練」や「非常時のくらし」に関連づけ、単なる遊びでなく「実際に役立つ学習」として位置づける。
2-2. 地域の自然や資源に関する学習
教科書との関連:3年生の社会科で「地域の産業や自然」について取り扱う場合あり。
具体案:
「もし〇〇市(地域)で野外活動をするなら、何が必要か?」と考えさせる。
地域にある川・森林・公園などを調べ、教室キャンプに“仮想で”取り入れる。
「自分たちの地域の自然を生かすならどんなキャンプができるか」を計画し、社会科の学習内容として扱う。
3. 「理科」:自然観察・光と影・気象など
3-1. 室内でできる“光と影”の実験コーナー
教科書との関連:3年生理科では「光の性質」や「植物の生長」「気象の観測」などが取り上げられます。
具体案:
「キャンプでは太陽の位置や時間の経過を感じることが多い」という発想から、室内でも光源を使って「影の長さ」や「日の光」の働きを実験的に確かめるコーナーをつくる。
教室をテント風に薄暗くしておき、懐中電灯やランタンの光で「影の向きが変わるのはどうして?」などの簡単な探究をする。
「キャンプ=屋外」というリアリティと理科の単元を掛け合わせる形。
3-2. 植物の成長環境シミュレーション
教科書との関連:3年理科で「ホウセンカ」「ヒマワリ」など植物の育ち方を学習。
具体案:
キャンプごっこ内で「小さな観察コーナー」を作り、植物の苗を“キャンプ場”に持ち込む設定。
「外と中では温度が違う。植物の成長にどんな影響が?」など、テントと室内との気温差を比べてみる。
これを理科の観察日記やグラフづくりに活かす。
4. 「家庭科」(3~4年生以降の内容が該当する学校も)
4-1. 簡単な「調理・配膳」の体験
教科書との関連:家庭科(小学校高学年で本格化しますが、3・4年生でも地域によっては体験的に扱う)。
具体案:
キャンプごっこで「簡単クッキング」コーナーを設定し、おにぎりやサンドイッチなど火を使わない料理をグループで作る。
「食材の下準備」「衛生管理」「道具の使い方」など教科書で学ぶ基礎的な部分を確認する。
学校の栄養教諭や給食センターの話と絡めて、「バランスのよい食事って何?」なども学習。
5. 「道徳」・「特別活動」:仲間づくり、助け合い
5-1. グループ協力と役割分担
教科書との関連:道徳の単元で「友達と協力する意義」「助け合うことの大切さ」を学ぶことが多い。
具体案:
キャンプごっこで「みんなの役割」を決める(リーダー、道具係、発表係など)。
道徳の時間に「役割分担で生まれる助け合い」「自分のできることを生かしてみんなに貢献することの喜び」について考える。
実際に教室キャンプで役割を実践し、後日道徳の時間に振り返りとして「自分は何をがんばれたか? 仲間にどんなところを助けてもらったか?」を書き出す。
5-2. 「他人の立場に立つ」ワーク
教科書との関連:道徳では「思いやり」や「共感」を学ぶ。
具体案:
キャンプごっこで、グループ内で協力して1つの遊び(工作・ゲーム)を作り上げる。
「みんなが楽しめるためには何が必要か?」を考えさせる過程で、道徳で学習する“相手への配慮”を実践。
後日、「○○くんが嫌がらないように工夫したこと」「△△さんの得意なことを活かすために工夫したこと」をまとめる。
6. 「図工」:空間づくり・工作
6-1. テントや飾りを自分たちでデザイン
教科書との関連:「空間や形を工夫して楽しく制作する」単元があります。
具体案:
大きな段ボールや布を使って、オリジナルの“テント風工作”を班ごとに制作。
「どうすれば丈夫になるか」「誰が入っても壊れにくい形は?」など、形や構造を考える。
仕上げにポスターカラーや紙テープなどで装飾して、キャンプの雰囲気を盛り上げる。
これを「作品展示」と位置づけ、図工評価の対象にもできる。
6-2. キャンプアイテムをみんなでデザイン
例:紙ランタン、紙皿で作る食器デザイン、オリジナルの旗(キャンプ場の看板)など。
作って終わりではなく、実際にキャンプごっこで使ってみて「使い勝手」を振り返り、創意工夫の良し悪しを評価する。
7. 「総合的な学習の時間」:プロジェクト学習として
教科書に直接の単元がなくても、「総合」の時間を活用すると位置づけやすい。
キャンプごっこを「プロジェクト」として計画・準備・実施・振り返りまで一連の流れを子どもたちと一緒に行う。
学習指導要領のキーワード(探究的な学び、問題解決学習、協働学習)に関連づけ、「教室キャンプ企画」は立派な総合的な学習の題材になる。
8. 「算数」や「音楽」と組み合わせる発想(発展編)
8-1. 算数:計測や見積もりで応用
テント(段ボール)の大きさや人数分の敷きマット、キャンプ場のレイアウト作りに「面積」「長さ」を計算。
予算を仮定して、「このくらいのお菓子代なら○○円」など金額の計算をする。
8-2. 音楽:みんなで「キャンプソング」を考える
教科書との関連:3年生で習う簡単なリズムや合奏に、キャンプをイメージした歌詞をのせて楽しむ。
キャンプ場(教室内)で簡単な合唱やリコーダー演奏の発表会をすると、イベント性が増す。まとめと提案
「教室キャンプごっこ」を教科書や学習指導要領の範囲内で正式に位置付けるには、上記のように各教科の学習目標や内容と関連づけるのがポイントです。
特に国語、道徳、図工、総合的な学習の時間などは「体験」「表現」「協働学習」を扱いやすいため、単なるレクリエーションではなく“学習活動”としての根拠を示しやすいです。
教頭先生など管理職への説明時には、
「〇〇教科の教科書・指導要領のこういう単元と結びつけていて、学習目標はこう設定しています」
「体験後には○○という形で振り返りレポート/発表をすることで、教科の狙いを達成します」 と具体的に示すと納得が得られやすいでしょう。
このように教科書やカリキュラムの一部としてしっかり計画を立てれば、「教室キャンプごっこ」も教育的価値の高い活動として認めてもらいやすくなります。ぜひご参考ください。どうでしょうか、読んでいただけたら、「新しい提案をしてもらう」というイメージも伝わったと思います。
⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎☆ChatGPTここまで☆⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎
いかがでしょうか。
まだまだ楽しい使いかたがたっぷりです。
読んだだけではなかなかその魅力を感じることができないこともあるでしょう。
特別WSを希望の方はお問い合わせください、カウンセリング費用と同額程度で引き受けています。とはいえ、その額は〈たのしい教育メールマガジン〉一年分と同じくらいの額12,000円くらいですから、通信教育としての〈たのしい教育メールマガジン〉の価値は高いと思います、ご希望の方はまずメルマガ購読をおすすめします。
① 毎日1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!