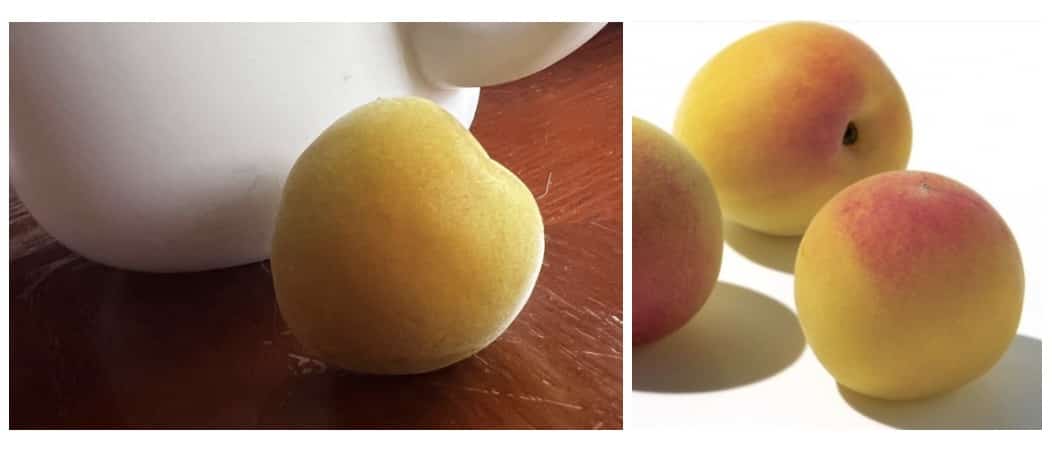春になって〈第一たの研〉の庭の手入れをしていて驚いてしまいました。太陽の力の大きさ、それを受けて生きる命たちの話です。
ほぼ一年くらい前のこと、桜の苗木が手に入ったので、もともとあった桜と桜の間に植えることにしました。その後、気づかないうちに2本の桜が枝をどんどん伸ばし葉を茂らせて、小さな苗を覆い隠してしまい、忙しくしている間にその存在を忘れてしまいました。
庭の手入れをしていると桜の葉の多さが気になって、ノコで枝を落としていました。
するとビックリ、大きな桜の木と木の間から一年前に植えた小さな桜を発見。
高さ50cmくらい、幹の太さも1cmくらいでまだまだ小さいままです。
植えた時よりほんの少しだけ成長したくらいです。
一年経ったのにこんなに小さい・・・

ごめんねごめんねと、隣の桜たちの枝葉を払って、近くのバラの枝葉も束ねて太陽の光が当たるようにしました。

電柱のすぐ左に50cmくらいの小さな木が見えると思います、それが一年前に植えた桜です。
左側の桜は三年くらい前に小さな苗をもらって植えたものです。
日当たりが良ければ、それくらいでしっかり成長します。
小さな桜には太陽の光が届かず、わずかな木漏れ日で光合成をして、なんとかがんばってきたのでしょう。
これ以上大きく育つための太陽光を受け取ることができはないので、これくらいの大きさのまま生命を維持してきたわけです。
よくがんばった!

忘れてしまってごめん。
一年順調に太陽の光を受けて、水と土のミネラルを吸っていたら、両側の桜たちをおしのけるように育っていたと思います。
これからたっぷり世話をしてあげようと思います。
それにしても〈太陽の光〉というのはすごいものだととても感心してしまいました。
前に書いた「太陽光発電」で電気を作り出す力にも感動したのだけど、地球上のたくさん生命は、太陽の力のおかげなのだということを実感したできごとでした。
春です、たくさんの植物たちを育てようと思います。
みなさんも植物たちの世話をたのしんでみませんか。
① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!