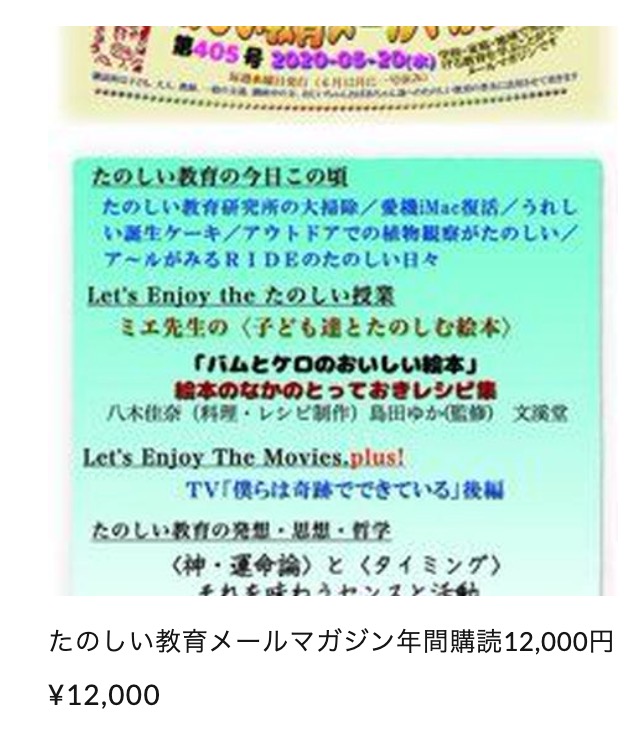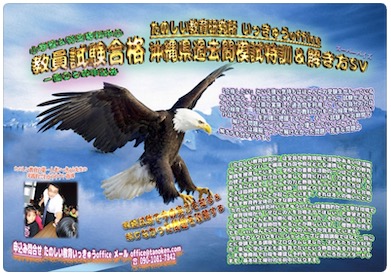以前予告したカウンセリング講座の開催が決まりました、3回コースです。
私のスケジュール調整がうまくいかず、一回ずつ曜日が異なってしまいました、すみません。
「入門講座」とはいえ、PEALカウンセリングは明確な流れを提示しているので、3回コースでカウンセリングの進め方をしっかり掴んでもらえると思います。
「カウンセラー資格コース」は年末の開催を考えているのですけど、合格は簡単ではありません。カウンセラー資格を目指している方は、ぜひこの基礎コースから受講してください。
これまで育てたカウンセラーの皆さんにも伝えてきたのですけど、カウンセリングも〈スポーツと同じ〉です、形がつかめたら、それに何度もトライしていくうちに確実にうまくなっていきます。
「よく友人たちから相談をうける」という方は、きっとカウンセラーとしての力が高いのでしょう。そういう方も一度しっかり学んでみることをおすすめします。
またカウンセリングの勉強なんてしたことない、という方も、その基礎を固めるのに最適です。
他流派のカウンセリングを学んだ来た方も『たのしい教育』に興味関心があれば受講可能です。

以下、事務局からの案内を添付します。
PEAL教育カウンセリング入門講座(3回コース)受講者募集!
子どもの悩みと向き合いたい、友人・知人から相談が来た時にその相談にのってあげたい。そういう時、相手の悩みや課題に向き合おうとしても、ふと気づくと「アドバイス」になっていたり「自分が応援するからね」という励ましだったり「他にも苦しんでいる人たちはたくさんいるんだよ」という現状許容だったりすることがあります。
カウンセリングはそうではなく、相手の悩み・課題を解決行動に結びつけるとても強力な手法です。
教育関係者はこれまでいくつものカウンセリング研修を受けています。その中で「カウンセリングは〈相手をそのまま受容することが大切だ〉〈共感が大切だ〉」という知識をもっている方もたくさんいます。
しかしカウンセリングは学んだけれど「相手と向き合った時はじめに何と声をかけたら良いのか」「単に相手の語ることを聞き続けていてよいのか」「質問されたどう答えたらよいのか」「そもそも一緒に乗りこんだこの舟をどこに向かわせたらよいのか」など《具体的な流れがわかりません》という人たちがとてもたくさんいるのが実情です。
カウンセリングを学んできた人たちの力が不足していたのでしょうか?
いいえ、そのカウンセリングがわかりやすく構造化されていないのです。また、あえて伝わらない様にしていることがあるのかもしれませんし、長い修行を積まなければ構造が体感できない様になっているかもしれません。
PEALカウンセリングは《どういう流れでカウンセリングをすすめていけばよいのか》《どう声かけをしていくか》を具体的に学んでいくことができます。
もちろん一度受講すれば上手くなるというわけではありません、そこはスポーツと一緒です。テニスの試合の流れがわかって試合に出ることができる、そして練習を積んでいくうちに確実に上達していきます。そこに名人芸的なものも特殊な技能も必要ありません。
今回、三回コースで理論と実践を学んでいただける講座の開催が決まりました。
実践重視のコースなので少数制です、興味のある方はお申し込みください。
自分の悩みや課題を客観的に整理したい方、教育関係者ではない、我が子の悩みに向きあいたいという方も〈たのしい教育〉に興味関心があれば受講可能です。
実践重視のコースなので少数制です、興味のある方はお申し込みください。
日時:2023年 ①7月23日(日) 09:30~12:30
②7月29日(土) 09:30~12:30
③8月02日(水) 15:30~18:30
※なお、何らかの事情で欠席せざるを得ない場合は1回の補講が可能です
会場:たのしい教育研究所(沖縄市研究所)
対象:たのしい教育に興味関心のある方
参加費:一般 3万9000円
これまでRIDEのカウンセリング関係の講座を受講したことのある方 3万4000円
メルマガ会員 2万9000円
持ち物:筆記用具、飲み物
感染症対策 ※検温、体調確認、殺菌消毒に加え、大型ファン複数台での換気他、いろいろな対策をして実施します
※
指導 いっきゅう先生
教師を早期退職し「NPOたのしい教育研究所」を設立国内だけでなく海外でも授業の腕を振るう。
現役の教師をしていた30年前、学校現場の数々の問題を目の当たりにし〈たのしい教育〉だけでなく〈カウンセリング〉的な力が必要だと悟り、大阪在住のアドラーカウンセリング名人〈野田俊作〉のもとに何度も通い、直接指導を受ける。
実力が認められ沖縄県で最も早くアドラー心理学カウンセラー免許を野田俊作から直接授与される。
他流派のカウンセラー免許も取得し既に数千件のカウンセリングを実施。
その後、教育と親和性が高く仮説実験的な手法を取り入れたPEALカウンセリングを開発し弟子を育てる。
やさしくユーモアのある人柄でわかりやすく実践的な指導で評価が高い。
※
申込み問合せ
たのしい教育いっきゅうoffice
メール office@tanoken.com ☎ 090-1081-7842
① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!