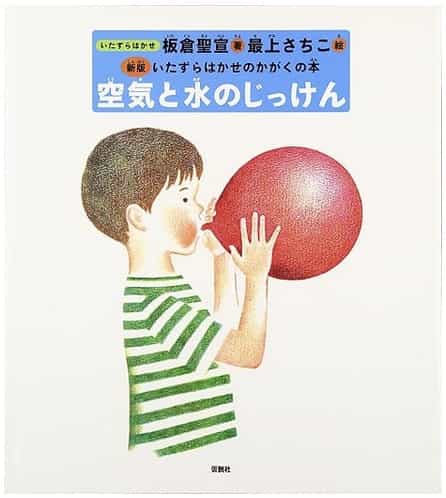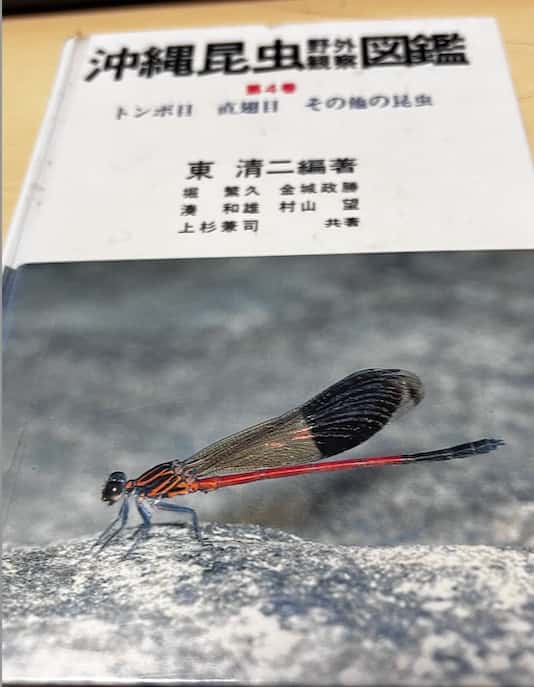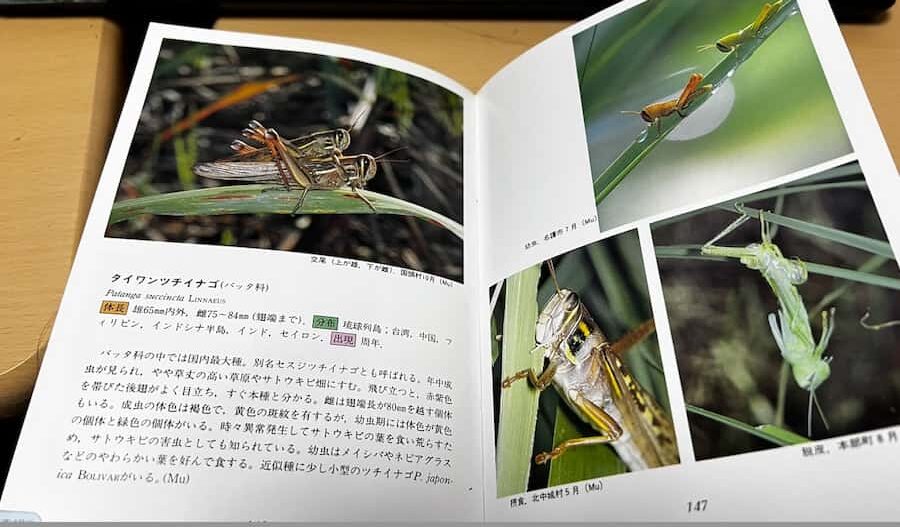週一回配信している「たのしい教育メールマガジン」の読者はおかげさまでいろいろな県にひろがっています。地味なのに人気があるのが『たのしい教育の発想法』です。紹介したいことに溢れていて、ボリュームの関係でメルマガからはぶいた内容がとてもたくさんあります。
ここで少し紹介させていただきます。
1989年1月14日
仮説実験授業の運営法に関して
「そんなの常識じゃないか」「非常識な人もいたもんだ」というような会話を廃止するための研究会
という不思議なタイトルの講座が開催されました。仮説実験授業研究会の初期には、こんな個性的な研究会がいろいろ開かれていました。
その中で語られた板倉聖宣先生(仮説実験授業研究会初代代表/元文科省教育研究所室長/元日本科学学会会長/たのしい教育研究所 初期から支援者)の話です。私いっきゅうの再校正・編集でお届けします。
※
中学校教師Oさん
授業書の問題を「読みたい人?」というと、中学生はほとんど手を挙げてくれません。
板倉聖宣
「読みたい人」という言い方をするの?
私は「読んでくれる人?」だと思うんだけど。「読みたい人」とは全然違う。
相当積極的な子じゃなかったら「読みたい!」なんて言わないもの。
Oさん順番で読ませていくのもあまりよくないと思う。読むのがすごくしんどいという子もいるので・・・
板倉聖宣学校の先生でも読むのをすごくイヤがる人がいるくらいだからね…
読むという行為は、慣れた人にはストレスのないものでも、子どもたちの多くは練習過程です。国語の本など、習ったことのない漢字や語句が出てくるのが普通ですから。
たのしい教育の中でも、そのあたりのことをしっかり考えておく必要があります。
板倉聖宣は教師ではありません、でもこういう感覚は研ぎ澄まされていて、教師一年目からとてもたくさんのことを教えてもらいました。もしかするとそれは「子どもの感覚を忘れていない」ということではないかと考えています。
⇩☆⭐︎⭐︎☆⭐︎ たのしい本の紹介・たのしいブックレビュー ⭐︎☆⭐︎⭐︎☆ ⇩
たのしい教育の発想に関してはまずこの本をおすすめします、『たのしい授業の思想』です。短いまとまりになっているので、どの項から読んでもOKです。
おっとAmazonで300円くらいで出ています、送料込みでも500円台です。早い者勝ちですね(2024-07-13 11:44現在)。
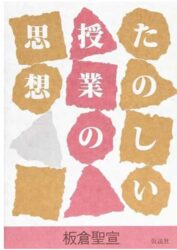 ⇧☆⭐︎⭐︎☆⭐︎ たのしい本の紹介・たのしいブックレビュー ⭐︎☆⭐︎⭐︎☆ ⇧
⇧☆⭐︎⭐︎☆⭐︎ たのしい本の紹介・たのしいブックレビュー ⭐︎☆⭐︎⭐︎☆ ⇧
① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!