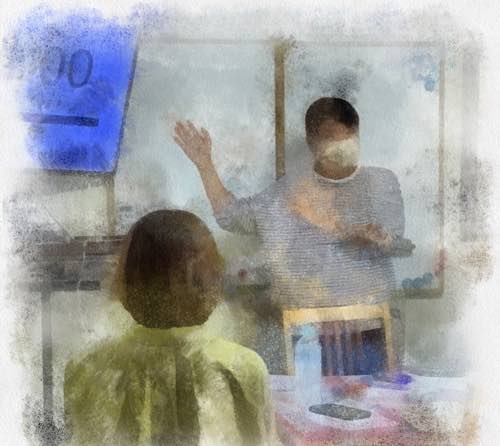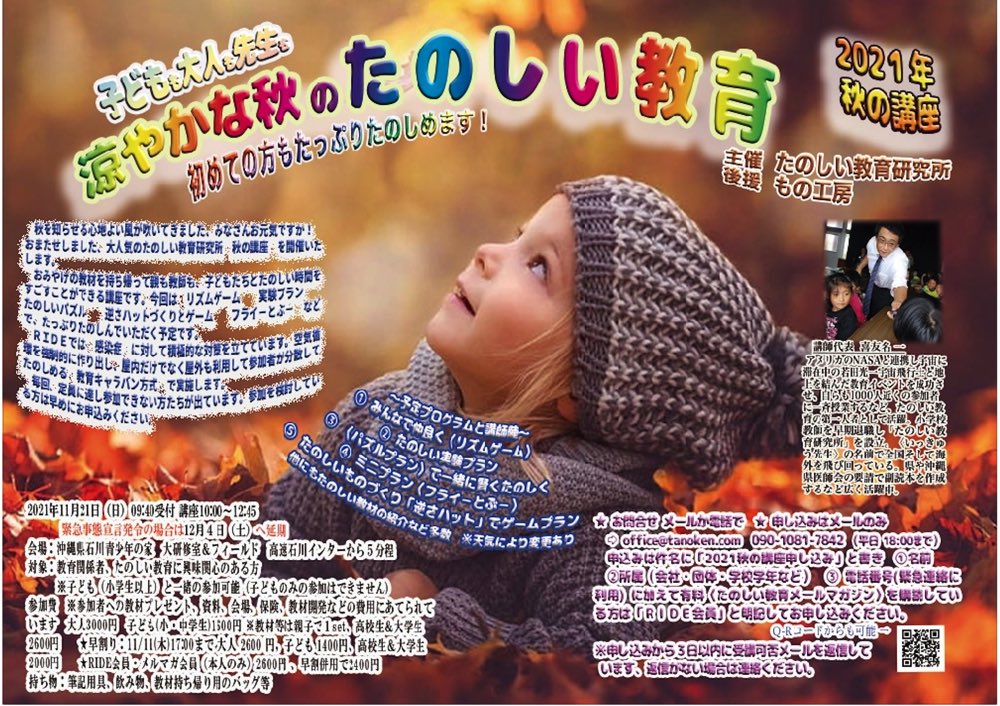前の記事で、雨の日、傘を指してアウトドアをたのしんでいる様子をお届けしました、その続きです。
多くの人が意外に思うかもしれません、雨の日の植物たちは美しく見えるんです。
あまりに暗いと困るのですけど、それなりに光があれば大丈夫。
植物たちにとってまさに〈恵みの雨〉だからだと思います。
これは二日前に紹介した〈イジュの花〉、正式には〈ヒメツバキ〉といいます、私にはとてもキレイに見えるのですけど、みなさんの目にはどういう様に映るのでしょう。

これは前に紹介した〈クチナシの花〉です。沖縄本島の中頃にある〈たの研〉の近くでは、殆どのクチナシの木は花が散っていたのですけど、少しは目にすることができます。
晴れていた時よりもキレイに見えました

野生の〈ランタナ〉も見つけました。

これは〈ノボタン〉ですね、これから花をつけてくれると思います。

これは〈コンロンカ〉、葉が花びらの様に見えるおもしろい植物です。
特徴的な〈白い葉〉が輝きを見せてくれます。

花はその白い葉の中にあって、やわらかな黄色です。

これはよくみる月桃と、花のつき方が少し違って見えます。同じジンジャー(ショウガ科)の別な種類かもしれません。これからもみていきたいと思います。

どうでしょうか。
花は太陽の光輝く時もきれいです、ほとんどの人たちは晴れの時に花を愛でるでしょう。
けれど雨の日も花たちはとても輝いて見えるんですよ。
嘘だと思ったら試してみませんか。
たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!