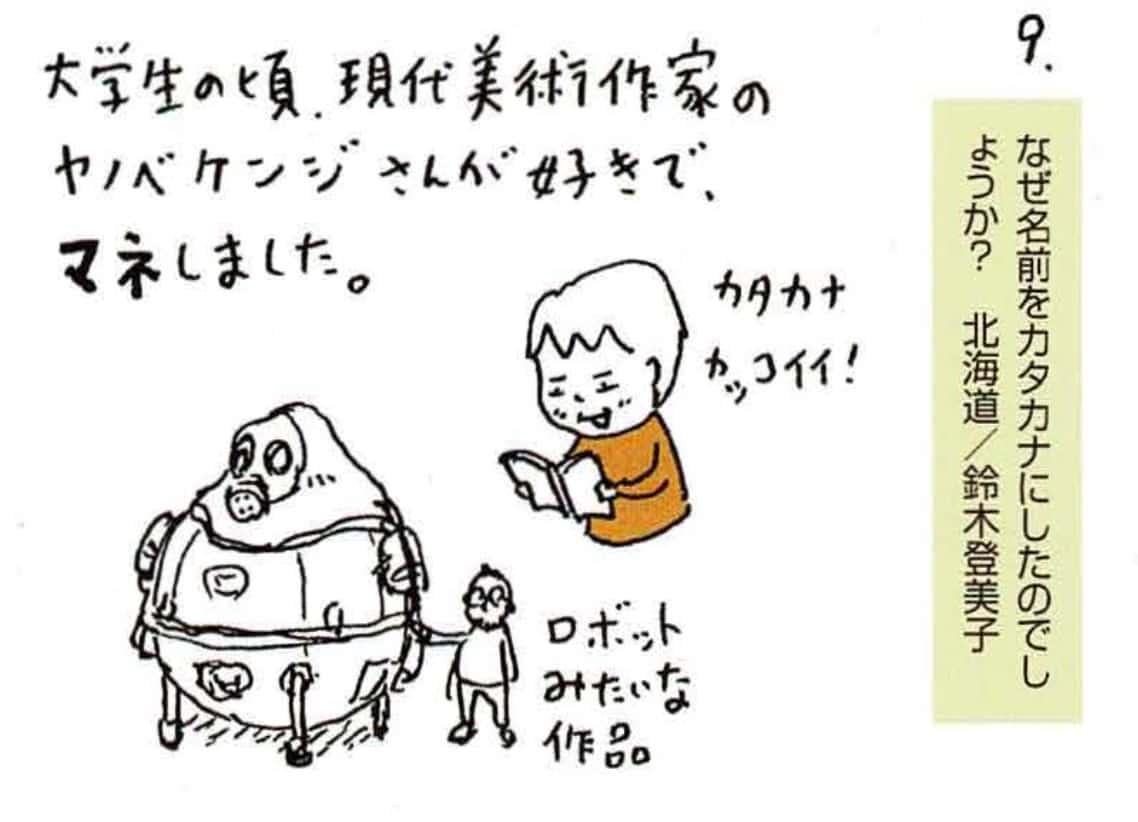寒さも過ぎて、外を歩くと汗ばむくらいの日々です。1時間くらい時間がみつかったので、車を走らせて野山さんぽしてきました。
木の実には自然に目がいくものです、私たちのDNAにそのように刻みつけられているのでしょう。
上からたれさがる黄色い木の実が目に入りました。

まだ熟していない実もたくさんあります。
これはなんだろう?
バナナではない。

カニステルという果物があって、それに似ているんだけどなぁ、散歩で初めて出逢ったので、同定してよいのか不安ありです。
こんな時にまず調べる必要があるのが「毒がある植物」なのかどうかです。
不用意に実を採って、毒性の液がついてしまうと困ります。
いくら自然が大好きであっても、こういうところはしっかり子どもたちにも伝えておく必要があるでしょう。
沖縄の樹木で強い毒があることで有名なのは〈キョウチクトウ〉と〈メフクラギ/オキナワキョウチクトウ〉です。
これはキョウチクトウ、公園などにも普通に見かけます。
キレイな花を咲かせる木です、でも強い毒で有名です。

調べてみたら、こんな細い実ができて

中から綿毛が出て飛んでいくんですね、知らなかったな。

これがメフクラギ・オキナワキョウチクトウです。子どもの頃、複数の大人たちから「この樹液で本当に失明するぞ」と教えられました。美味しそうだけど、有毒です。〈オキナワキョウチクトウ〉といっても〈キョウチクトウファミリー(科)〉ではありません、それは実を見てもわかると思います。

私の長いアウトドア生活で安全に過ごしてきた知識・感覚から「見つけたきのみがこの二つでなければ大丈夫だ」と判断して、実をもぎ取って、匂いをしてみることにしました。
※
次に進む前に、沖縄の樹木で毒を心配しなくてはいけないものを整理しておきましょう。
A.I.のディープリサーチがすぐれものです、まとめてもらいました。お茶にして飲む「ギンネム」の毒性まで収集してくれているのでかなり信頼できると思います。
沖縄県における有毒な樹木の詳細
• 2.1. ソテツ (Cycas revoluta)
• 植物の特徴と沖縄での分布: ソテツは、沖縄県において庭園や公共スペースの装飾用として広く植栽されている常緑樹です 3。ヤシの木に似た外観を持ちますが、実際にはヤシの仲間ではなく、ソテツ類に分類されます 12。その独特な樹姿は、沖縄の景観に欠かせない要素の一つとなっています。
• 有毒部位:種子を含む全株: ソテツは、種子だけでなく、葉、茎、根など、植物体全体に毒性があります 3。特に、成熟した雌株にできる鮮やかなオレンジ色の種子は、見た目が美しく、子供などが誤って口にしてしまう危険性があります 3。
• 主要な毒性成分と作用機序: ソテツの主要な毒性成分はサイカシンであり、これは体内で分解されてメチルアゾキシメタノールという強力な肝臓毒や神経毒を生じさせます 13。
• ソテツ中毒の症状: ソテツを摂取した場合、症状は摂取後数時間から数日遅れて現れることがあります 13。初期症状としては、吐き気、嘔吐、下痢(血便を伴うこともある)、食欲不振、腹痛などが挙げられます 5。重症化すると、黄疸(皮膚や目の黄染)、肝機能障害、腎機能障害、意識障害、痙攣、そして最悪の場合には死に至ることもあります 5。ペットがソテツを誤食した場合も同様の重篤な症状を示すことが報告されています 13。• 2.2. ミフクラギ / オキナワキョウチクトウ (Cerbera manghas)
• 特徴と沖縄での生育環境: ミフクラギは、沖縄を含む熱帯から亜熱帯地域に自生する常緑性の小高木です 6。海岸近くや公園、街路樹などにも植えられています 6。白い花を咲かせ、熟すと赤くなる丸い果実をつけることから、オキナワキョウチクトウという別名でも呼ばれます 6。
• 有毒部位:全株、特に果実と乳液: ミフクラギは、葉、枝、果実、そして切り口から出る白い乳液など、植物体全体に毒性があります 6。特に、熟した赤い果実は、見た目がマンゴーに似ているため、誤って口にされる危険性があります 7。
• 主要な毒性成分:ケルベリン: ミフクラギの主要な毒性成分は、強心配糖体の一種であるケルベリンです 7。
• ミフクラギ中毒の症状: ミフクラギを摂取すると、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛などの消化器系の症状が現れることがあります 9。また、不整脈や徐脈、低血圧などの心血管系の症状を引き起こし、重症化すると死に至ることもあります 9。乳液が皮膚に触れると炎症やかぶれを引き起こし、目に入ると腫れや痛みを伴うことがあります 6。和名の「ミフクラギ(目脹ら木)」は、この乳液が目に入ると腫れることに由来しています 6。かつて沖縄では、この植物の毒性を利用して魚を捕獲する漁法が行われていましたが、現在は禁止されています 7。• 2.3. キョウチクトウ (Nerium oleander)
• 沖縄での生育状況(外来種): キョウチクトウは、日本在来の植物ではありませんが、沖縄県内では庭園や公園、道路沿いなどに観賞用として広く植栽されている常緑性の低木または小高木です 3。美しい花を咲かせるため、緑化樹としても利用されています。
• 有毒部位:全株、特に乳液: キョウチクトウは、花、葉、枝、根、種子、そして白い乳液など、植物体全体に強い毒性があります 3。
• 主要な毒性成分:強心配糖体: キョウチクトウの主要な毒性成分は、オレアンドリンなどの強心配糖体であり、これは心臓の機能を著しく阻害します 5。
• キョウチクトウ中毒の症状: キョウチクトウを摂取すると、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢などの消化器系の症状が比較的早く現れます 5。その後、不整脈や徐脈、頻脈、低血圧などの心血管系の症状が現れ、重症化すると心停止を引き起こす可能性があります 5。神経系の症状としては、めまい、頭痛、錯乱、眠気、昏睡などが報告されています 19。皮膚が乳液に触れると、炎症や皮膚炎を引き起こすことがあります 20。キョウチクトウは乾燥にも強く、公園や道路分離帯などにも植えられているため、身近な場所で注意が必要です 9。• 2.4. ハゼノキ (Toxicodendron succedaneum / Rhus succedanea)
• 沖縄での分布と特徴: ハゼノキは、アジア原産の小高木であり、沖縄県内でも紅葉の美しさから観賞用として植栽されることがあります 4。ウルシ科の植物であり、接触性皮膚炎を引き起こすことで知られるアメリカのポイズンオークやポイズンアイビーと同じ属に属します 4。
• 主な危険部位:樹液と果実(議論あり): ハゼノキの新鮮な樹液には、皮膚に触れると激しい炎症を引き起こす有毒物質が含まれています 4。症状としては、発疹、強いかゆみ、炎症、水ぶくれなどが現れます 4。果実については、酸味のある果肉が食用になるという情報もありますが 24、植物全体の毒性を考慮すると、摂取は推奨されません 23。
• 毒性成分: 樹液には接触性皮膚炎を引き起こす成分が含まれています 28。葉には、発がん性物質であるシキミ酸が含まれています 24。
• ハゼノキによる中毒症状: 主な症状は、樹液との接触による皮膚炎です 4。果実を摂取した場合の明確な中毒症状は不明ですが、安全性を考慮し、摂取は避けるべきです。
• 2.5. ハスノハギリ (Hernandia nymphaeifolia)
• 沖縄での分布と特徴: ハスノハギリは、熱帯から亜熱帯の海岸地域に分布する高木であり、沖縄県でも見られます 29。大きなハート型の葉と、提灯のような形をした特徴的な果実をつけます 30。
• 有毒部位:種子: ハスノハギリの種子には、有毒なアルカロイドが含まれています 31。
• 毒性成分:アルカロイド: 種子に含まれるアルカロイドが毒性の原因です 31。植物体全体には、細胞毒性などの活性を持つリグナン類も含まれていることが研究で示されています 32。
• ハスノハギリによる中毒症状: 種子を摂取すると、めまいや下痢などの症状が現れることがあります 31。• 2.6. ギンネム (Leucaena leucocephala)
• 沖縄での分布と利用: ギンネムは、熱帯アメリカ原産の быстрорастущее дерево であり、沖縄県内では荒地や空き地などに広く自生しています 35。成長が早く、薪や緑肥として利用されることもあります 35。また、近年ではギンネム茶として利用されることもあります 35。豆果の中に種子が入っています。
• 有毒部位:主に葉と種子(豆果): ギンネムには、ミモシンという毒性アミノ酸が含まれており、特に葉と種子に多く含まれています 36。
• 毒性成分:ミモシン: ミモシンがギンネムの主要な毒性成分です 36。
• ギンネムによる中毒症状: 人間におけるギンネム中毒の報告は限られていますが、動物(主に家畜)では、脱毛、甲状腺腫、成長不良、食欲不振などの症状が確認されています 36。一部の情報源では、人間が摂取した場合に重度の下痢や嘔吐を引き起こす可能性が示唆されています 44。また、近縁種の未熟な果実では幻覚や胃の不調が報告されています 46。ギンネムの葉を茶として摂取する習慣があることから、慢性的な低レベルのミモシン摂取による長期的な影響も考慮する必要があります。• 注意すべき類似の果実:アダン (Pandanus tectorius)
• 沖縄県の海岸沿いなどでよく見られるアダンは、オレンジ色でパイナップルのような形をした大きな果実をつけます 47。この外見から、観光客などがパイナップルと間違えてしまうことがよくあります 47。しかし、アダンの果実は非常に繊維質が多く、人間が食用とするには適していません 48。味もあまり良くなく、無理に食べようとすると不快な思いをする可能性があります 48。アダンの果実は、ヤシガニやヤドカリなどの一部の動物にとっては食料となりますが 47、人間の食用にはならないことを理解しておく必要があります 53。アダンの果実を誤って口にしても、通常は致命的な中毒を引き起こすことはありませんが、不快な症状を避けるためにも、食用ではないことを認識しておくことが重要です。
つづく
① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!