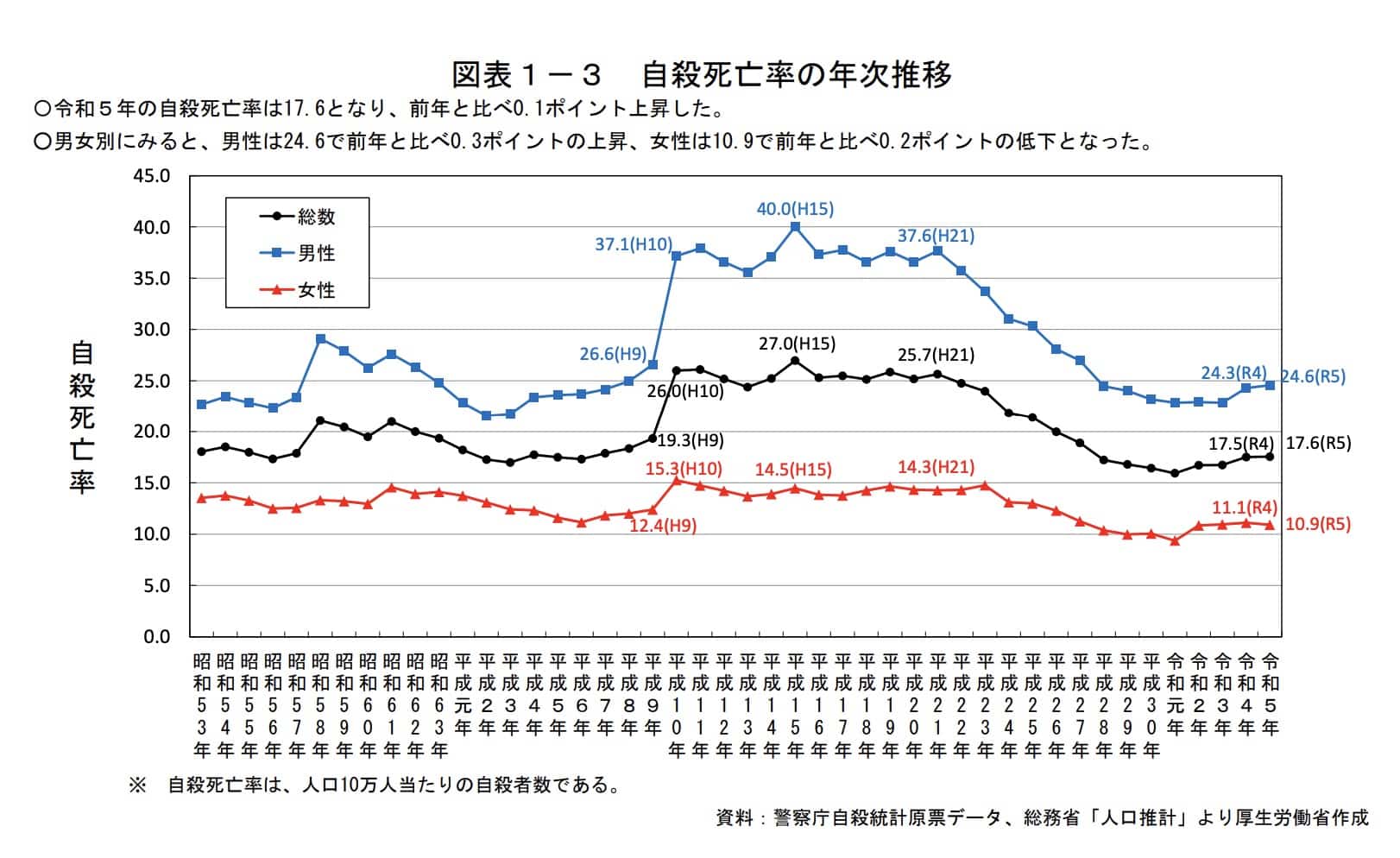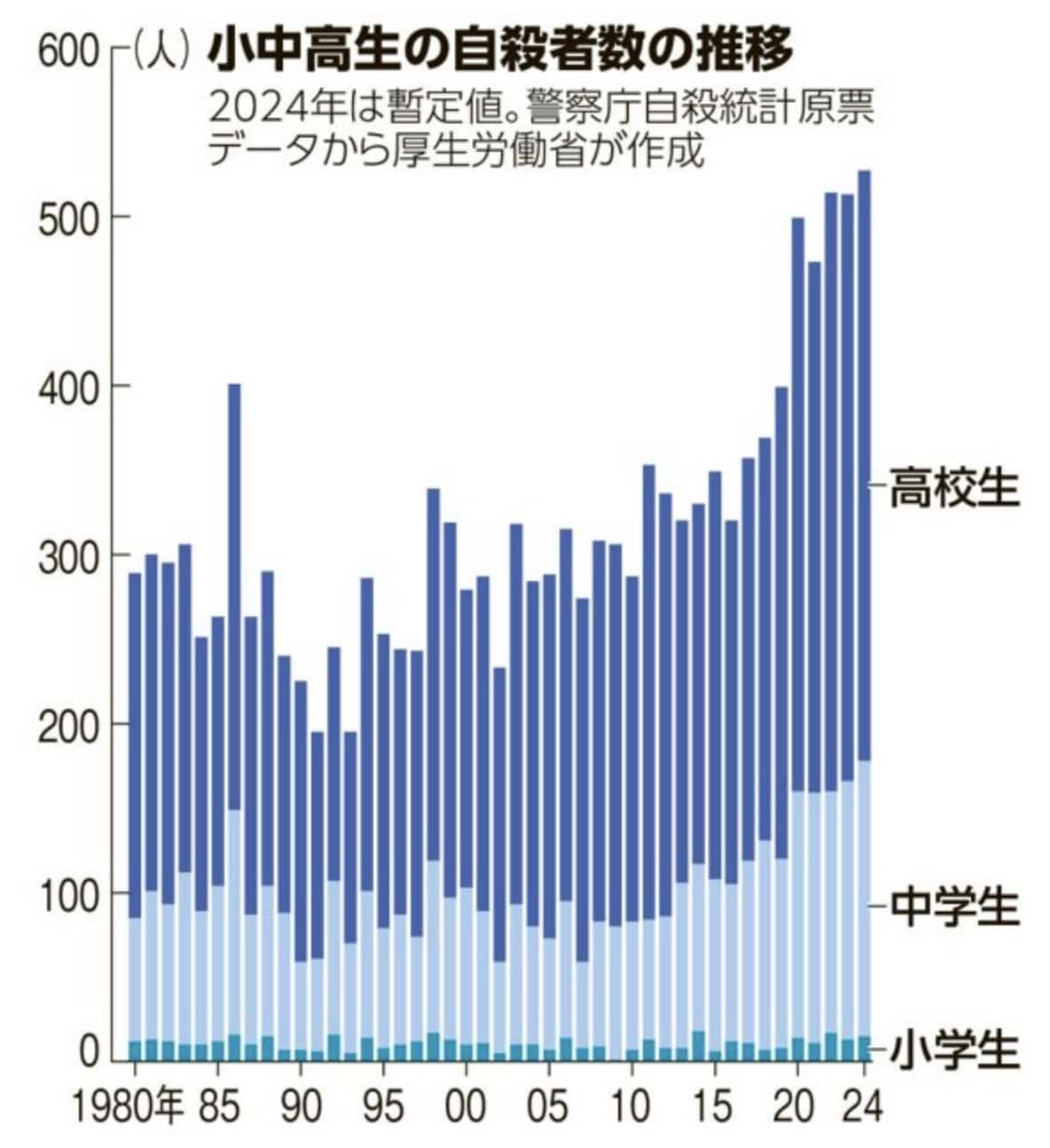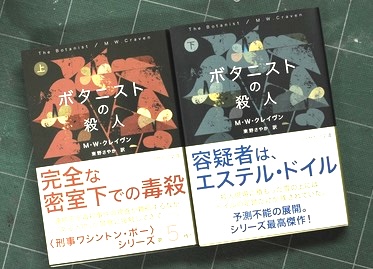花を見て歩くことも楽しいのだけど、畑の野菜たちを見ながら歩くこともかなりたのしくて、おすすめです。
沖縄のこの頃はマンゴの実りの時期で、ビニールハウスをみると、タワワに成ったマンゴたちが白い袋に入っている姿を見ることができます。
この写真がそうです。

マンゴというのは自然に育てると、一つの枝にいくつも実がつきます。
これは、あまり手をかけずに自然に近い状態で育てたマンゴです。
伸びた枝から5個も6個も実がなっています。
スーパーなどに並ぶマンゴよりかなり小さいサイズです。
甘さはどうなんだろう?

そうやって歩いていると遠くに陽が沈む美しい光を見ました。
山並みに沈むところです、時間は19:15くらいです。

考えてみるとそろそろ夏至の頃です。
調べてみると6/21(土)が夏至、日没時間は19:25です。
その日を境に、冬至(クリスマスの頃)まで日照時間が短くなっていきます。
その太陽の動きにともなって、畑の作物たちもどんどん変わっていきます。もちろん野山の草花樹木も変わっていきます。
たのしみです。
① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!