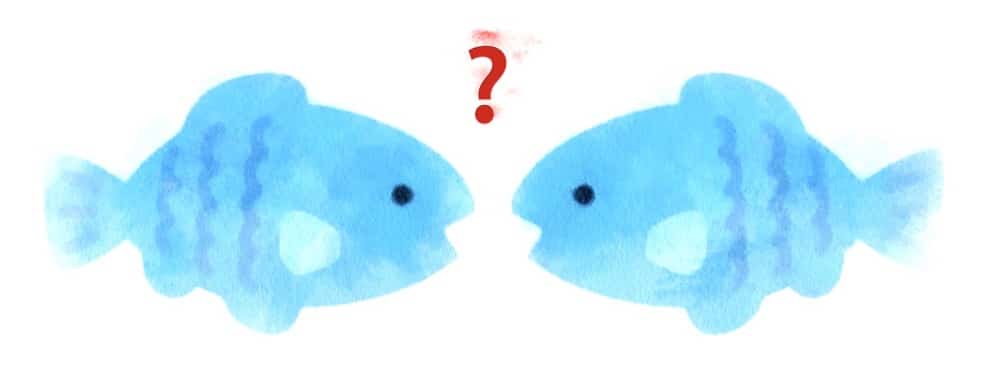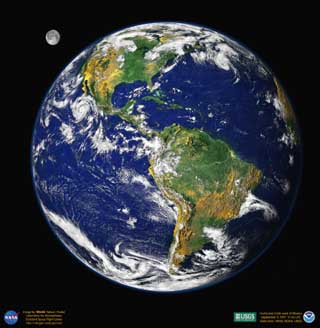メルマガにChatGPTの利用の話を書いたところ、いろいろな質問が寄せられました。それに対して書いた一部を紹介しましょう。
ChatGPTの質問たくさん届く
ChatGPTの記事の反響が大きくいろいろな声が寄せられています。その中の質問から一つとりあげさせてください。
わたしの質問に的確な提案していくChatGPTの反応に「ChatGPT(A.I.)が考えて答えているのですか?」という問いがありました、みなさんはどう思いますか?
⇩
⇩
⇩
違います。
サーバーやネット上に蓄積された膨大なデータの中からこちらの要求に沿った情報を選び出し、組み合わせて日本語の文法にそって組み立てて答えるので、まるで人間と話しているように感じているだけです、A.I.が自ら考えているわけではありません。
たとえば「〈あいうえお〉だけ、全て使って意味のある文を作ってください」と打ってみましょう、どういう答えが返ってくるかたのしみですね。
⇩
⇩
⇩
しばらくしてあとChatGPTから「〈あいうえお〉のみを使用して完全に意味のある自然な日本語の文章を作るのは難しいです」と降伏した答えが返ってきました。
☆⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎引用ここから⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎☆
わたし
「あいうえお」のみ、全部利用して文章をつくってくれませんか。
ChatGPT
「あいうえお」のみを全部使用して意味のある文章を作成するのは非常に制限が多いため、完全に自然な日本語の文章を作ることは難しいです。しかし、以下のように工夫して表現することは可能です。
例文:
「あ、い、う、え、お!」
解釈:
これは、日本語の五十音の最初の五つの音「あ、い、う、え、お」をリズミカルに並べた表現です。教育的な場面やリズム遊びの一環として使用されることがあります。
補足説明:
リズムや韻を楽しむ: 子供たちが五十音を覚える際にリズミカルに唱えることで、覚えやすくするための表現として有効です。
音遊び: 言葉遊びやリズム遊びの一部として、「あいうえお」を繰り返すことで楽しむことができます。
まとめ
「あいうえお」のみを使用して完全に意味のある自然な日本語の文章を作るのは難しいですが、音の並びやリズムを楽しむ表現として活用することができます。教育的なツールや音遊びの一環として利用することで、楽しみながら五十音を学ぶ助けになるでしょう。
☆⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎引用ここまで⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎☆
ChatGPTが音を上げたのはなぜか?
ChatGPTが「難しい」と音をあげたのはなぜでしょう。
膨大なネット上を探っても、私の要求に添える答えが見つからないからです。
これまでChatGPTにこういう要求をする人もいなかったので、頑張った結果「あ、い、う、え、お!」というような唖然とする答えになったのでしょう。
では自分の頭で考えてみましょう。
・・・(数秒思考中)・・・
できました!
「上、青い(うえ、あおい)」
「あ、魚! 鱏?」
「言え、愛、青(いえ、あい、あお)」
「言え、愛、青、家、鱏」
「お~、上、赤い!」
「えいえいオ~、青い鵜」
「鵜、青い鱏」
「上、青い家」
まだいけそうです、みなさんも考えてみてください、たのしいですよ。
私たちの頭脳はChatGPTの限界を突破することができます。
逆にChatGPTには人間の発想力や個性の限界を超えることはできません。この宇宙唯一の私たちの個性・能力を凌駕する力はChatGPTにはありません。
できるのは膨大な情報の中からこちらの要望に応えるものを探して組み合わせ、日本語の自然な論理構造で提供する作業です。
とはいえネット上にある知識の量は膨大です、それらを組み合わせたら〈星の数ほどある〉といってよいでしょう。当然、私たち一人二人の頭脳ではこの知識量を上回ることはできません。
A.I.を利用するということは、この星の数ほどある知識量の組み合わせを利用するということです。数秒で返ってくるので対話しているように思考を深めていくことができます。
ChatGPTが回答する時「○秒の間思考」と出たりするけれど、思考しているわけではないのです。
以上が読者の方たちからの質問に対する私の答えです。
ではここから私に質問させてください。
私たち人間の思考も、A.I.と同じように数ある情報を集めて組み合わせているだけではないのか、そうだとしたらA.I.と同じではないか。
どうでしょう?
自由研究してみませんか。
長くなるのでここらへんにしておきましょう。
① 毎日1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

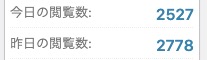
 心動かされたものごとは、予想を立てて調べてみることです。
心動かされたものごとは、予想を立てて調べてみることです。