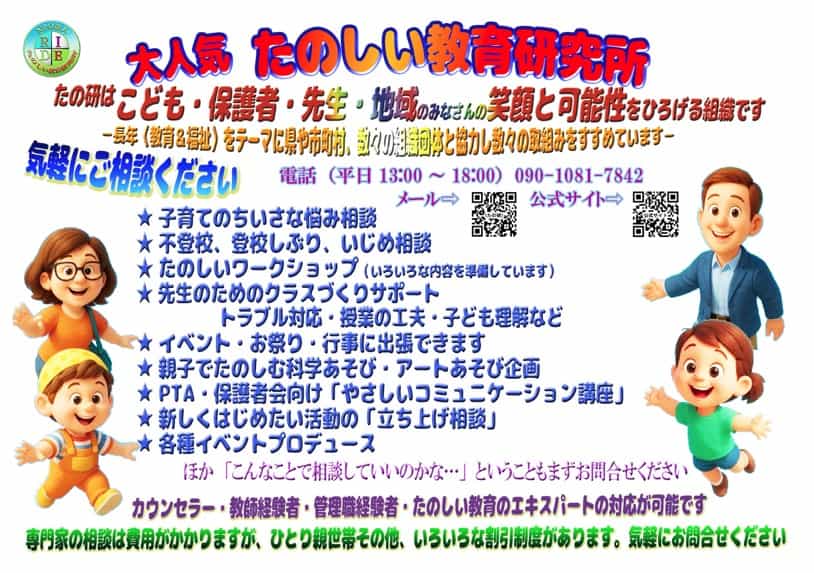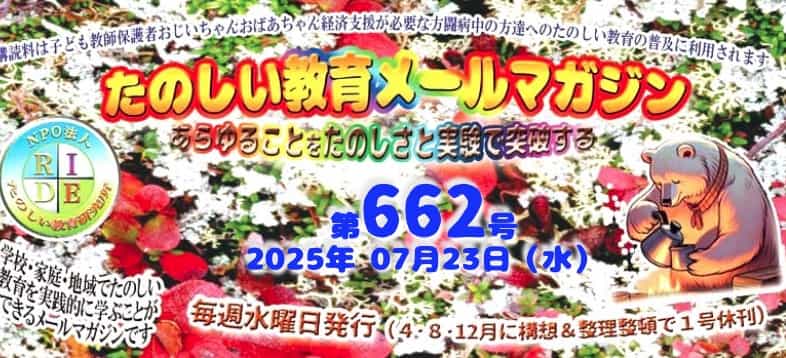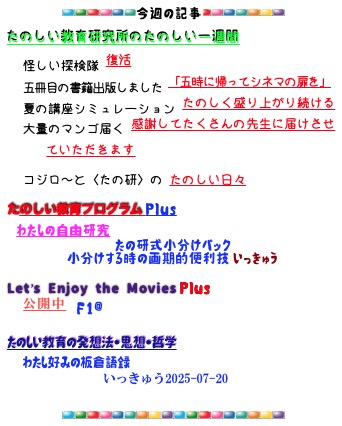最近読んだ刑事物の小説に出てきた会話を紹介します。
久しぶりに娘の元を訪ねた刑事のシーンです。
娘が自分の息子に向かって「いつまでスマホで漫画みてるの!」と叱るシーンで、父親に嘆きます。
「この子、学校から帰ったら宿題しないでずっとスマホばっかりなの…
お父さん、子どもにスマホをやめさせる一番いい方法は何だかわかる?
・・・
みなさんはどう思いますか?
⇩
⇩
⇩
会話はこう続きます。
「コンピュータゲームなの。
笑えるわよね」

主人公の刑事は笑いませんでしたが、私は笑ってしまいました。
その子はその道で可能性を伸ばす可能性があります。
とはいっても科学の楽しさはコンピュータに閉ざされた世界を簡単に凌駕します。
先日ある方から、栽培しているシイタケを見せてもらいました。ふくふくして大きく、とても美味しそうです。
なんと一週間くらい菌糸に水をスプレーしていくだけで、スーパーで売られているシイタケより大きくなったとのこと、おどろきました。
コンピュータゲームも楽しいけれど、自然や科学はかんたんにそれを超えていくでしょう、そのを体感してもらうのがたのしい教育です。
興味のある方は12月のクリスマススペシャルを体験してみてください。
① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!