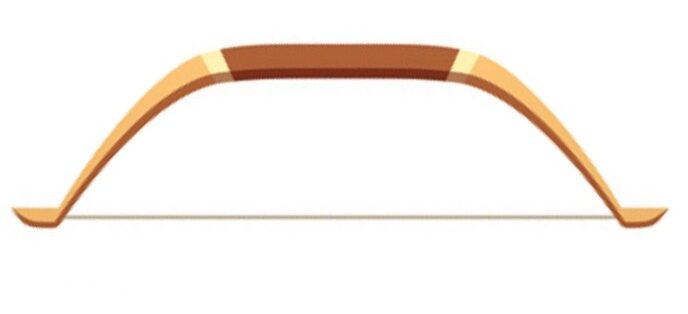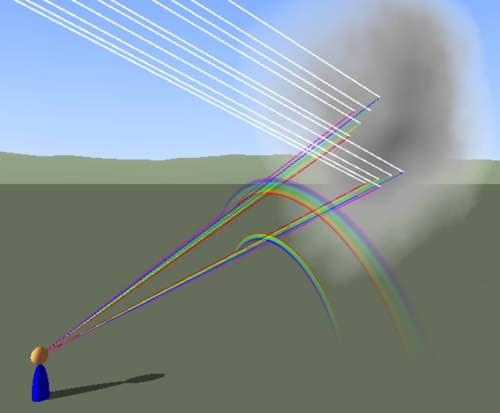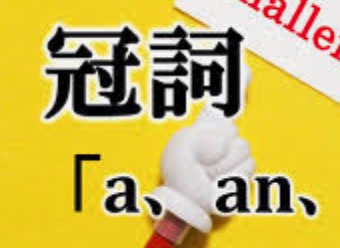以前,アメリカで宇宙飛行士の講演を聞いた時、「That’s a good question/いい質問ですね」というフレーズが何度も出てきて気になったことがありました。
気づいてみたら日本のテレビ番組などでも、そう語る人たちが増えてきていますね。

この間、テレビで流れたある授業のワンシーンにもそのフレーズが出てきたので驚いてしまいました。
質問に〈良い質問〉があるとしたら〈悪い質問〉や〈取るに足りない質問〉があるということでしょうか。
私もいろいろなところで授業や講演などをしてきたのですけど、こちらはたくさんの人たちの前で話すことに慣れている上に、話の内容を整理して、ああでもないこうでもないと考えた上で臨んでいるのに対して、それを聞いた側は、そういう話の内容にはじめてそういう話を聞いて、よくわからないところとか、質問する側は勇気を出して、一生懸命考えながら話をしてくれます。
授業でもまさにそうでしょう。
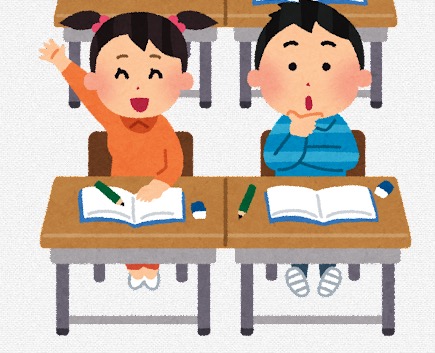
語り慣れた教師と違って、子どもたちははじめてその話を聞いたり、もっとそれを知りたいということが聞いたり、意味がわからなくて聞いたりするわけです。
がんばって手を上げて聞いてくれたその質問に、ある子の質問には「それはいい質問ですね」といい、別の子にはそういうことはを言わない・・・
※
アメリカでの講演の話に戻りましょう、宇宙飛行士の次に宇宙工学の専門家が講演をしていました。宇宙ステーションの居住環境についてとても興味深い話をしてくれていて、面白く、講演後に手を上げて質問してみました。
その時、彼は「Thanks for asking that./聞いてくれてありがとう」と言ってから詳しく話をしてくれました。
あ~、気持ちいいいい方だな、私は〈いい質問ですね〉よりずっとこっちの方が好きだな、と感じて、日本にもどってから真似ることにしました。
他にも「その質問は、先生も考えさせられるなぁ」とか「その気持ち、よくわかる」という様に伝える様にしていました。
可能な方はご利用ください。
① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!