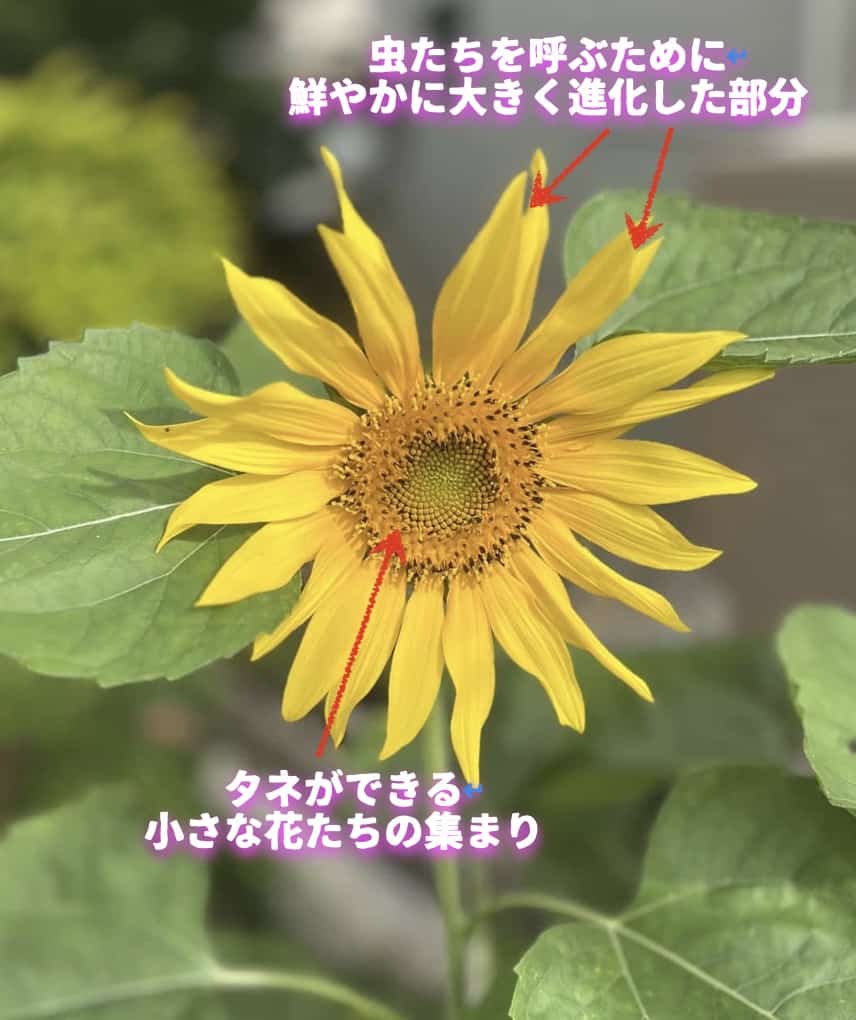〈たの研〉の若手中堅の先生たちが中心になって、毎月「たのしい教育Enjoy-Cafe」が開催されます。
今月の様子が送られてきました、〈たの研〉の個人情報保護規定に合わせて加工した画像を交えて紹介します。
前回の記事、絵本の紹介でも取り上げたのですけど、〈たのしい教育〉で絵本・書籍は強力なプログラムになります。
これはA先生が紹介している様子です。
画像加工してもなおあふれ出る笑顔がわかると思います。
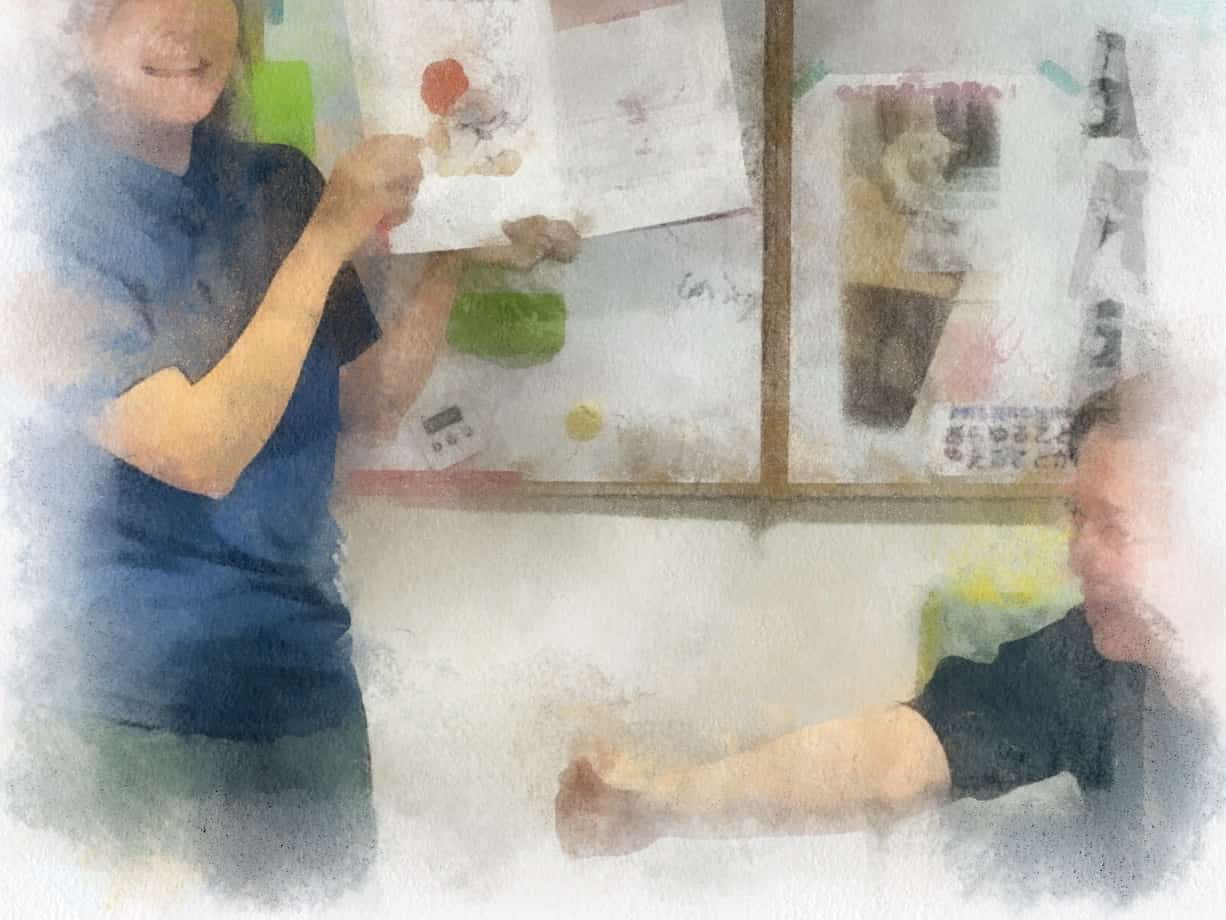
2部屋つないで広くした場所いっぱいに、たくさんの人たちが集っています。
みんな笑顔です。

これは折染めをたのしんでいる様子、周りの人たちはワクワク顔です。

たのしい教育は、子どもたちがのめり込んでくれる、深い内容を伴ったプログラムです。
もっと学びたい、そう感じて、家に帰ってから家族に紹介してくれる子どもたちがたくさんいます。
たとえば「折染め」を単なる遊びだと考えている人もいるかもしれません、違います。
楽しんだほとんどの子どもたちは
⭐︎ 色の混合で発色のバリエーションを体感し感動を深めてくれます
⭐︎ 色付ける場所の違いや回数で、二度と生まれない想像を超えた造形に感動してくれます
☆紙を折る行為や、開いたときの模様の対称性から、図形や空間の概念を直感的に学ぶことができます
☆ 次第に予測力と論理的思考の芽生え:「こう折ったらどうなるか」「この色をつけたらどう広がるか」など、結果を予測する力を高めていきます
☆ 友達と作品を見せ合ったり、感想を言い合ったりする中で、コミュニケーション能力や協調性が養われる、つまり仲がよくなります
☆ 指先を使って紙を折ったり、染料をつけたりする作業は、手の器用さや巧緻性を高めます
☆リラックス効果とストレス軽減: 創造的な作業に没頭することは、心を落ち着かせ、リラックス効果やストレス軽減につながります
☆ 日本の伝統的な染色技法(絞り染めなど)にも通じる部分があり、日本の文化や伝統工芸への関心を抱くきっかけになります
☆ 折染めを書道やものづくりなどに活かすことができるようになります
ほかいっぱい!
学力向上も、たのしい教育でこそ実現できるでしょう。
次回の〈たのしい教育Enjoy-Cafe〉は6/28(土)14:00~16:00です。
希望する方は、席の空きがあるかまずお問合せください⇨ office@tanoken.com
① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!