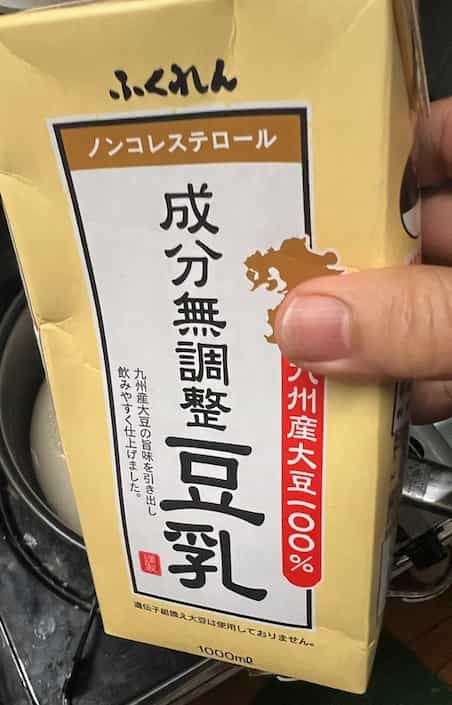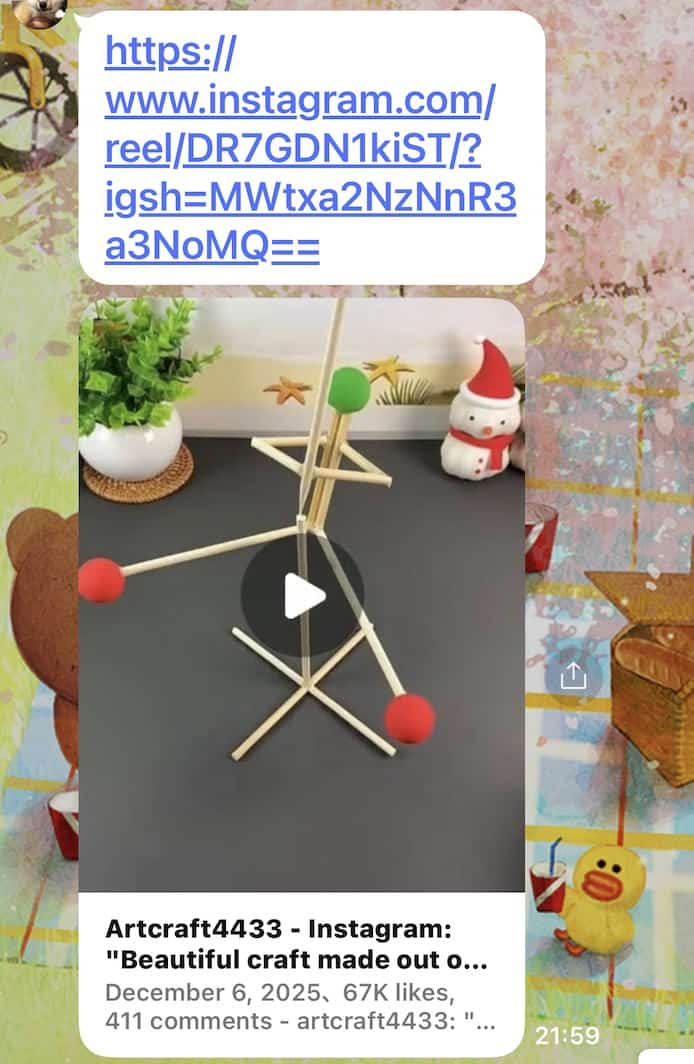メルマガを執筆してあと、たのしい教育ラボの近くの川沿いの細い公園を歩きました。
勝手にリバーサイドパークと名付けたその場所には梅の木が植えられています。
嬉しいことに今年は梅や桜の開花が遅く、まさに花盛りの梅の木に出会うことができました。

冬の冷たい空気の中で、白い小さな花が輝いて、とてもきれいです。
よい香りも漂っています。
あと3~4日で今年の見頃は過ぎて、また来年の季節を待つことになるのでしょう。

今年は楽しい福祉&教育 で〈楽しい食育・たのしい食育〉に力を入れています。
梅の実は梅干しとして古い時代から親しまれています。
でもそれを作るのはこどもたちには難しい。
以前から〈花〉を食べたらどんな味かと考えていました。
調べてみると…
梅の花は食用可能で、春の訪れを感じさせる香り高いエディブルフラワー(食用花)です。
花茶や塩漬け、お吸い物の具、天ぷらなどとして親しまれています。
栄養面ではポリフェノールやクエン酸、ビタミンCを含み、疲労回復や殺菌、喉の渇きを癒やす効果が期待されています。
主な楽しみ方・食用方法
-
-
梅の花茶(花茶): 生の花や乾燥させた花にお湯を注ぎ、見た目と香りを楽しむ。
-
梅の花の塩漬け: 梅の花を洗って塩をまぶし、重石をして3日ほど置く。お吸い物やおにぎり、お茶請けに。
-
料理の彩り: お吸い物、サラダ、ちらし寿司の具材として、そのまま、またはさっと茹でて使用。
-
天ぷら: 軽く薄衣をつけて揚げる。
-
〈たの研〉には「こどもマルシェチーム」があって、栄養士の先生も入っています。
今度、落ちたての花を集めて、楽しい食育プログラムの実験をしようと思います。
① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!