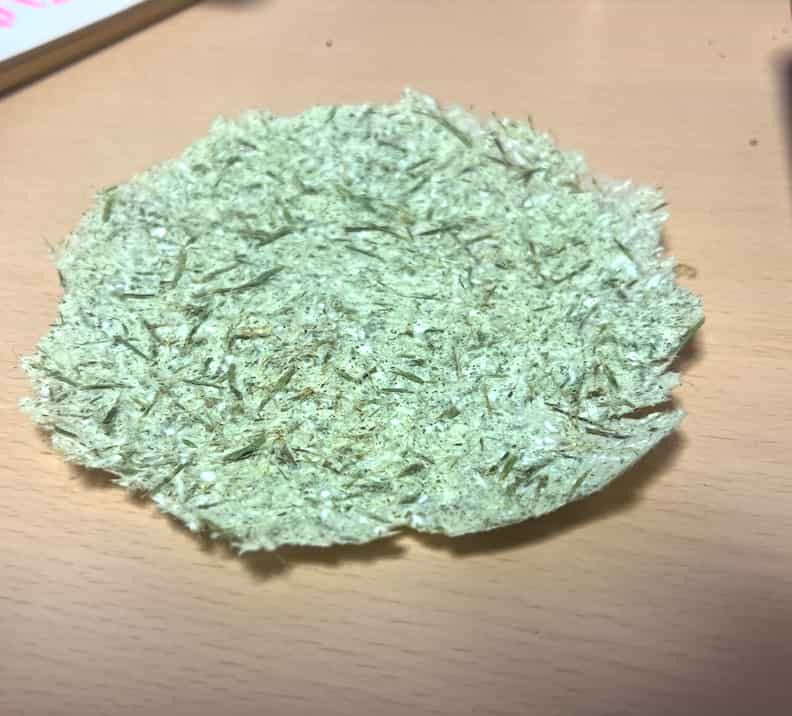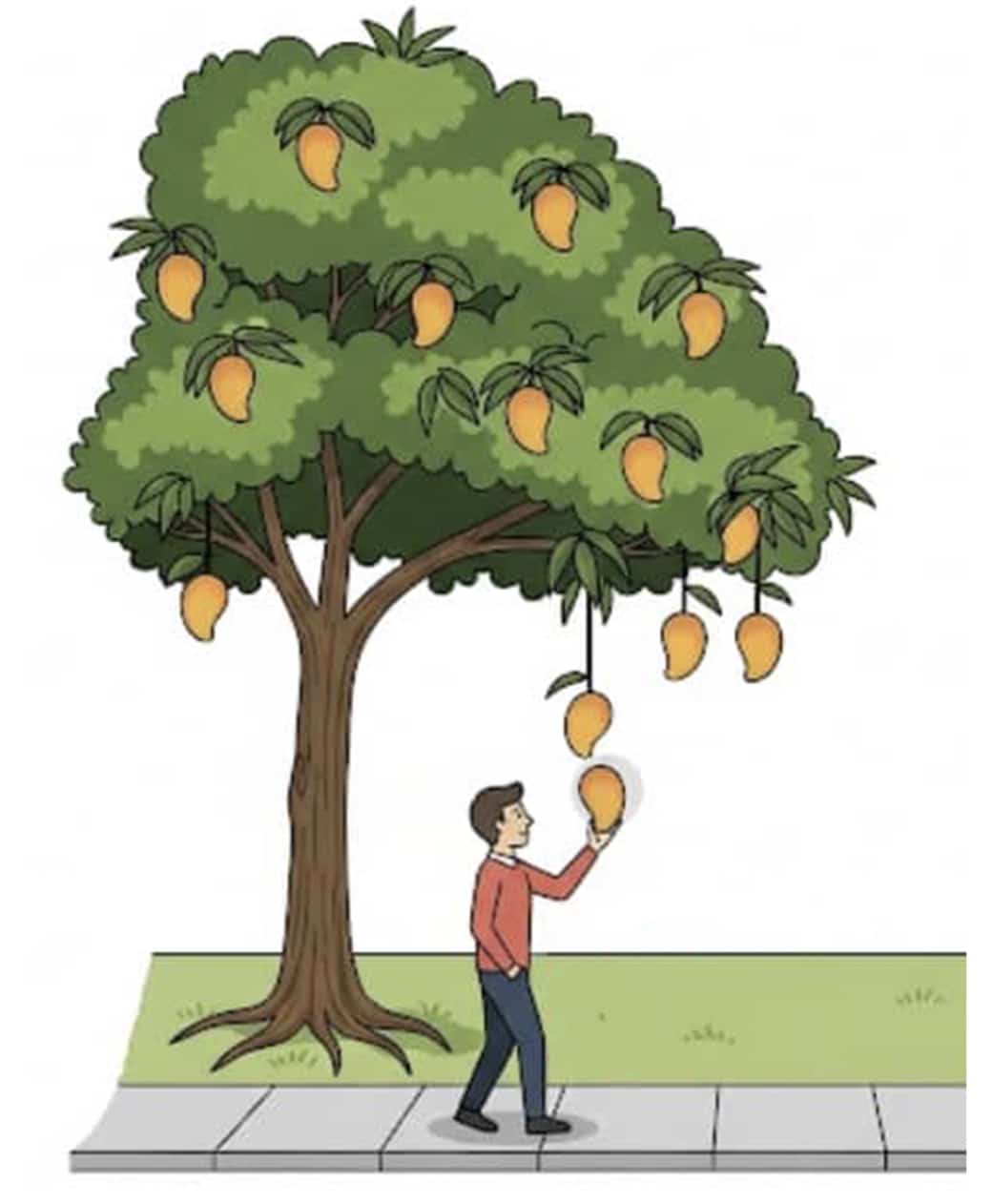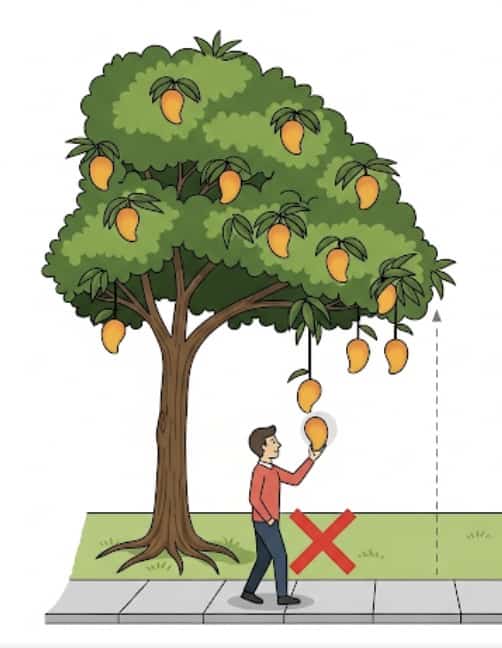新しい教育プログラム『文字の力』〈授業書@たの研〉を作成しています。 今回は全体的に早めに進んでいるので、紙に打ち出しての校正やブラッシュアップをするゆとりがあります。
紙で読むと、単純な校正作業だけでなくて、全体を把握した中で「ここはさらにこう書いた方がよい」「これはカットした方がよい」というようなブラッシュアップが遥かに早く進みます。
忙しさの中で逆に遠回りになっていたことを再認識しました。
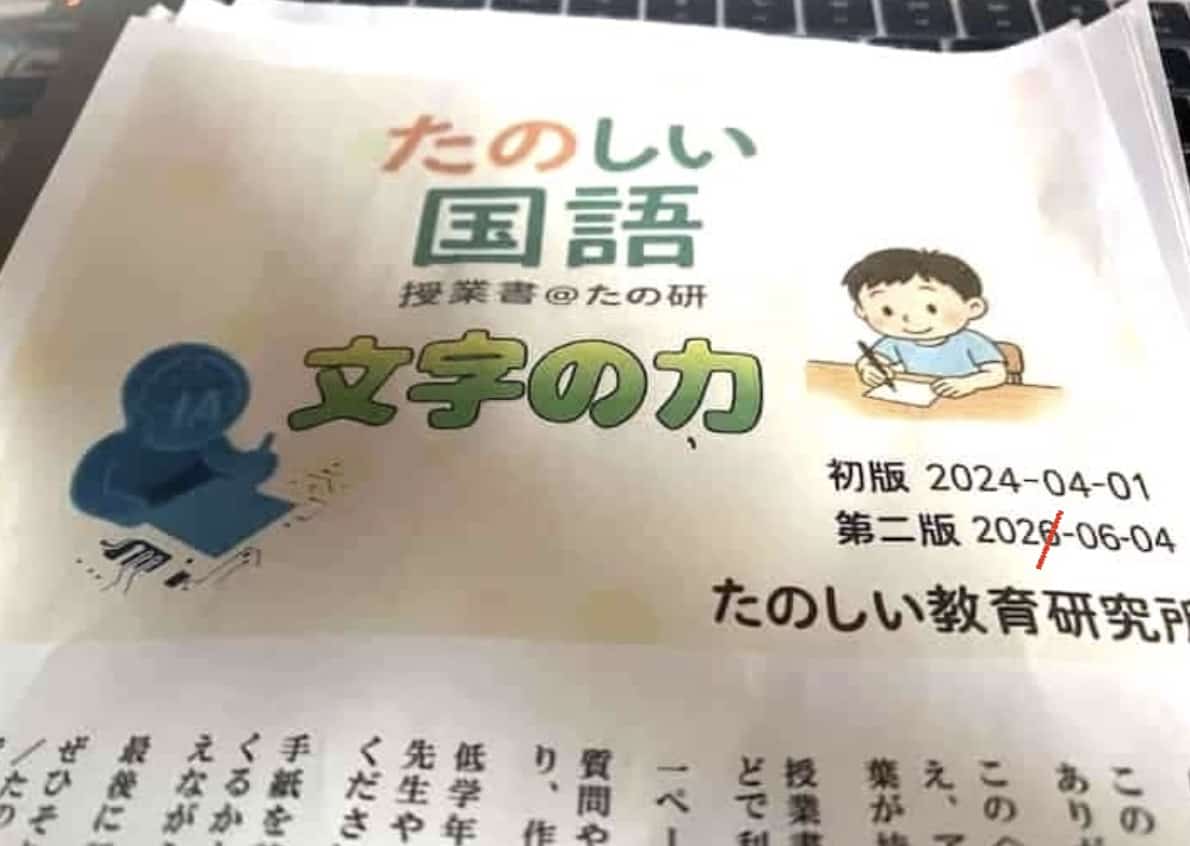
さてそれは本好きの私の個人的なスタイルに合っているからなのか?
みなさんはどう思いますか?
問題
一般的に言って、紙で読む方が〈読みの質が高くなる〉といってよいのか?予想
ア.それは個人的なもので人それぞれ違う
イ.一般的にそう言える
ウ.その他
どうしてそう予想しましたか?
※
こういう研究は注意してみないといけません。デジタル機器を広めるために大量の資金を投与している企業がたくさんありますから、その企業に有利なように結果を出す研究もあります。
一つ二つの確認では間違ってしまうことがあります。
大量の研究をサーチして結果をみなくてはいけません。
それに適しているのはA.I.です。
二つのA.I.&webサイトでトリプルチェックしてみました。
結果として「明らかに紙で読む方が質の高い読みになる」といって間違いないようです。
軽く整理してみると…
| 視点 | 紙の方が優位になる主な理由 | 典型的な効果 | 参考ソース |
|---|---|---|---|
| 視覚・生理 | 紙は反射光で高コントラスト/ちらつきゼロ。画面はブルーライト・グレア・ピクセル間隔が眼球運動を細切れにし、疲労を早める。 | 読字スピード低下・誤字見落とし増加 | researchgate.net |
| 注意制御 | 紙は通知・タブ・スクロールがなく、視野内の情報量が限定されるため“深いモード”に入りやすい。 | 集中維持時間↑、読み飛ばし↓ | phys.orghechingerreport.org |
| 空間マッピング | 紙面は「物理ページ位置」「指先の触覚」で脳内に立体的マップが形成され、誤植や論理飛躍に気づきやすい。 | 文脈想起・段落間の整合性チェックが容易 | wired.com |
| ワーキングメモリ | スクロールは情報が流動し、直前の文脈を保持しづらい。紙は固定されているので保持負荷が軽くなる。 | 文法ミス・重複表現の発見率↑ | snexplores.org |
| 身体性(Embodied Cognition) | ペンで囲む・書き込む・折るといった手指運動が、前頭前野を刺激し再評価を促す。 | 発想転換・追加アイディアの発生率↑ | cambridgeassessment.org.uk |
| メディア意識 | 画面→「暫定ドラフト」感、紙→「最終版」感という心理的緊張差。 | 校正モードへの切替が鮮明 | cambridgeassessment.org.uk |
たくさんの人たちを研究したもの、国際的なものなどがたくさんあるのですけど、読みやすい記事として、こういうものがあります⇨ https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/health/370003
※
けれどそれはある程度の年齢に達した人たちに言えることで、若い人たちとは違うのではないか?
とも考えられます。
あなたはどう思いますか?
問題 若い人たちなら紙で読むのもデジタルで読むのも大差ないのか?
予想
ア.子どもの段階なら大差ない
イ.子どもの時はデジタル機器のようが読む質が高くなる
ウ.子どもの時も紙の方が読む質が高くなる
エ.その他どうしてそう予想しましたか?
※
簡単にいうと「年齢にかかわらず紙の方が誤り検出・理解・発想で優位」という結果 です。長くなるので興味のある方は自由研究しください。
https://yuchrszk.blogspot.com/2024/01/vs.html
ということで「古い」と言われようが、〈より質の高い知的作業〉を目指すなら「紙」で読むことです。
私の楽しい面白い自由研究結果でした。
① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!