ほぼ唯一視聴するTV番組『チコちゃんに叱られる』でたくさんの人たちに紹介したいテーマを取り上げていました。
日本人は普通に「私は」と書いて「わたしわ」と読みます。
これはどうしてか?

私の先生は
「昔は〈てふてふ〉と書いて〈ちょうちょう〉と読んでいたり、〈をとこ〉と書いて〈おとこ〉と読んでいて、〈私は〉は昔の読み方が残ってるんです」
と説明していました。
でもよく考えるとそれは「昔の名残り」といっているだけで、どうしてこんなに違うのかをしっかり説明しているとはいえません。
今週の「チコちゃんに叱られる」で、しっかり謎解きしてくれました。
要旨はこうです。
⭐️奈良時代までは「は」を「ぱ」と発音していた⇨「私ぱ」と発音
そもそも奈良時代までは〈はひふへほ〉がなく〈ぱぴぷぺぽ〉に近い発音だった
⭐️平安時代で「ひらがな」が誕生してた頃は「は」を「ふぁ」と発音していた⇨「私ふぁ」と発音
⭐️平安時代の終わり頃から江戸時代にかけて「は」を「わ」と発音するようになった
「私ぱ」⇨「私ふぁ」⇨「私わ」と変化してきたわけです。
どうしてこんなふうに変化してきたのか?
「楽だから」です。対話していく中でどんどん力がぬけた音に変化してきたというのがその理由。長い歴史の中でどんどん使いやすいものに変化していった、それがまず一つ目の答えです。
「それなら〈私は〉を〈私わ〉と書けばよいのに、どうしてそうしないのか?」という問題が残っています。
それは「古くからの仮名遣い(歴史的仮名遣い)を現代の仮名遣いに直す時に文科省が表記を残したから」というのがもう一つの答えです。1946年(昭和21年)11月16日、吉田茂総理の頃の「当用漢字表の実施」(昭和21年内閣訓令第7号)の「現代かなづかいの実施」のときです。まだ80年くらい前のことで、それほど古いことではありませんね。
① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!
④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎

 「この流れでみると、地球が誕生したのは何月何日でしょう?」というのは知的好奇心をくすぐる問題です、ぜひ子どもたちに出してあげてください。一緒に調べるとたのしさが深まりますよ。
「この流れでみると、地球が誕生したのは何月何日でしょう?」というのは知的好奇心をくすぐる問題です、ぜひ子どもたちに出してあげてください。一緒に調べるとたのしさが深まりますよ。
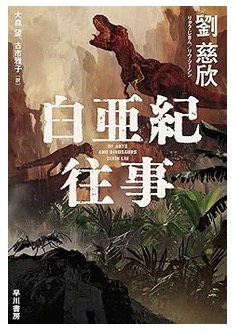 彼はその小説のはじまりで「地球の歴史」を1日24時間で表現しています、図ではなく言葉の力で。
彼はその小説のはじまりで「地球の歴史」を1日24時間で表現しています、図ではなく言葉の力で。









 wikipediaより
wikipediaより