たのしい夏の講座が大盛況のもと開催されました。

予想を超える参加希望者の熱い声に応えて、いつもの人数を倍に増やし、プログラム作り会場作りをすすめているうちにも希望者はどんどん増え、たくさんの方達が受講できない結果となりました。
申し訳ありません。
「みなさんの周りにも残念ながら席を確保できなかった方たちが何人かいると思います、今日たのしんでくれたプログラムをぜひその人たちにも伝えてあげてくださいね」という話をして夏の講座がスタートしました。

前半は『リリエンタールに挑戦』というプログラムと、板倉先生の『科学的とはどういうことか』の一つの章『砂糖水に卵は浮くか』というプログラムを全体でうけて、たのしい自由研究を体験してもらってあと、選択型のプログラムに移りました。
講師の先生たちもノリノリです。

大人も子どもどんどん予想を立ててくれて、笑顔たっぷりの時間になりました。

沖縄のたのしい教育界の泰斗、いらはさんも随分ひさしぶりに講座を担当してくれて、さすが安定の授業運びでした。

終わってあと、講師がそろって参加者全員の評価感想を読むのが〈たの研〉スタイルです。
ドキドキの瞬間です。
結果は満足度100%でした。
プログラムの内容は、機会をみて紹介しようと思います。
子どもも親も一緒になって本気でプログラムをたのしむ姿を思い出しながら、授業者みんなで懇談し、さぁ、次は遠隔地での授業だ、どういうプログラムを実施しよう。加えて病気療養で入院中の子どもたちにたのしいプログラムを提供したい、といろいろなアイディアを出し合っていました。
学ぶことのたのしさ、もっと学びたいと感じてくれるような〈たのしい教育〉をいろいろな方たちに提供していきたいと思います。応援、サポートしてくださる方たちが増えてくれることを期待しています。
① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

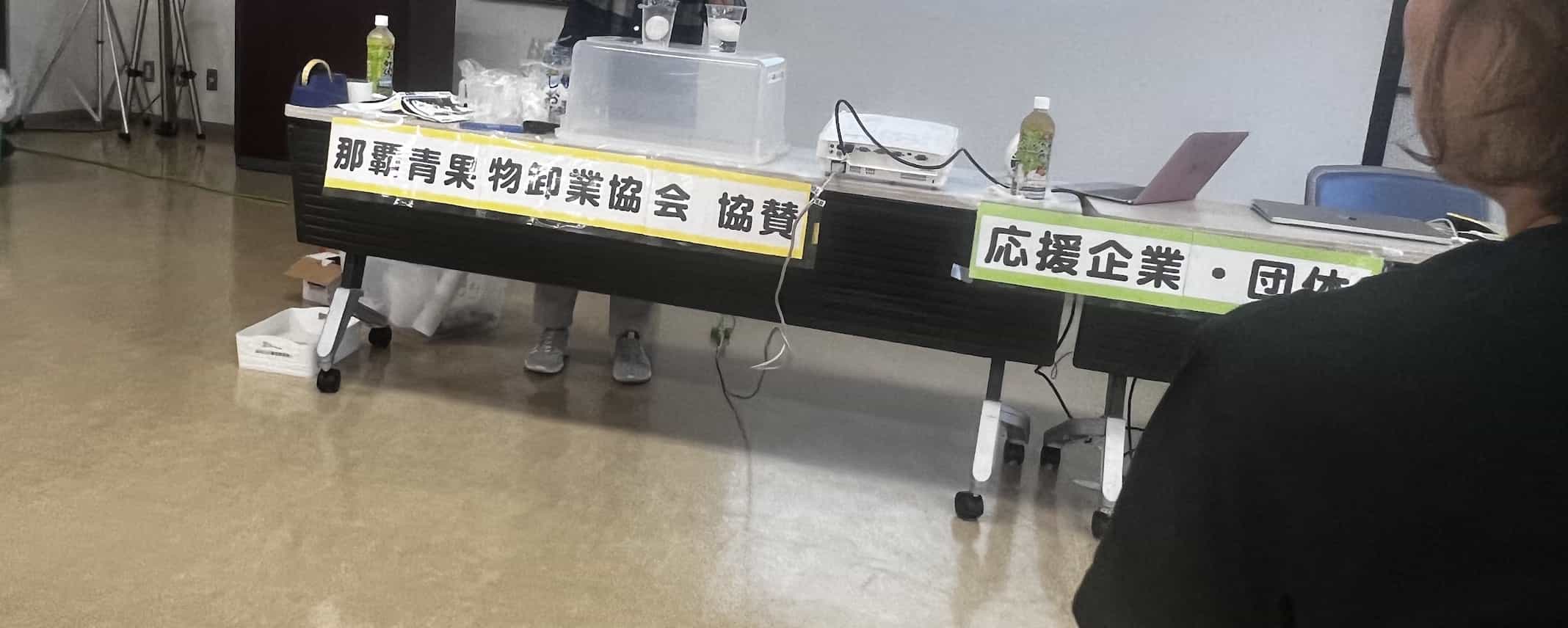 「企業は社会貢献をしなければいけないから」と軽く考える人たちもいると思うのですけど、これだけ日本の経済活力が落ちてきた現在、教育活動を支援するというのはなかなか難しいことです。
「企業は社会貢献をしなければいけないから」と軽く考える人たちもいると思うのですけど、これだけ日本の経済活力が落ちてきた現在、教育活動を支援するというのはなかなか難しいことです。



