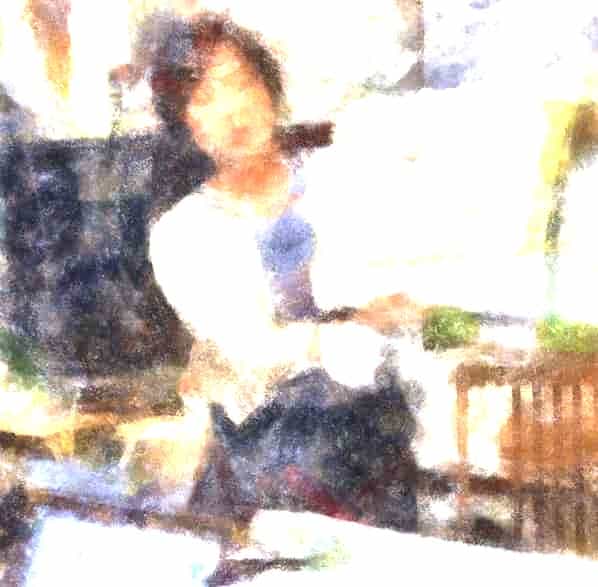夏休みに入り、〈たの研〉で学んだ先生たちがおしゃべりしに来てくれました。
学校のこと、日々のことetc.
たくさんん語ってくれて、たのしい時間になりました。

そもそも、教師になる頃のほぼ全員が、たのしい教師生活を目指していたはずです。それが、日々の忙しさ、学校の「ねばならない型の風土」に、ごく普通のというか、ため息の多い日々をおくる教師はたくさんいるとおもいます。
子ども心を失わない、チャレンジ精神を失わない、それが大切です。
自分で突破できない時には、たのしい発想の先生から学んでいく、そういうことで、たのしくすすめていけるでしょう。
〈たの研〉はそういう先生たちを全力でバックアップしたいと考えています。
福祉の場面で「たのしさ」の発想を持つ人はかなり少ないのが現状です、ハードな事例がたくさんあるからでしょう。
でも困難を抱えた人たちが、少しずつ明るい未来にすすんでいく、それをサポートするのはたのしいことに違いありません。
〈たの研〉は福祉の場でがんばっている方たちも全力で応援しています。
いよいよ、福祉活動の一環としての「自由研究まつり」も近づいてきました、〈たの研〉のスタッフ一同全力でブラッシュアップにとり組んでいます。
福祉の場面でも、教育の場面でも、たのしいプログラムが欲しい、困った時の突破の仕方をコーチして欲しい、そういう方はどんどんご相談ください。
① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!