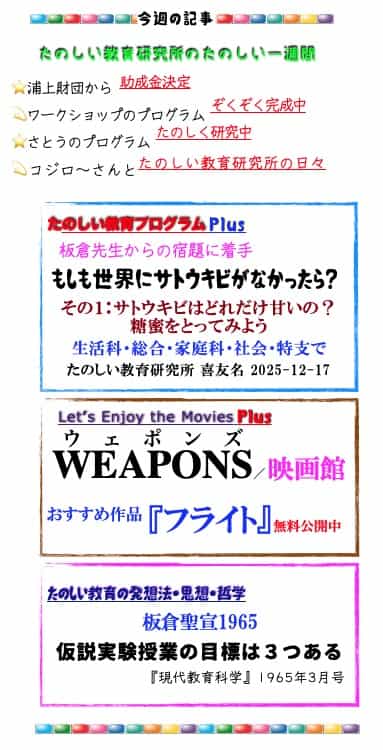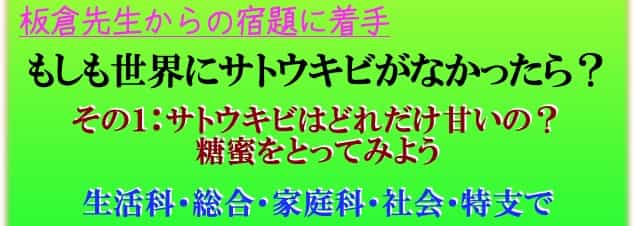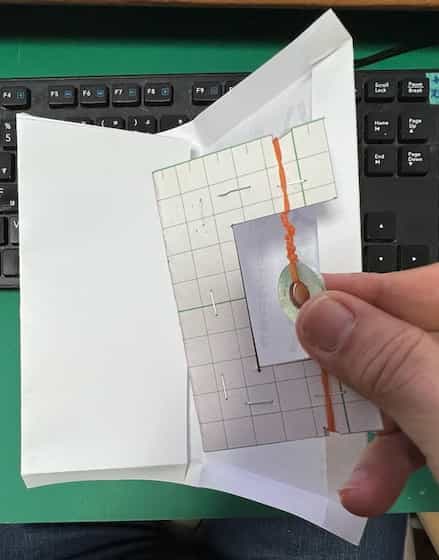〈ヤクルト1000〉や〈LG21〉など液体の 乳酸菌飲料からヨーグルトをつくる研究は、ほぼ100%成功するくらい試してきて、すでに次の段階に入っています。
チーズからのヨーグルトづくりです。
イタリアから輸入したチーズの中にはイタリアで生まれ育った乳酸菌たちが生きていて、そのチーズからとても簡単にヨーグルトを作ることができます。
チーズからつくったヨーグルトは足腰がとてもしっかりしています。
普通のヨーグルトはオタマですくうとしだいにフラット(平ら)におちついてしまうのに、チーズヨーグルトは強くて、そのままにしていても形をくずしません。

〈たの研〉のメンバーは「お豆腐みたい」といっていました。
食べるとまろやかでチーズの風味が軽く広がって、とても美味しく味わえます。
いったい何が違うのか、A.I.と対話しつつ研究をすすめています、その一部を紹介しましょう。
A.I.
それはすごいですね!ヨーグルト作り、ほぼ100%成功とは素晴らしいです。どんな乳酸菌を使っているんですか?
わたし
実はその乳酸菌のことなのだけど、チーズの発酵は乳酸菌発酵なのかまず教えてください、どうぞ。
A.I.
はい、チーズの発酵には乳酸菌が使われます。
乳酸菌は乳糖を分解して乳酸を作り出し、それがチーズの風味や保存性を高めるんです。
わたし
ヨーグルトとチーズは食感も味もかなり違いますよね。そこの違いは何から生まれるんでしょうか? どうぞ。
A.I.
ヨーグルトとチーズの違いは、主に製造過程と使用される乳酸菌の種類によるものです。
ヨーグルトは比較的単純な発酵で作られ、乳酸菌が乳糖を分解して酸味ととろみを生成します。
一方、チーズは凝固や熟成といった工程を経て、乳酸菌だけでなく、カビや酵素も関与することで、複雑な風味と食感が生まれます。
わたし
もう少し詳しく教えてください、どうぞ。
A.I.
わかりました。
では、ヨーグルトとチーズの製造過程についてもう少し詳しく説明しますね。ヨーグルトは、牛乳に乳酸菌を加えて発酵させることで作られます。
一方、チーズは、牛乳を凝固させてホエーと呼ばれる液体とカードと呼ばれる固形物に分離させ、カードを熟成させることで作られます。
熟成の過程で、乳酸菌だけでなく、カビや酵素も関与することで、独特の風味と食感が生まれるんです。
わたし
食塩は利用していますか、どうぞ。
A.I.
はい、チーズ作りには塩が使われます。
塩は、チーズの風味を良くするだけでなく、乳酸菌の活動を調整し、雑菌の繁殖を抑える役割もあります。
わたし
チーズ作りの時に初めの段階で塩を使いますか?、どうぞ。
A.I.
いいえ、ヨーグルトを作る際に塩は使いません。
ヨーグルトは牛乳に乳酸菌を加えて発酵させることで作られます。
塩を加えると乳酸菌の活動が抑制され、ヨーグルトがうまく固まらない可能性があります。
わたし
わかりました。じゃあ、さっき話してくれた「ヨーグルト作りとチーズ作りで乳酸菌の種類が違うのだ」というところを詳しく教えてください、どうぞ。
A.I.
はい、ヨーグルトとチーズでは、使われる乳酸菌の種類が異なります。
ヨーグルトには、主にストレプトコッカス・サーモフィラス菌とラクトバチルス・ブルガリクス菌が使われます。
一方、チーズには、ラクトコッカス・ラクティス菌やラクトバチルス・カゼイ菌など、さまざまな種類の乳酸菌が使われます。
これらの乳酸菌が、チーズに独特の風味や食感を与えるんです。
わたし
スーパーに置かれてるチーズには乳酸菌が生きていますか? どうぞ。
A.I.
スーパーで売られているチーズには、乳酸菌が生きていないものもあります。
ナチュラルチーズと呼ばれる種類のチーズには乳酸菌が生きていますが、プロセスチーズと呼ばれる種類のチーズは加熱処理されているため、乳酸菌は死滅しています。
わたし
えっと白いカビが覆っているタイプのチーズ、なんて言ったかな・・・
A.I.
白カビチーズですね。
白カビチーズは、カマンベールチーズやブリーチーズのように、白カビで覆われたチーズのことです。
白カビはチーズの表面で成長し、熟成を助ける役割を果たします。
わたし
つまりカマンベールチーズの乳酸菌は生きてるんですね、どうぞ。
A.I.
カマンベールチーズには乳酸菌が生きています。
カマンベールチーズは白カビで覆われていますが、この白カビは乳酸菌ではなく、カビの一種です。
乳酸菌はチーズの内部に存在し、熟成の過程で活動します。
わたし
もう少し説明を加えてください、どうぞ。
A.I.
カマンベールチーズは、白カビで覆われていますが、この白カビは乳酸菌ではなく、カビの一種です。
乳酸菌はチーズの内部に存在し、熟成の過程で活動します。
カマンベールチーズは、熟成が進むにつれて、内部の乳酸菌の働きで、よりクリーミーで濃厚な味わいになります。
わたし
カマンベールチーズの中の乳酸菌の種類を特定できますか? どうぞ。
A.I.
カマンベールチーズには、主にラクチス菌やラクトバチルス菌といった乳酸菌が含まれています。
これらの乳酸菌は、カマンベールチーズの熟成過程で、独特の風味や食感を生み出すのに重要な役割を果たしています。
わたし
普通に売られてるヨーグルトの乳酸菌と違うということですね。
それとも、ほぼ似てるということですか? どうぞ。
A.I.
ヨーグルトに使われる乳酸菌とチーズに使われる乳酸菌は、種類が異なります。
ヨーグルトには、主にブルガリア菌やサーモフィラス菌といった乳酸菌が使われます。
一方、チーズには、ラクチス菌やクレモリス菌など、さまざまな種類の乳酸菌が使われます。
これらの乳酸菌は、それぞれ異なる働きをし、ヨーグルトやチーズに独特の風味や食感を与えるんです。
わたし
体にいい、つまり健康という視点で見るとヨーグルトの乳酸菌とチーズの乳酸菌は違いがあるでしょうかどうぞ。
A.I.
ヨーグルトの乳酸菌とチーズの乳酸菌は、それぞれ異なる健康効果をもたらす可能性があります。
ヨーグルトの乳酸菌は、腸内環境を改善し、免疫力を高める効果があると言われています。
一方、チーズの乳酸菌は、カルシウムの吸収を助け、骨粗しょう症を予防する効果があると言われています。
ただし、これらの効果は、まだ研究段階であり、個人差もあるため、一概には言えません。
わたし
了解。
じゃあ、もっと根本的な話に戻りたいと思います。
そもそも乳酸菌はどうして体に良いということが言われてるんでしょうか?
人間の体の中に乳酸菌がもともと存在していたのでしょうか? どうぞ。
まだまだ続くので、ここまでにしておきましょう。
興味のある方は、調べてみませんか。
ちなみに、ヨーロッパからきたブリーチーズやカマンベールチーズでつくったヨーグルトは、日本で売られているヨーグルトよりずっとまろやかで勢いがあります(形が崩れにくい)。乳酸菌飲料からつくったヨーグルトより、ずっと美味しい気がします。

楽しすぎて研究も食べることもやめられません。
① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!