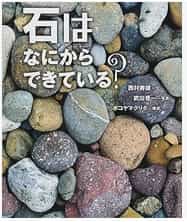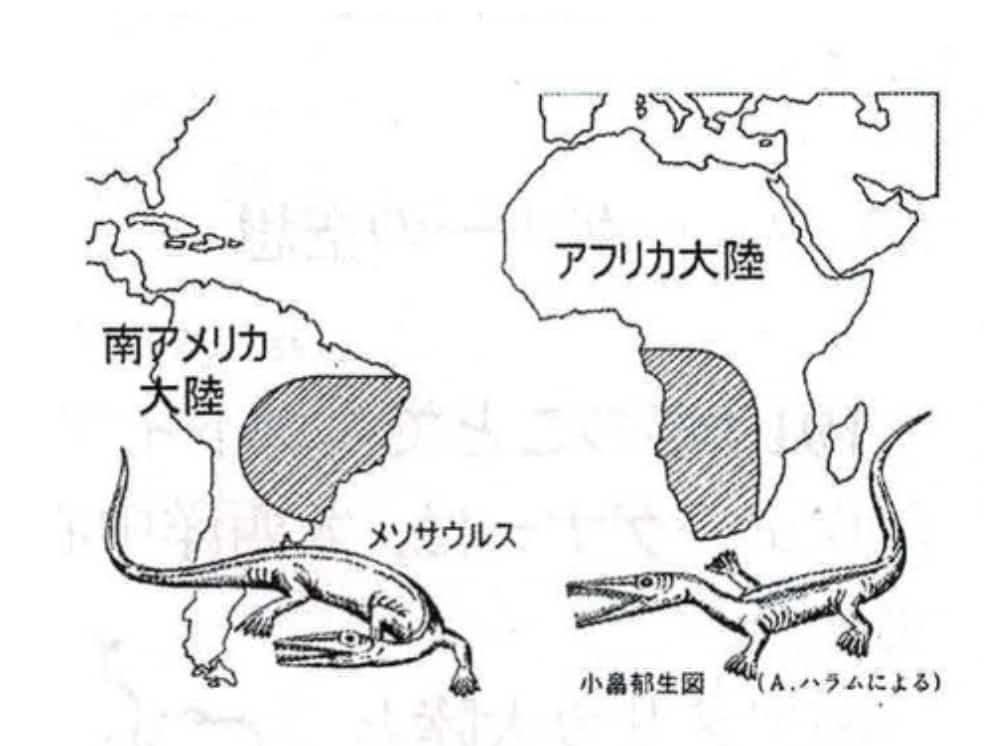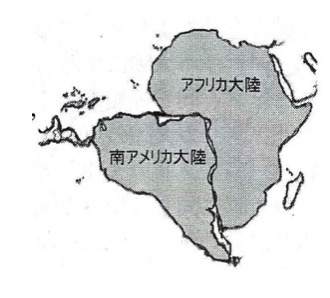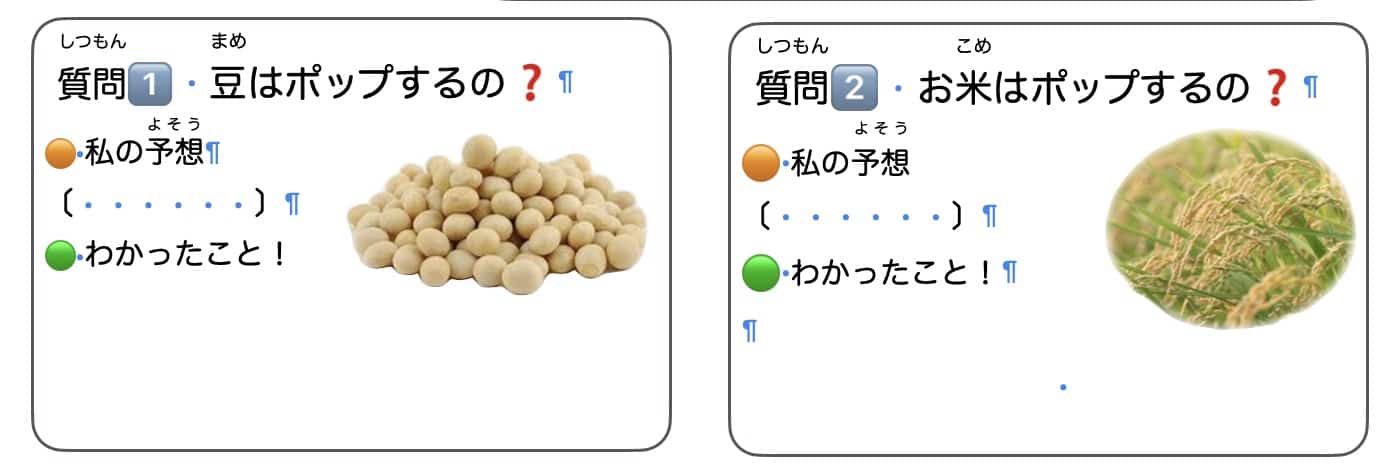最近、友人のA先生との会話の中で、以前カウンセリングした時の方法を思い出して伝えたのだけど、それは「たのしいカウンセリングプログラム」として残しておく価値があるものだっただと気づいて、急ぎまとめはじめています。
以前のカウんセングは「毎週毎週、高圧的な管理職にいろいろ言われてメンタルが持ちそうもない」という内容でした。
相談者の心に最もヒットしたのが、私が提案したアイディアです、うまくいって2回で終了しました。その先生が元気に教師生活を続けていることは、本人や周りの人たちからの情報が入っていて、安心しています。

プログラムをまとめて秋から冬にかけて、たのしい車好きカウンセリング講座を実施します。
PEALカウンセリングは教育だけでなく福祉の場面でも有効です。子どもたちからの相談にアドバイスするだけなら自分の経験や知識でできるかもしれません。けれで相手の心の中で言語化されていない、本人も正確に把握できていない悩みや課題、目標と向き合うのはPEALカウンセリングの実技レッスンが必要です。
自分の問題・課題をたのしく解決したい、周りの人たちから寄せられる相談・悩み事と元気に向き合いたい方は、お問い合わせください。
① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!