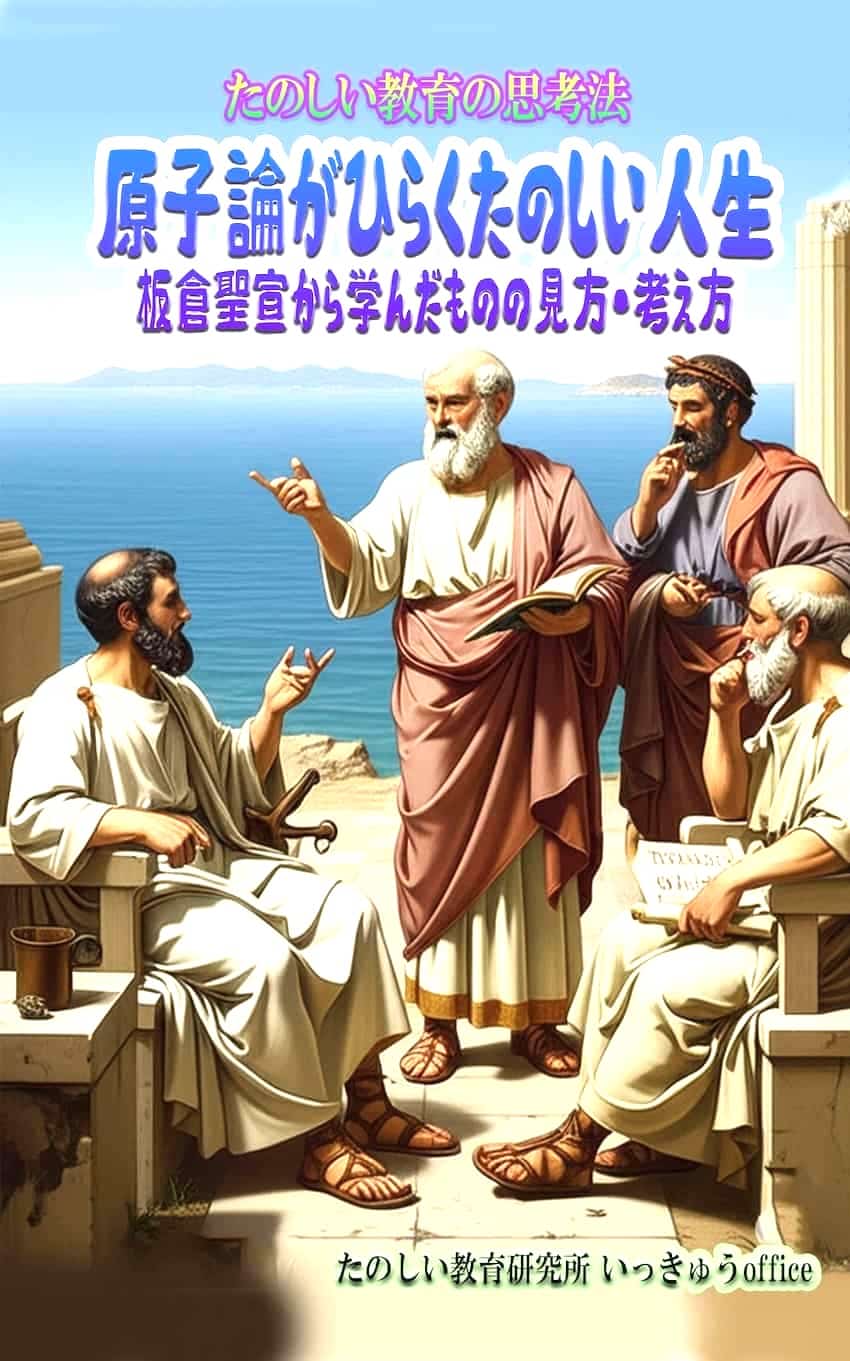これは今までも書いてきたのだけど、転勤先で元気な子どもたちを担当したとき「前の先生は授業でよくアニメ映画をみせていたから先生もみせるべきだ」と激しく要求されたことがあります。きいてみると、ライオンキングとか美女と野獣とか…
たのしい教育派の私は「前の先生の授業はどうなっていたのか」ととても残念な気持ちがしたものです。
もちろん授業で「この先生たのしい、おもしろい」と感じてもらうのが私のモットーです。それが教育のモットーだとも考えています。
とはいえ映画は大好きです。
逃げで映画を使うというのは残念なことです。そうではなく「この単元の12時間の中の2コマ(90分)は映画を観てもいたい」と考えて授業に取り入れることもあります。おそらく普通の先生よりたくさん映画を利用してきたはずです。
今ならたとえば「海の生き物」とか「生態系」、「夏の自由研究」をテーマにこの作品ををとりあげたでしょう、名作です。
| オクトパスの神秘: 海の賢者は語る My Octopus Teacher | |
|---|---|
| 監督・脚本 |
|
 |
|
未見の方は、ぜひご覧ください。
仕事に疲れた男性が、タコに癒され、心を傾けて自由研究するものがたりです。
今月の出版は、先生と保護者の皆さんのための映画ガイドです。
月末になると講座と重なるので、中頃には出したいと考えてます。
ご期待ください!
① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!