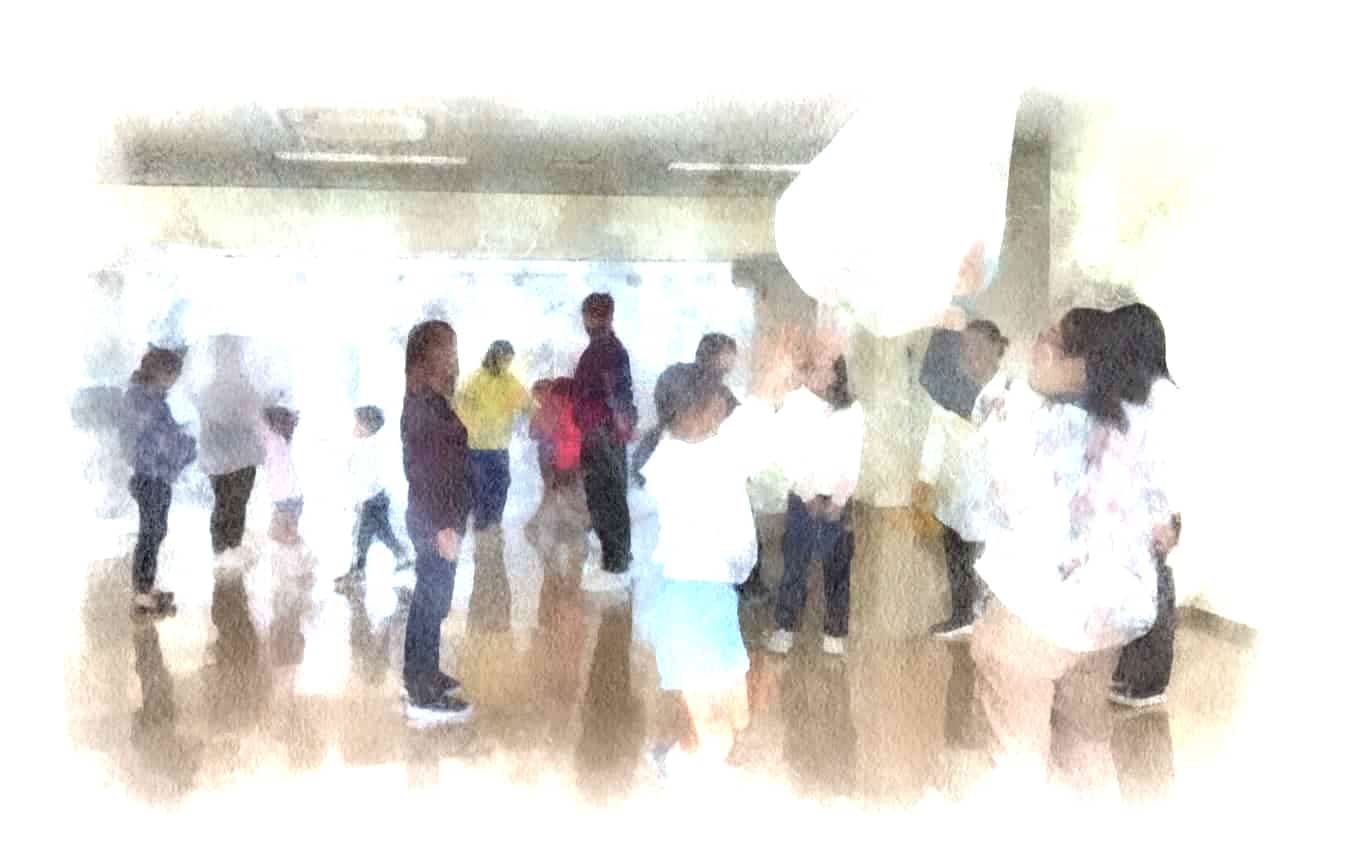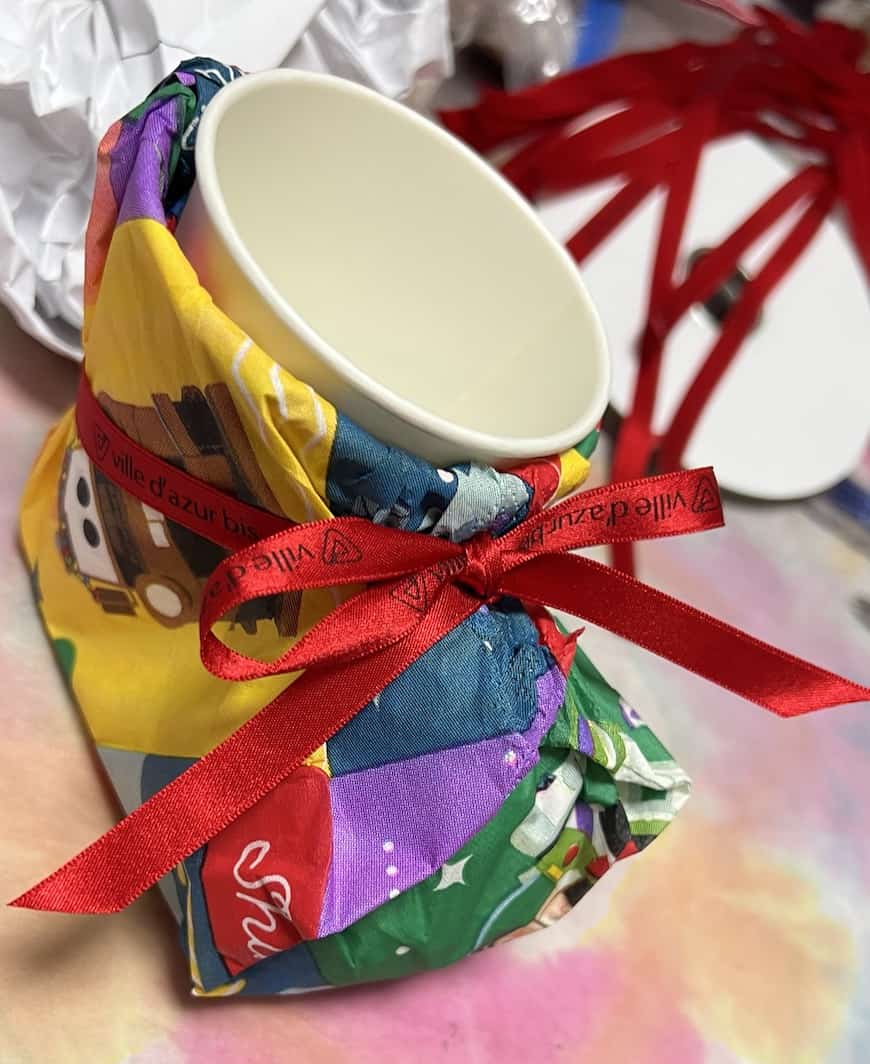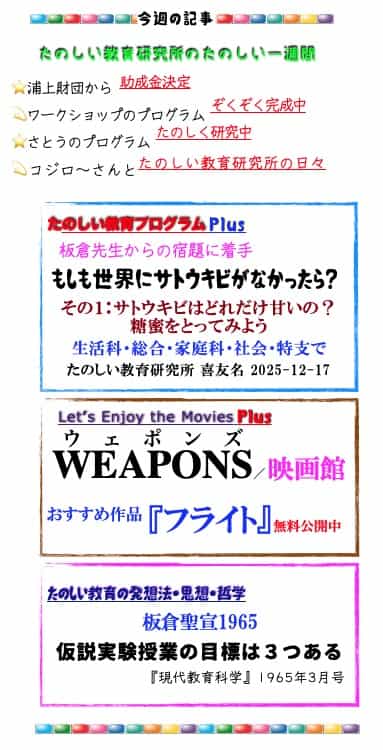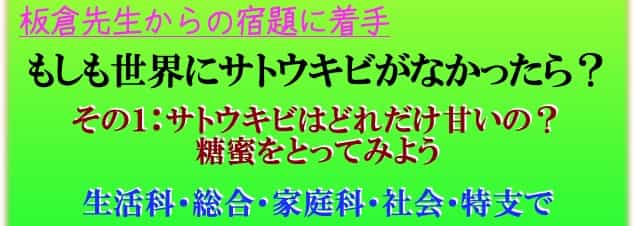〈たの研〉の講座で大ヒットしたプログラムの一つが「音で伝えよう」です。
たとえば「雨」を音だけで相手に伝えるにはどうしますか?

ザーザー とか パラパラ とか?
伝わらなかったら、ピッチャンピッチャンとか、しとしと という音があるでしょう。
風はどうでしょう。

ビュービュー、ピューピュー、そよそよ とかいくつか浮かぶと思います。
では「美味しい」はどうやって伝えたらいいでしょう?

こういう一連の擬音語・擬態語が、とてもたのしいゲームになることがわかって、さくら先生がたのしくまとめてくれました。
このゲームは人間の言葉の進化に密着した大切な内容を含んでいます。だから楽しさ度もとても高いのでしょう。
興味のあるみなさんはお問い合わせください、初期バージョンとしてすでにカードをまとめてたのしい教材になっています。ワークショップを受講することができます。
① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!