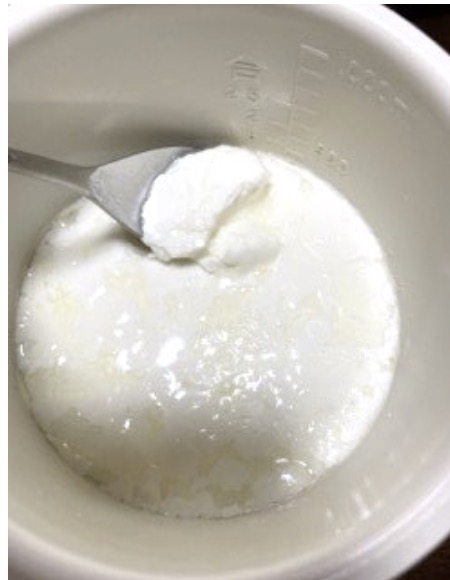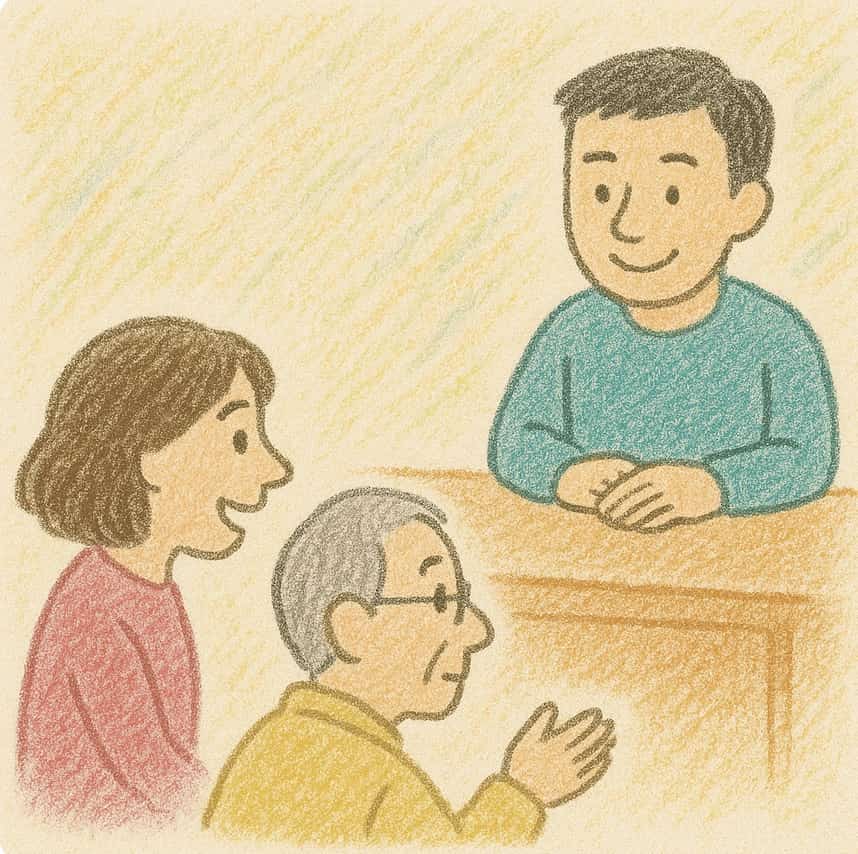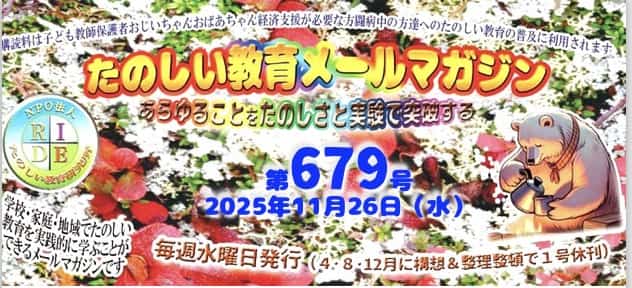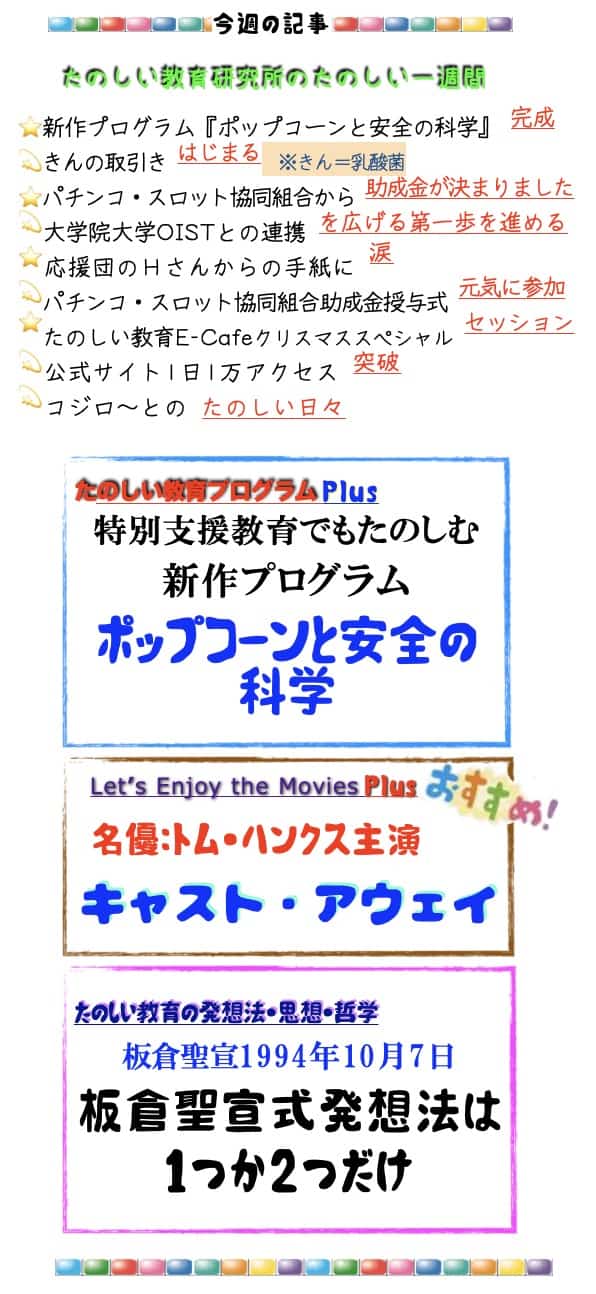最新のメルマガに載せた内容を抽出して少し手を加えて紹介します、「発想法の章」からです。
文科省の教育政策研究所(かつての国立教育研究所)をしていた板倉聖宣先生の著作からです。
今でもとても斬新な話を書いてくれています。
板倉
私の評価論の原則は〈評価はニ段階評価〉です。
「合格」と「不合格」、「わかった」と「わからない」です。
『自由電子が見えたなら』という授業をしたとしたら、例えば「電気を通す」か「通さない」かのどちらなのかということです。
ところが普通は、合格や不合格の中を細かく分けて「スレスレ合格」だとか「スレスレ不合格」だとかいいたくなる。
そんなら私は「もう勝手にしろ」と言うだけです。原則的には〈合格〉と〈不合格〉の二つしかないんです。
どうして「5段階評価」なんてあるかというと、それは教師が教育目的としていないことまでも評価しようとしているからです。
例えば水泳で「少なくとも10mは泳がせたい」と教師が思ったときに、10m泳いだ子どもは全員「合格」でしょ。
先生は10m泳がせたいと思っているのに100m泳ぐ子もいる。1000m泳げる子もいる。
そのとき1000m泳げた者が「5」で、100mくらいが「4」で、10mが「3」だと、どうしてそんなことするんですか。
10m泳がせたいなら10m泳げれば「5」、「合格」でしょ。
「実態評価」ではないんですから。
結局、教師の教育目標の評価としては「合格」 と「不合格」だけなんです。
現実的な評価として「選抜」ということがありますね。
選抜といったって〈合格・不合格〉だけです。
みなさんが大学に入るとき「一等合格」「二等合格」なんてなかったでしょ。「あの人は一等合格だから単位は少なくていい」とかやったらた異変です(笑)例えば「東大の医学部と芸大の音楽部とどちらが上か」という議論ができるかどうか?
これはできないでしょ。
東大の医学部が受かるからといって芸大の音楽部は受かるとは限らない。
これは全然評価基準が違うからです。
にもかかわらずいろいろな大学の入学試験を統一的にテストして、一流から三流までちゃんと区別しようとする者がいて、その意図にのっかっちゃう人がいるわけです。つづく
問題意識を持った取り組みは評価と一体です。
板倉先生には「評価論」という分厚い一冊もあります。興味のある方はぜひお読みください。
① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!