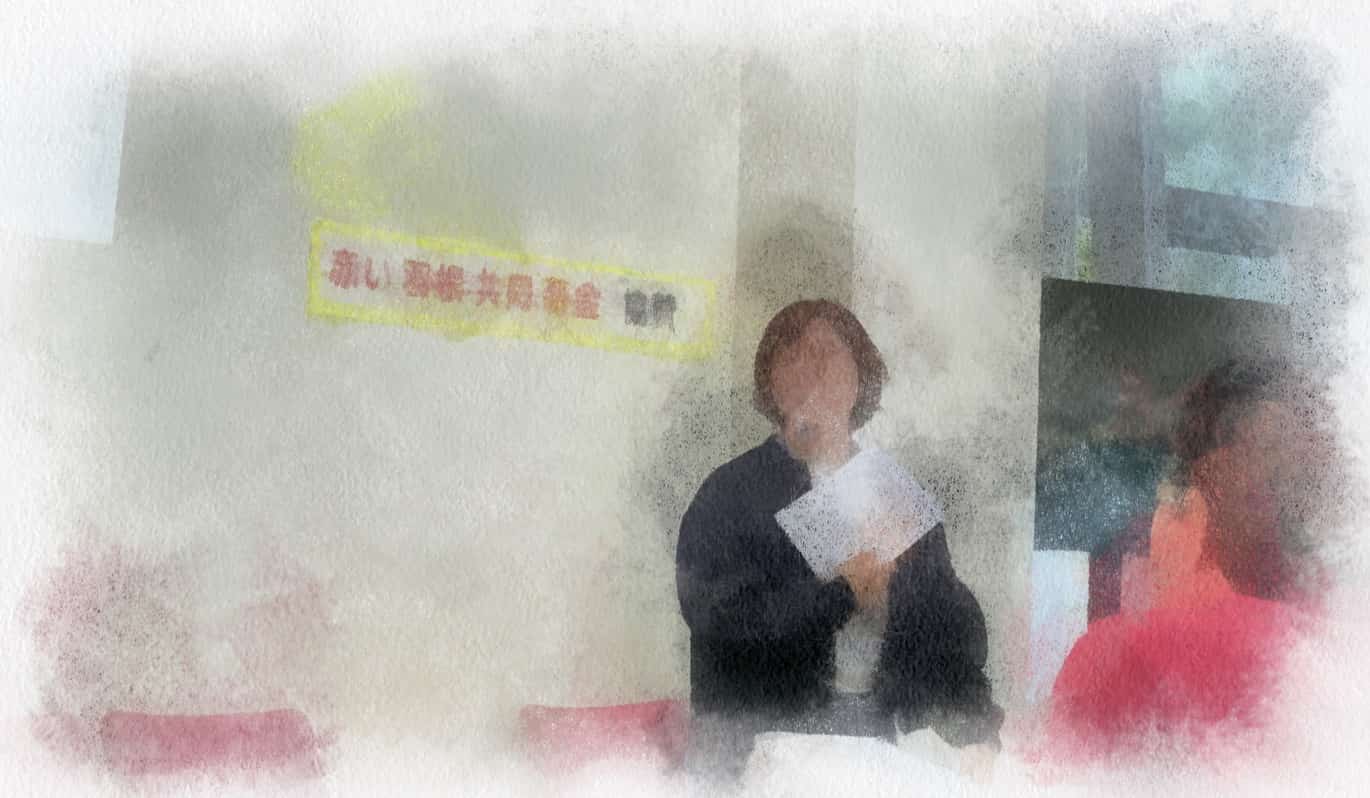〈たのしい教育メールマガジン〉に書いている発想法の章のはじめのあたりを紹介します。
楽しい教育&福祉という視点でも意義深い内容だと思います。
基本的に〈変化〉を好まないのが生物です、周りの環境の変化は命を脅かすこともあるからです。そういう中でチャレンジングな生命体が新しい環境に立ち向かったり、地殻変動などで別な環境に置かれることになったり、そうやってゆっくりと新しい環境に慣れていった生物たちが、今、地球上で過ごしています。
新しい自然環境で暮らす生物が、数千年前、数万年前、数百万年前の環境では暮らすことができるか?
ほぼ無理でしょう。
実は自然環境だけでなく社会環境の変革も同じです。
インターネットが普及した時も多くの批判が飛び交いました。
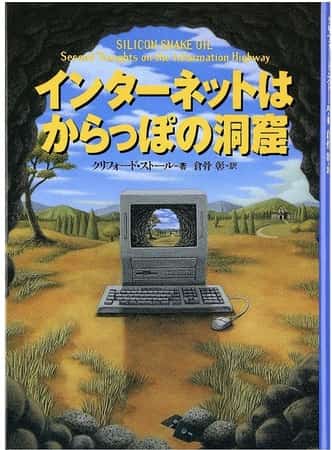
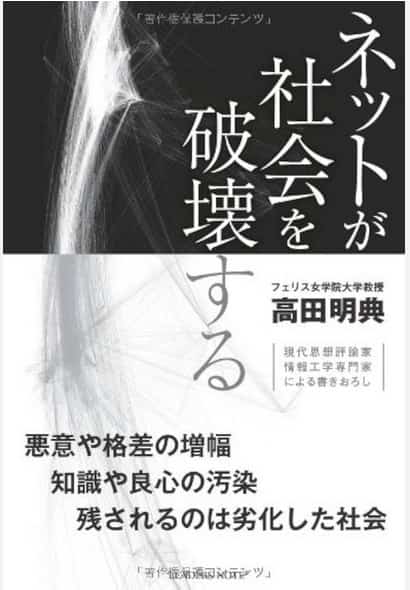
日本の論客として有名な田原総一郎もデジタル教育批判の本を書いています。もちろん今では絶版です。
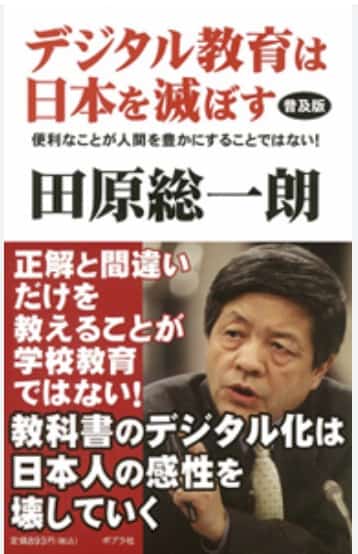
それでもゆっくり社会の中に根を広げていったインターネットは、もう社会に欠かせない基本ツールになりました。
インターネットが崩壊すると手紙や電話の時代に戻ってしまうと考える人がいます、違います。
インターネットが崩壊すると電話回線も機能しなくなります。
郵便局のシステムも崩壊するので手紙を届ける前の状態に戻すことができるかどうか、そのために10年20年という時が必要になるでしょう。
コンビニも信号機も高速道路も機能しなくなりますから、それを古い機械システムに戻すとしても、その間は明治時代くらいの暮らしを続けることになるでしょう。
それほどまでに社会の進化は元に戻れないほど前に前にと進んでいったわけです。
予想以上に長くなりました、1回目はここまでにします。
① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!